オリゴ糖を多く含む食品は?腸内美人になるためのポイントを解説

オリゴ糖は腸内環境を整えられると聞き、いざ食事に取り入れてみようと思ったあなた。「あれ?でも何を食べたらいいんだろう……?」と悩んでいませんか?
オリゴ糖は糖質の仲間でありながら、積極的に摂ることをすすめられている栄養素。しかも、いつも食べている親しみのある食品の中にもオリゴ糖が含まれているのです。
この記事では、どんな食品にオリゴ糖が多く含まれているのか、何を食べると効果を感じやすいのかを紹介します。おすすめの食べ方やレシピなども載っているので、ぜひ参考にしてください。
オリゴ糖は腸内環境を整える低エネルギーの糖類

オリゴ糖は腸内環境を整える作用があり、低エネルギーなので太りにくい糖質であると言われています。そのため、健康志向が高まる現代において人気の栄養素です。
そもそもオリゴ糖とは糖質の仲間であり、ブドウ糖や果糖などの単糖が3~9つくっついたものを指します。私たちがよく摂取しているものだけでも、大豆オリゴ糖やフラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖など、多くの種類があります。
オリゴ糖は人の体では消化しにくいため、体のエネルギーとしてはあまり利用できません。その代わり、腸内にいる善玉細菌のエネルギー源として利用されることが分かっています。エネルギーが足りていれば善玉菌は元気に活動できるため、腸内細菌のバランスが整いやすいです。
オリゴ糖を多く含む食品

では、具体的にどのような食品にオリゴ糖が含まれているのか確認してみましょう。
例えば、次のような食品が挙げられます。
・大豆
・玉ねぎ
・ごぼう
・にんにく
・アスパラ
・バナナ
・牛乳
・ヨーグルト
・はちみつ
多くは私たちが食べ慣れた食品であり、身近なものが多いです。
また、白ご飯や小豆などにもオリゴ糖は含まれています。糖質を含む食品には、微量ながらにオリゴ糖が含まれると考えていただいて大丈夫です。なかでも、今回紹介した9つの食品のオリゴ糖含有量は高いことが分かっています。
オリゴ糖を一番多く含む食品は?

「オリゴ糖をよりたくさん摂れる食品を知りたい!」という方は、次の表をご覧ください。
| オリゴ糖を含む食材 | オリゴ糖の含有割合 |
|---|---|
| きなこ | 7.0% |
| ごぼう | 3.6% |
| 玉ねぎ | 2.8% |
| はちみつ | 1.5% |
| 蒸し大豆 | 1.4% |
| にんにく | 1.0% |
| バナナ | 0.3% |
オリゴ糖の含有率は、きなこが群を抜いて1番多くなっています。次いでごぼう、玉ねぎ、はちみつと続きます。「オリゴ糖をたくさん摂るならきなこが一番なのか!」と思ってしまいがちですが、食品によって1回で食べる量に差があることを忘れないように。
例えば、きな粉ヨーグルトとごぼうの金平を、食事1回量で比べてみましょう。
・きな粉ヨーグルト(使用するきなこは5gと仮定)・・・オリゴ糖0.4g
・ごぼうの金平(使用するごぼう)は50gと仮定)・・・オリゴ糖1.8g
このように、しっかり量を食べられる野菜類の方が、オリゴ糖を取りやすいです。また、大豆やバナナ、ごぼうには食物繊維も含まれているため、腸内細菌がよろこぶエネルギーの源であると言えます。
オリゴ糖は食物繊維や有用菌と一緒に摂るのがベスト

オリゴ糖を摂るときは、食物繊維や有用菌である乳酸菌やビフィズス菌などと一緒に摂ると、さらに腸内の善玉菌が優勢になります。そのため、オリゴ糖と有用菌、食物繊維は一緒に採ることがベストです。
食物繊維やオリゴ糖のように腸内細菌のエサになるものを「プロバイオティクス」と呼びます。一方、善玉菌などを「プレバイオティクス」と言い、両者を同時に摂ることで腸内環境は改善しやすいと考えられています(※)。
オリゴ糖を手軽に摂りたいならシロップやパウダーがおすすめ

オリゴ糖を食品から摂ろうと思うと、少し手間がかかりますよね。それに、毎日ごぼうを食べるのも好きでなければ難しいですし、ましてやオリゴ糖を含む野菜が苦手な方からすれば苦痛でしょう。
そこでおすすめなのが、オリゴ糖を含んだシロップやパウダーを活用することです。オリゴ糖の有用性はさまざまな研究を通して広く認められたため、多くの商品が販売されています。
シロップやバターであれば、飲み物に入れたりパンにかけたりと、日常の食生活の中に取り入れやすいですよね。また、食品では「実際どのくらいのオリゴ糖を摂れたのか」が目視できませんが、オリゴ糖の製品であればきちんと摂取量を把握できます。
かわしま屋では、オリゴ糖のシロップとパウダー両方の扱いがあります。食品由来のオリゴ糖でできているうえ、食物繊維や善玉菌も添加しているので、腸活を考えている方にもピッタリです。

【お試しサイズ】オリゴ糖7種シロップ 260g|腸活シンバイオティクス 乳酸菌・ビフィズス菌・食物繊維プラス -かわしま屋-
オリゴ糖7種と乳酸菌、ビフィズス菌、食物繊維を配合しました。罪悪感なく甘みをプラス、毎日スッキリしたい人におすすめ。家族みんなで使いたいボトルタイプです。
907 円(税抜)

オリゴ糖 (粉末) 腸活シンバイオティクス 150g【送料無料】*メール便での発送*_t1
オリゴ糖(粉末)|8種のオリゴ糖+乳酸菌・ビフィズス菌+食物繊維を独自配合でブレンドした、腸活にオススメのオリゴ糖粉末。ヨーグルトや飲み物にぴったりな、ほんのり優しい甘み。
3480 円(税抜)
また、オリゴ糖は摂り過ぎるとお腹が緩くなりやすいです。パウダーやシロップで摂る際は、1日に2~10gを目安(※)に摂り、自分の体調に合わせながら量を調整してみてくださいね。
オリゴ糖で腸内美人♡おすすめレシピ3選
最後に、オリゴ糖をしっかり補えるおすすめのレシピを紹介します。スッキリしたい・気持ちを軽くしたいという方は、ぜひ一度お試しくださいね。
1.はちみつバナナヨーグルト

材料
- バナナ
- 1本
- はちみつ
- 小さじ2〜
- ヨーグルト
- 大さじ大盛り2杯
つくり方
- 1
- お好きな器に盛り付けるだけ
2.五目煮(4人分)

材料
- 大豆
- 1パック(200g)
- ひじき
- 乾燥で5g~10g
- 人参
- 1/2本
- 油揚げ
- 1枚
- めんつゆ
- 大さじ3
- はちみつ
- 大さじ1
つくり方
- 1
- ひじきは水で戻しておく
- 2
- 人参・油揚げは細切り
- 3
- 鍋を熱し油を入れて温めたら、人参と油揚げを入れて炒める
- 4
- しんなりしたら、戻したひじきと大豆・むき枝豆も入れて炒める
- 5
- 材料にかぶるくらい水を入れ、柔らかくなるまで蓋をして煮込む
- 6
- 調味料を入れ5分ほどコトコト煮込んだら完成
3.豆腐と香味野菜の塩麴炒め

材料
- 豆腐
- 1丁(300g)
- 玉ねぎ
- 1/2個
- アスパラ
- 2本
- しいたけ
- 中サイズ3枚
- 塩麴
- 大さじ1
つくり方
- 1
- 野菜類は細切りにしておく
- 2
- 油はひかずにフライパンへ豆腐を載せ、火にかける
- 3
- 2に1も乗せ、料理酒を回し入れたら蓋をして5~10分加熱
- 4
- 豆腐から水分が出て材料がしんなりしたら塩麴を入れ、水分が飛ぶまでしっかり炒めたら完成(豆腐は好きなサイズに崩しながら炒めてください)
オリゴ糖を含む食品のQ&A
- オリゴ糖はたくさん食べた方が便秘に効きますか?
- オリゴ糖は適量を摂ることが大前提です。多過ぎると下痢になる可能性があるので、摂りすぎないようにしましょう。1日に2~10gが目安です。
- オリゴ糖を一番多く含む食品は何ですか?
- 含有率が高いのはきな粉ですが、食事としてしっかり摂れるのは大豆やごぼうです。
- オリゴ糖はいつまで食べれば効果が持続しますか?
- オリゴ糖や食物繊維、有用菌などは日常的に摂ることで効果を感じやすくなります。そのため、一定期間だけ摂ったとしても、摂らなくなれば効果は減ります。無理をせず、継続できる範囲で摂れるように意識してみましょう。
- オリゴ糖は食品を加熱しても減りませんか?
- 減りませんので、お好きな調理法で食品を召しあがってください。
記事の監修
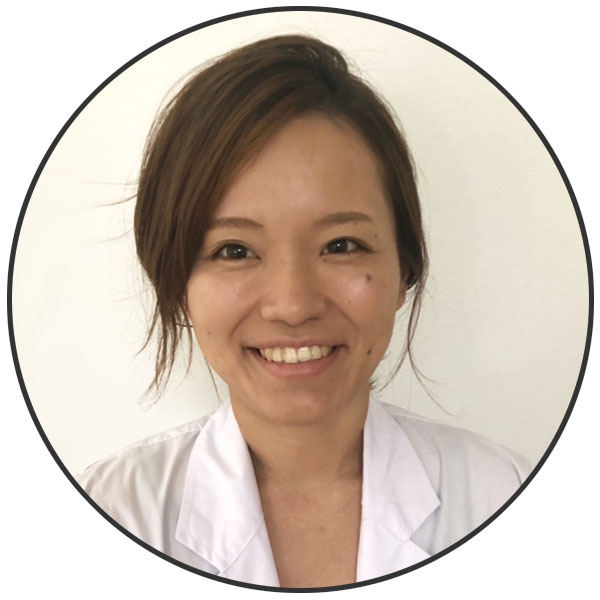
管理栄養士
川野 恵
オリゴ糖は腸内の環境を整える栄養素として有名です。とくに、乳酸菌やビフィズス菌などの有用細菌との同時摂取で効果が出やすいことが分かっています。私が個人的におすすめしている食材が、発酵食品でありオリゴ糖を含む大豆原料である納豆です。納豆には食物繊維も豊富に含まれるため、腸内の環境を改善したいときのサポート役に向いています。オリゴ糖を含む食品に苦手なものが多い方は、パウダーやシロップでオリゴ糖を摂るのも検討してもいいですね。オリゴ糖を摂ることでガスが溜まりやすい腸の方もいるので、違和感があるときは無理に使用せず、体調に合わせて食べるようにしてくださいね。

























