クコの実の栄養と効果効能|おすすめの食べ方とレシピもご紹介。
記事の監修
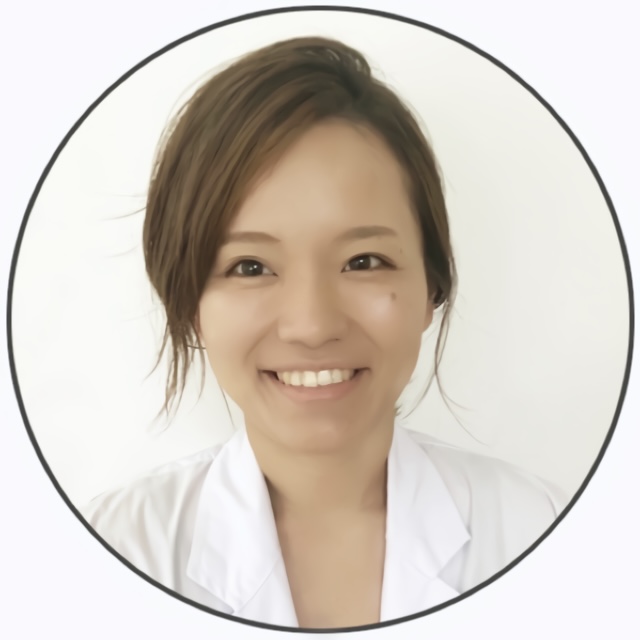
管理栄養士
川野 恵
フリーランスの管理栄養士としてレシピ開発や栄養のコラム作成のほか、外食チェーン店でのダイエットを意識した食べ方を紹介。現在はクリニックにて、生活習慣病などに悩む方々へ栄養指導を行なっている。

はっと目をひく赤い色で料理に彩りを添えてくれるクコの実。
デザートなどに飾られることが多いため「添え物」というイメージをもっている方も多いかもしれませんが、実は古くから不老長寿や滋養強壮の妙薬として知られてきた生薬です。
今回は、クコの実にぎゅっと詰まった栄養と効能、そして本場中国や韓国、クコの実がブレイク中のアメリカで楽しまれているおすすめの食べ方をご紹介します!
クコの実とは

古くから中国で栽培され、その実が強精作用のある食べ物として親しまれているクコ(枸杞)。
ナス科の低木で、日本でも各地で自生しています。
日本では「杏仁豆腐」の上にのっている赤い小さなドライフルーツとしておなじみですが、中国の古典薬学書『神農本草経』の中では最もランクの高い「上品薬」(少ない副作用で身体を養う薬)。
れっきとした生薬であり、薬膳や漢方薬の材料です。
クコは、中国では春の新芽(天精草)や夏の茎(長生藤)、秋の実(枸杞子)、冬の根(仙人杖)のすべてが宝だといわれており、それぞれさまざまな症状に使用されています。
日本では、平安時代に文徳天皇がクコ園を作り、実や若葉を愛用していたそうですが、その管理人が120歳まで健やかに生きたという逸話があるそうです。
このクコの実は近年欧米でもスーパーフードとして注目を集めており、ゴジベリー(英語:Goji berry)と呼ばれてエキスやタブレットなどのサプリメントにも加工されています。
クコの実の栄養

クコの実には40種類以上の有効成分が含まれていることが確認されており、ビタミンA、B類、C、カルシウム、リン、鉄、ニコチン酸、ルチンなどの栄養素が豊富であるといわれています。
特徴的な栄養成分としては、アミノ酸の一種であるベタインやカロテノイドの一種であるゼアキサンチン、クコの実特有のLBP(クコ多糖類)などがあり、これらがクコの実の健康効果に大きく寄与しているようです。
気になるカロリーは、ドライの状態で318kcal/100g。
ヘルシーなイメージですが、同じドライフルーツであるレーズン(301kcal/100g)と比べてちょっと高め。
健康に良いからといって食べ過ぎると太るので、「毎日少しずつ」を心がけるのがよさそうです。
クコの実の効果・効能
中国では、身体の弱った人や老人にもすすんで食べさせるというクコの実。中医学では「肝、腎の機能を高める」とされ、老人の口の渇きや男性不妊などといった症状の治療にも使われているようです。
梁晨千鶴『東方栄養新書』(メディカルユーコン社)などを参考にクコの実の効果・効能をまとめました。
効果・効能1 コレステロール値・中性脂肪値の降下作用

クコの実には肝細胞の再生を促して、動脈硬化を予防する効能があるそうです。
クコの実に含まれるベタインという成分には脂質代謝を改善する効能があり、その結果コレステロール値や中性脂肪値を降下させ、心疾患の予防に貢献すると考えられています。
効果・効能2 血糖値の降下作用

クコの実には血糖値を下げる効果があることが分かっています。
お酒に入れて食前酒としていただいたり、食事の前にクコのお茶を飲んだりすることで、食後血糖値を上げづらくする効果が期待できそうです。
効果・効能3 血圧降下作用

クコの実には血圧を降下させる作用があることが分かっています。
この効能はクコの葉にもあり、蒸して日に干したクコ葉をお茶にして飲むとよいといわれています。
効果・効能4 抗酸化作用・アンチエイジング作用
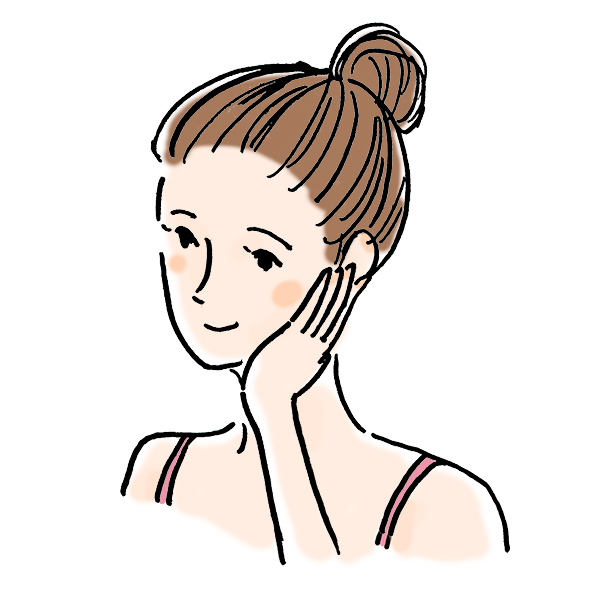
クコの実に含まれるクコ多糖類(LBP)には抗酸化作用があり、生活習慣病の予防や老化の抑制に効果的であるほか、細胞の免疫機能を高めてがん細胞の増殖を抑制する効果もあるといわれています。
効果・効能5 美容(美白)効果

クコの実の抽出エキスを使った実験で、紫外線を浴びた肌に炎症が起きるのを抑える効果、肌が黒くなるのを抑える効果が報告されています。黒くなった肌の回復を助ける効果もあると考えられており、シミのできにくい肌をつくる可能性が期待されています。
クコの実のおいしい食べ方

スーパーフードの中でも手軽に摂れるクコの実ですが、毎日継続して摂るとなるとそのまま食べるだけでは飽きてしまいますよね。
できれば毎日の食事やお菓子作りに活かしてみたい!という方のために、クコの実の味とおいしい食べ方をご紹介します。
クコの実ってどんな味?
クコの実は生で食べると渋く、甘みも薄くておいしくないため、生で流通することはほぼありません。
ドライのクコの実は甘酸っぱく、わずかに苦みのある味をしています。
レーズンのように強い味ではなく、やさしくやわらかい味で、食感も口当たりがよいのが特徴です。味に主張がないため、食事に入れてもその味には大きな変化を及ぼしません。
クコの実の食べ方いろいろ
長年クコの実を食べてきた歴史をもつ中国や薬膳の盛んな韓国、さらに近年クコの実が流行中というアメリカでの食べ方をご紹介します。
 |
<薬膳料理に> 中国や韓国では、クコの実を鍋やスープなどに入れることが多いようです。 おかゆやあんかけなどとろみのある料理にも使われます。 『薬膳・漢方食材&食べ合わせ手帖』(西東社)では相性のよい食材として同様に抗酸化作用のあるやまのいもやはちみつ、目の疲労を回復するといわれている菊の花などが挙げられています。 |
 |
<デザートに> クコの実といえばまず思い浮かぶのが杏仁豆腐。その他に「オーギョーチ」という甘酸っぱいゼリーに使ったり、同じようになつめやキクラゲなどの薬膳食材を使ったデザートの中に入れられることもあります。 クコの実自体には強い味がないため、甘さや酸っぱさ、香りなどを補ってくれる食材と好相性。日本でははちみつレモン漬けが人気のようです。 |
 |
<飲み物として> 韓国では血や肝臓によいとして「クコの実茶」が飲まれます。作り方はコップ1杯に対して大さじ1のクコの実を入れ、お湯を注ぐだけ。 お酒に浸けた「クコ酒」も滋養強壮や美容、眼精疲労などに効くとされて人気です。 ホワイトリカー1.8リットルに対してドライのクコの実を200グラム浸けて手作りすることもできます。 |
 |
<アメリカでは…> アメリカではスーパーフードの一種として扱われているクコの実。主にデザートとして使われ、ナッツやモリンガなどとともにグラノーラにしたり、カカオやチアシード、ヨーグルトなどと一緒にローフードのエナジーバーやチアプディングを作ったりと、他のスーパーフードと一緒に使われることが多いようです。 雑穀と一緒にサラダに混ぜたり、ディップやバーベキューソースの材料にするというアイデアもありました。 |
クコの実を調理するときの注意点
伝統的にスープなどに入れられることが多いクコの実ですが、熱に弱いビタミンC、ビタミンB1、ルチンなどの成分が含まれるため、加熱しすぎない方がよいようです。
鍋に入れるタイミングは仕上げに近い方がいいでしょう。
また、βカロテンを摂りたい場合は油を使って調理すると効率的に吸収することができます。
クコの実の戻し方
ドライのクコの実は、水に入れれば30分程度でふっくらとしてきます。
スープなどの料理に入れたい場合は、水で戻さずにそのまま入れてしまってもOKです。
焼き菓子などに入れたい場合は、レーズンを使うときと同様にラム酒などで戻したり、アップルジュースやオレンジジュースで戻したりすることも。
水分に栄養が溶け出るので、戻すときに使った汁も飲んでしまいましょう。
クコの実に副作用はあるの?

中国の古典薬学書では副作用の少ない薬として紹介されているクコの実。
中医学では無毒でどのような体質にも合うとされていますが、もちろん食べ過ぎは禁物です。
カロリーや糖質を摂りすぎたり、身体のバランスを崩したりしないよう、摂取量は1日に15g~20gを限度に、食べる量に注意しましょう。
また、クコの実はビタミンK拮抗薬である「ワルファリン」との相互作用を起こす可能性があるとされています。
ワルファリンを服用している方は食べないように気をつけてください。
『薬膳・漢方食材&食べ合わせ手帖』(西東社)によれば、クコの実はカニとの食べ合わせが悪いとされ、胃腸の悪い人がクコの実とカニを食べ合わせるとお腹を壊す原因になるとのこと。
胃腸が弱い方は食べ合わせにも気をつけてくださいね。
クコの実は妊婦が食べても大丈夫?
医学博士による前述の書『東方栄養新書』(メディカルユーコン社)によれば、クコの実は妊娠中の方や子ども、老人などどのような体質の方でも食べられるとのことです。
一方で、現代医学における実験では安全性が確認されていないため、「妊娠中・授乳中の安全性については信頼できる十分な情報が見当たらないため、摂取を避ける」としている情報もあります。
かかりつけの医師に相談することをおすすめします。
おすすめクコの実レシピ
やさしい味わいでどんな料理にも溶け込むクコの実。
ここに挙げた以外にも、中華風のスープやあんかけなどさまざまな料理に鮮やかな彩りと栄養をプラスしてくれますよ。
サムゲタン
今回は、日本でも手軽に作れる漢方材料抜きのレシピをご紹介します。
4人分
120分

材料
- ・丸鶏
- 1羽
- ・もち米
- 50g
- ・なつめ(ドライ)
- 6個
- ・松の実
- 大さじ1
- ・クコの実(ドライ)
- 大さじ1
- ・生栗
- 8個(皮と薄皮を剥いたもの)
- ・にんにく
- 5かけ
- ・しょうが
- 親指大(スライス)
- ・長ネギ
- 1本(青い部分のみ)
- ・昆布
- 10㎝
- ・水
- 1300ml
- ・塩
- 適量
つくり方
- 1
- もち米は、炊く半日前に洗って水(分量外)に浸けておきます。昆布を水1300mlに浸けておきます。
- 2
- 丸鶏はお腹の中をきれいに洗い、拭いておきます。尾の部分を切って取り除きます。なつめ、クコの実を水(分量外)に浸けておきます。
- 3
- 丸鶏のお腹の中に、水を切ったもち米と松の実、栗となつめの半量を詰め、タコ糸で縫い合わせます。竹串や楊枝で留めてもOK。足もクロスさせてタコ糸で縛ります。
- 4
- 鍋に3の丸鶏を入れ、1の水を昆布ごと注ぎます。皮を剥いてつぶしたにんにくとスライスしたしょうが、青ネギ、なつめ(戻し汁ごと)を入れ、火にかけます。
- 5
- 沸騰直前に昆布を取り出し、沸騰したら弱火にし、入れてアクを取り除きながら2時間煮込みます。
- 6
- 火を止めて塩を入れ、長ネギ、しょうが、にんにくを取り出し、浮いてきた余分な脂をすくいます。
- 7
- クコの実(汁ごと)を入れてできあがりです。
鶏と木の実、クコの実の中華粥
日本では病人食のイメージがあるお粥ですが、中国では毎日のように食べられるメニューのひとつ。
朝食やランチにもどうぞ。
2人分
40分

材料
- ・米
- 1合
- ・鶏もも肉
- 1枚
- ・長ネギ
- 10㎝(青い部分のみ)
- ・しょうが
- 親指の爪大
- ・クコの実
- 大さじ2
- ・松の実、クルミ
- 各大さじ2
- ・レタス
- 適量(好みで)
- ・熱湯
- 2000ml
- ・ごま油
- 大さじ1
- ・塩
- 適量
つくり方
- 1
- 米は洗って水を切っておきます。クコの実は水(分量外)に浸します。
しょうがはスライスして細切りにします。
- 2
- 鍋にごま油を入れて強火でしょうがと米を炒めます。
油がなじんだら熱湯を注ぎ、一口大に切った鶏肉と長ネギを入れます。
- 3
- 沸騰したらアクをとり、肉が柔らかくなって米が煮えるまで弱火にかけます。
途中で長ネギを取り出します。
- 4
- 塩で味をととのえ、上にちぎったレタスと松の実、クルミ、クコの実をトッピングしてできあがりです。
クコの実となつめのシフォンケーキ
ここでは同じ漢方材料のなつめを使いましたが、より味のはっきりしたレーズンやオレンジピールなどと組み合わせても。
紅茶やほうじ茶の茶葉などを入れて香りにアクセントをつけるのもいいでしょう。
2人分
100分

材料
- ・強力粉
- 200g
- ・グラニュー糖
- 80g(生地に入れる分)
- ・グラニュー糖
- 80g(卵白に入れる分)
- ・ベーキングパウダー
- 小さじ2
- ・塩
- ひとつまみ
- ・水
- 135ml
- ・植物油
- 90ml
- ・卵黄
- 5個分(溶きほぐす)
- ・卵白
- 6個分
- ・なつめ
- 30g
- ・クコの実
- 30g
つくり方
- 1
- 強力粉、グラニュー糖80g、ベーキングパウダー、塩を合わせてボウルにふるいます。
なつめとクコの実は小さく刻んでおきます。
- 2
- 1のボウルに水、溶きほぐした卵黄、油を入れて、泡だて器で混ぜて均一な生地を作ります。
- 3
- 別のボウルで卵白を泡立てます。ハンドミキサーを使うと便利です。
ふわふわと泡がたってきたらグラニュー糖80gを3回に分けて加え、ピンと角が立つまでしっかりと泡立てます。
- 4
- オーブンを160℃に予熱します。2に3の1/3を加えてよく混ぜ合わせ、刻んでおいたなつめ、クコの実と一緒に残りのメレンゲに加えて、泡を消さないように混ぜ合わせます。
- 5
- シフォンケーキの型に4を流し込み、160℃で約60分焼きます。
- 6
- 焼きあがったら逆さにして完全に冷まし、ナイフを使って型からケーキを抜いてできあがりです。
●管理栄養士からのコメント
中華料理でよく見かけるクコの実は、栄養価の高いフルーツのひとつです。
クコの実はとくに「美味しい」と感じる食材ではないため、食べるのを避けていたという方も多いのではないでしょうか。
血糖値や血中脂質の高値は、現代の食事(糖質や脂質が多い食事)を続ける成人によく見られる症状です。この状態が長く続くと、糖尿病や脂質異常症などの疾患へとすすんでしまいます。
そのため、クコの実のように食後の血液の状態を整えるサポート力がある食品は、意識して摂るようにしましょう。
ただし、クコの実が入っているからと甘いお菓子やスイーツを食べ過ぎないように。わたしのおすすめは、クコの実を3個ほど浮かべた温かいお茶を常飲することです。
飲み終わるころには柔らかくなっているので、クコの実だけでも食べやすいですよ。
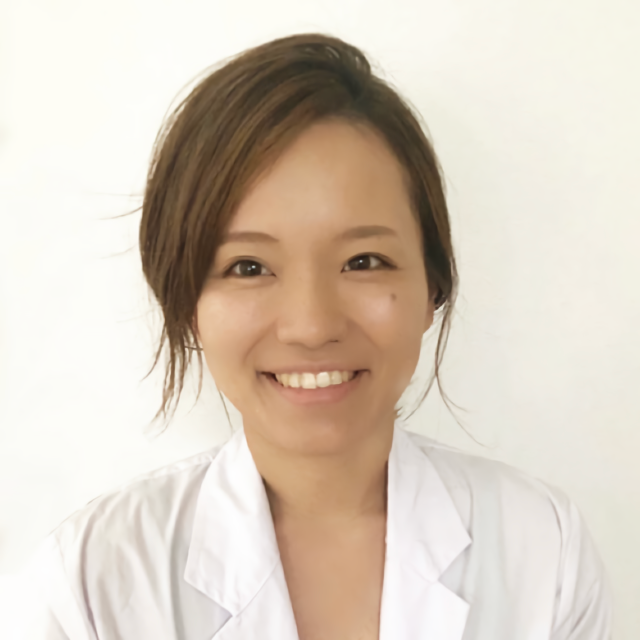
管理栄養士プロフィール
◎川野 恵
給食委託会社や仕出し弁当屋での献立作成を経験後、出産を機にフリーランスとして活動。
フリーランスの管理栄養士としてレシピ開発や栄養のコラム作成のほか、外食チェーン店でのダイエットを意識した食べ方を紹介。現在はクリニックにて、生活習慣病などに悩む方々へ栄養指導を行なっている。
身体は食べ物でできている事を意識し、健康で過ごせるよう多くの方を支えていける管理栄養士になりたいと日々活動しています。
SNSやブログを通して、
・管理栄養士として栄養指導に携わりたい!
・血圧や血糖など血液結果を注意された!
・美味しく食べてきれいに痩せたい!
という悩みを解決するための情報を発信しています。
▼Twitter
@kawa040508
クコの実についてのQ&A
- クコの実は日本で栽培できますか? 日本産のクコの実はありますか?
- クコの実は日本でも栽培できますが、市販のクコの実はほとんどが中国産です。
中国産のものの中では、寧夏回族自治区のものが品質がよく、薬効が高いとされているそうです。
- クコの実でダイエットができるという話を聞きました。
- クコの実には血糖値を降下させる作用があり、肥満の改善に効果があるともいわれています。
食べ過ぎは逆効果ですので適量を守り、普段の食事に取り入れる程度にどうぞ。
- クコの実の保存方法を教えてください。
- クコの実の有効成分LBPは酸化しやすいので、必ず密封し、直射日光を避けて涼しい場所で保管してください。
- クコの実が黒くなってしまったのですが…。
- 黒く変色したクコの実は酸化してしまったと考えてください。食べるのはおすすめしません。






 もくじ
もくじ
















