難消化性デキストリンとは。健康やダイエットに効果的な理由を解説

「難消化性デキストリンが体に良いと聞いたけど、本当なの?」
「なんだか難しそうな名前だけど、どういうものなの?」
…と思っている方が多いのではないでしょうか?
確かに名前が難しそうだし、名前からはどういうものか想像がつきません。
そこで今回は、難消化性デキストリンの正体やその効果について、詳しくご紹介していきたいと思います。
難消化性デキストリンとは

難消化性デキストリンは水溶性食物繊維の一つです。
食物繊維と聞くと一気に身近に感じられるのではないでしょうか。
そんな難消化性デキストリンは天然のデンプンを原料として作られます。
そして原料であるデンプンは、ほとんどがトウモロコシ由来。
難消化性デキストリンは、「トウモロコシから作られた食物繊維」ということですね。
難消化性デキストリンが誕生した理由
近年、日本では食の欧米化によって和食中心の食生活ではなくなってきました。
そうすると、和食にはたっぷりと含まれていた食物繊維が不足しがちになります。
食物繊維は私たちの体にとってとても良い働きをしてくれます。
例えば腸内細菌のエサとなり大腸内の環境を良い状態で保ってくたり、便の体積を増やしてくれたり。
そんな多くのメリットをもつ食物繊維が不足すると、困ってしまいますね。
そこで、食物繊維不足を改善する目的で作られたのが「難消化性デキストリン」なのです。
難消化性デキストリンは、食物繊維が不足しがちな私たちの食生活を補ってくれる役割を担っているのです。
どのように使われているの?
では実際に、難消化性デキストリンとはどのようにして利用されているか具体的にみていきましょう。
利用される場面としては以下の3つです。
1. 食物繊維素材として利用される

みなさんは”食物繊維入り”と書かれた食品を見たことがあるでしょうか?
あまり注意して見たことがないかもしれませんが、このような「食品表示」にはちゃんとした決まりがあるのです。
例えば「食物繊維入り」を表示したい場合なら、100g当たり3g(飲料は1.5g/100ml)の食物繊維を含んでいなければいけません。
このように、食物繊維に対した食品表示を行うために利用される場合があります。
2. カロリーオフや物性として利用される

生活習慣病が問題とされる昨今、カロリーオフや低カロリーを目的とした食品も数多く開発されています。
しかしながら、”カロリー=おいしさ”とはうまく言ったものです。
そこまではいかなくとも、商品開発をする上で”低カロリー”と”美味しさ”を両立することは、極めて難しいことなのです。
そこで活躍するのが難消化性デキストリンです。
食物繊維だからカロリーはかなり低く、食品に利用してもカロリーが増えません。
また脂肪と似たようなテクスチャーを持つため、アイスクリームやドレッシング、ポタージュなどといった食品で活躍します。
3. 生理機能として利用される
難消化性デキストリンは多くの健康作用を持っています。(下記で解説)
そのため特定保健用食品の関与成分として利用され、食品へ付加価値をつけることに役立っています。
特に”おなかの調子を整える”といった表記と共に利用されています。
難消化性デキストリンの健康効果・健康作用

上記では難消化性デキストリンについてざっくりと説明しました。
どんなものなのか、どのように利用されてるのかが分かったかと思います。
では次に、難消化性デキストリンの健康作用についてみていきましょう。
1. 糖の吸収スピードを遅らせる(血糖値を急激に上げない)

難消化性デキストリンには食後高血糖を抑制する効果があることがわかっています。
食事とともに難消化性デキストリンを摂取すると、食後の血糖値の上昇が緩やかになるのです。
食後高血糖は生活習慣病の発症リスクを増加させる一つの要因。
つまり、難消化性デキストリンには生活習慣病の発症リスクを低減する効果があるといえるのです。
2. 整腸作用
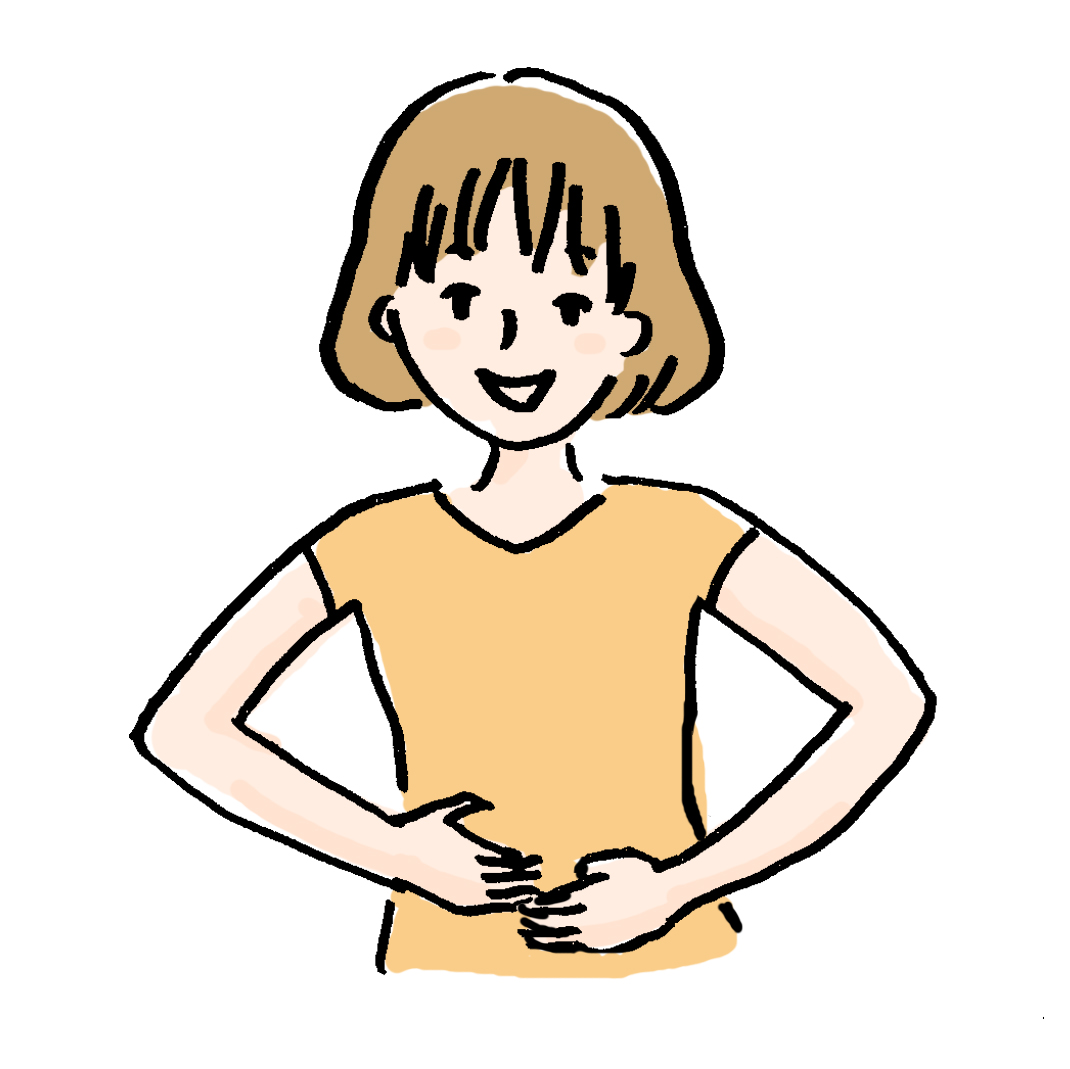
難消化性デキストリンには便の体積および回数を増やす効果があることがわかっています。
水溶性食物繊維である難消化性デキストリンは、食物繊維として便の体積を増やす効果を発揮します。
また、水溶性食物繊維は大腸菌のエサとしても好まれ、腸内環境を整えるカギとなります。
難消化性デキストリンは、2つの面から整腸作用を促してくれるのです。
3. 中性脂肪の吸収スピードを遅らせる(中性脂肪を急激に上げない)

難消化性デキストリンには食後の中性脂肪上昇を抑制する効果があることがわかっています。
食事とともに難消化性デキストリンを摂取することで、食後の中性脂肪値の上昇が緩やかになるのです。
中性脂肪の急激な上昇は血管に負荷をかけ、必要以上に吸収された中性脂肪は体に蓄えられていきます。
そうなると体にとって良くないことは明らかで、生活習慣病の発症に繋がりかねません。
また食後の中性脂肪上昇が抑制されるということは、中性脂肪の吸収スピードを遅らせるということでもあります。
つまり過剰な中性脂肪を吸収せずに済み、”上昇抑制”と”吸収抑制”の2つの面で生活習慣病の予防になるのです。
4. 内臓脂肪の低減作用

難消化性デキストリンには内臓脂肪を減少させる効果があることがわかっています。
これは上記で説明した「中性脂肪の吸収スピードを遅らせる」ことに関係していています。
そもそも内臓脂肪は、必要以上に吸収された中性脂肪が体内に蓄えられたもの。
つまり、吸収される中性脂肪が少なければ、蓄えられないということ。
難消化性デキストリンによって吸収される脂肪が少なくなることで、エネルギー源として内臓脂肪が利用されていきます。
よって、難消化性デキストリンによって内臓脂肪が減少しやすくなるというわけなんですね。
5. 血清脂質の低下作用
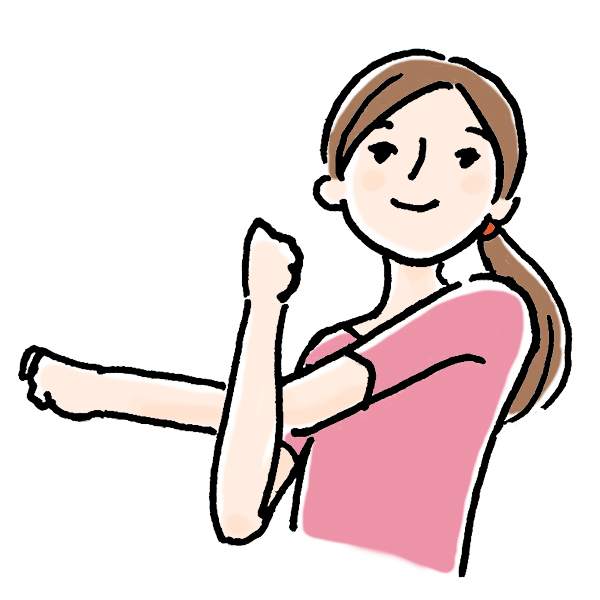
難消化性デキストリンには「血中の中性脂肪とコレステロール値を低下させる効果がある」ことがわかっています。
(中性脂肪の低下については上記「3と4」をご覧ください。)
コレステロール値については、「2.整腸作用」に関連があります。
難消化性デキストリンは排便を促進しますが、この時、便と一緒に排出される”胆汁酸”というものがあります。
胆汁酸はコレステロールから作られているため、体外に排出されることで体内のコレステロール値を低下させることに繋がるのです。
つまり難消化性デキストリンは、間接的に体内のコレステロール値を低下させてくれるということなんです。
6. ミネラルの吸収促進作用

動物実験の結果、難消化性デキストリンにはミネラルの吸収率を高める効果があることがわかっています。
ミネラルは人体の生理機能を維持・調節するために欠かせない物質なので、とても嬉しい効果です。
また人を対象とした実験では、難消化性デキストリンによって血液中の鉄分の値が上昇(改善)したことも確認されています。
鉄分が不足しがちな女性には特にありがたい効果といえるでしょう。
難消化性デキストリンはダイエット効果が期待できる

難消化性デキストリンはダイエットに良い、と聞いたことがありませんか?
確かに難消化性デキストリンはその性質から、ダイエット効果が期待できると考えられています。
具体的にどういうことなのか、みていきましょう。
糖の吸収スピードが緩やかになる
糖の吸収スピードが緩やかになることは、体脂肪合成に関係しています。
体脂肪は体脂肪を合成するホルモンが作用して生成されますが、このホルモンは食後に増加しやすいのです。
その理由は、食後の血糖値上昇によってホルモンが分泌されるからです。
また血糖値の上昇が急激・頻繁な場合はホルモンも過剰に分泌されてしまいます。
ですが逆を言えば、食後の血糖値上昇を抑制すれば、体脂肪合成ホルモンも抑制できる、ということ。
難消化性デキストリンは食後の血糖値上昇を緩やかにしてくれる効果をもっているため、ダイエットへの効果が期待できるのです。
腸内環境の改善が期待できる

太りにくい体をつくるために大切なのが腸内環境。
なぜなら、腸内環境が乱れていると代謝が低下したり、糖を吸収しやすくなってしまうからです。
水溶性食物繊維である難消化性デキストリンは、二つの面で整腸作用を発揮します。
一つが便の体積を増加させること。
食物繊維は分解されずに便として体積を増加させ、排便を促します。
もう一つは大腸菌のエサとなること。
水溶性食物繊維は大腸菌のエサとして好まれるため、大腸菌を元気にします。
難消化性デキストリンが腸内環境を改善することで太りにくい体づくりを助けてくれるのですね。
ミネラルの吸収を高める

ダイエットにミネラルは欠かせません。
なぜなら、ミネラルは間接的に代謝を調節する働きがあるからです。
代謝は、”代謝酵素”とよばれる酵素によって行われますが、この酵素を活発にさせるのがまさに”ミネラル”。
ミネラルは”補酵素”と呼ばれ、代謝を行う”酵素”を助ける役割を担っているのです。
ミネラルが不足していると酵素の働きが弱まってしまうため、せっかくのダイエットの効果が表れにくくなってしまうことも。
難消化性デキストリンはミネラルの吸収を高め、ダイエットをより効率的にしてくれるのですね。
ダイエットに効果的な摂取方法

難消化性デキストリンの効果は、食事と一緒に摂取することで最も効果を発揮します。
なぜなら糖の吸収を抑制する効果は、難消化性デキストリンが食物中の糖と吸着した状態で取り込むことで発揮されるからです。
特に食後に摂取した場合では、難消化性デキストリンの作用が血糖値の上昇に間に合いません。
せっかくの効果を最大限に活かすためにも、普段の食事や飲み物に混ぜて摂取することをおすすめします。
「食事が不味くなったりしないの?」
「とろみがついてしまったりしないの?」
と不安に思うかもしれませんが、そんなことはありません。
難消化性デキストリン自体には味はほとんどありませんし、食事の物性が変化する心配もありませんので、ご安心ください。
ごはんを炊く前のお水に溶かしたりお味噌汁やお茶に溶かしたり、あらゆる食事で活用できそうです。
難消化性デキストリンの安全性と摂取量、副作用は?

普段の食事に取り入れるとなると、やはり気になるのは摂取量ですよね。
「どのくらい摂取したら良いの?」
「摂取しすぎると体に悪いの?副作用は?」
と疑問が浮かんでくると思いますので、以下で解説していきます。
食物繊維の一つだから安全
難消化性デキストリンは水溶性食物繊維で、みなさんご存じの食物繊維と特に変わりありませんので安全です。
どれほど安全かというと、消費者庁(厚生労働省)や米国FDA(食品医薬品局)が摂取量の上限を明確に定めないほどです。
また特定保健用食品(トクホ)の関与成分として認められており、なんとトクホ全体の三割以上の商品に、この難消化性デキストリンが使用されているから驚きです。
それほど、体への良い効果が期待でき、安心安全で提供できるものだということですね。
子どもから年配の方、妊婦さんまで、どなたでも安心して摂取できます。
食物繊維の目標摂取量は女性18g以上、男性20g以上
厚生労働省が定める食事摂取基準(2015年版)では、食物繊維の目標摂取量は18~69歳で1日あたり”男性20g以上”、”女性18g以上”とされています。
日本人の食物繊維の平均摂取量は約14gという報告がありますので、明らかに不足しがちですよね。
食の欧米化により今後ますます食物繊維の摂取量は減少していくでしょうから、積極的に摂取していきたいところです。
副作用は特になし
難消化性デキストリンには副作用は特にありません。
上記で説明したように、難消化性デキストリンはとても安全な食品といえます。
しかし、過剰摂取をすると下痢や腹痛といった症状を起こす可能性があります。
安全な食品とはいえ、過剰に摂取したからといって病気を治したりすぐに健康になるというものでもありません。
適度な範囲で活用するよう、ご注意ください。
難消化性デキストリンに関するQ&A
- 難消化性デキストリンとはなんですか?
- 難消化性デキストリンは水溶性食物繊維の一つです。
ほとんどがトウモロコシのデンプンを原料として作られます。
「トウモロコシから作られた食物繊維」ということですね。
- 難消化性デキストリンには健康効果があるのですか?
- はい、健康に効果があることがわかっています。
特に「1.整腸作用」「2.糖の吸収スピードを遅らせる」「3.脂肪の吸収スピードを遅らせる」「4.内臓脂肪の低減作用」「5.血清脂質の低下作用」「6.ミネラルの吸収促進作用」の6つの作用があります。(具体的には本文で解説しています。)
- 難消化性デキストリンはダイエットに効果があるのですか?
- はい、ダイエット効果が期待できます。特に難消化性デキストリンの「腸内環境を整える」効果で太りにくい体づくりに役立ちます。
また、糖の吸収を抑制したりミネラルの吸収を高めて代謝を促す効果も期待できます。
- 難消化性デキストリンの安全性や副作用について教えてください
- 難消化性デキストリンは消費者庁(厚生労働省)や米国FDA(食品医薬品局)が摂取量の上限値を明確に定めないほどに安全です。
また特定保健用食品の関与成分として認められています。
特に副作用などもありません。
しかし、過剰摂取をすると下痢や腹痛といった症状を起こす可能性があるため、適度な範囲で摂取するよう注意してください。
- 妊婦が摂取しても大丈夫でしょうか?
- 難消化性デキストリンは食物繊維ですので、妊婦さんが摂取しても特に問題はありません。
しかし過剰摂取をした場合の安全性に関しては、十分な情報がありませんのでご注意ください。
- 難消化性デキストリンは食品添加物ですか?
- 難消化性デキストリンは「食品素材(食物繊維)」となります。
ほとんどがトウモロコシのデンプンを原料として作られています。
- デキストリンと難消化性デキストリンの違いを教えてください
- デキストリンはデンプンを消化しやすく加工したものです。
主にとろみ剤として介護職や離乳食などに用いられます。
糖質を含み消化が行われます。
それに対し難消化性デキストリンはデンプンから作られますが食物繊維です。
消化はされません。
デキストリンと難消化性デキストリンの一番の違いは「糖質が含まれるかどうか」という点です。







 もくじ
もくじ

















