お酢ができるまで|美味しいお酢の選び方ポイント4つご紹介

味つけの基本となる調味料のひとつ、酢。
「さしすせそ(砂糖、塩、酢、醤油、味噌)」なんていう語呂合わせをご存じの方も多いと思いますが、砂糖や醤油、味噌よりも昔から使われてきた、由緒ある調味料なのです。
「酸っぱくて苦手」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は質のよいお酢には旨味や栄養もたっぷり。
今回は、その生産方法と選び方をご紹介いたします!
Contents List/目次
お酢の種類と効果
お酢には様々な種類があり、それぞれ味わいや効果も異なります。
日本で一般的なのは、穀物酢である「米酢」。
アミノ酸を多く含み、主に料理に使用されています。
米酢の種類

「米酢」「米黒酢」「玄米酢」…同じ米が原料ですが、一体違いは何なのでしょうか?
JAS規格では、米酢と米黒酢は概ね次のように定められています。
| 原材料の穀類 | 米の使用量 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 米酢 | 米 | 酢1Lにつき40g以上 | 米黒酢を除く |
| 米黒酢 |
・玄米/分づき米 ・小麦/大麦を入れてもOK |
酢1Lにつき180g以上 |
・発酵・熟成により褐色/黒褐色に着色したもの ・窒素分が0.12%以上 ・着色度が0.30以上 |
大きく異なるのは、米の精米歩合と、使用する米の量です。
多くは白米で作られる「米酢」は米の甘み、旨味がありながら、すっきりした味わい。
「米黒酢」はたっぷりと使用された玄米由来の複雑な旨味と甘み、豊かな香りが感じられる濃厚な味わいです。
一方、「玄米酢」という酢はJASの規格にはありません。
商品名が「玄米酢」となっていても、ラベルの「名称」の欄を見ると、「米酢」か「米黒酢」のどちらかが記載されています。
一般的に「玄米酢」と呼ばれる酢には原材料に玄米が使われ、一般的な米酢よりも旨みの強い、米酢と米黒酢の中間のような味わいのものが多いようです。
おすすめの米酢
「穀物酢」って?
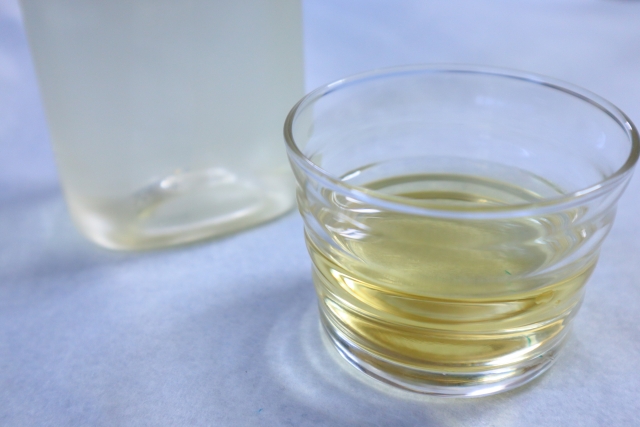
「穀物酢」というのは穀物を主原料として作られるお酢の総称です。
米酢も穀物酢の一種ですが、米酢が米を主原料として作られているのに対し、通常「穀物酢」として売られているお酢の原料は、小麦やコーン、酒粕に米などがブレンドされて作られています。
そうした「穀物酢」の特徴は、まずとてもリーズナブルなこと。
そしてさっぱりとしたシンプルな味です。
一方で、米酢や米黒酢のようなまろやかで深みのある味わいには欠けるため、「米酢」と書いてあるレシピで「穀物酢」を使用すると、思ったような仕上がりにはならないということも。
同じ「お酢」といっても効能等も異なるので注意が必要です。
米酢と穀物酢の違いは?|かわしま屋コンテンツ
米酢と穀物酢の違い知っていますか?
意外と知られていない酢の種類について比較・検証いたしました。
米酢と穀物酢の違いは?の記事を見る
酢の効果

様々な効果・効能があるとされるお酢。
広島修道大学の多山賢二教授が2002年に発表した論文『生活習慣病に及ぼす食酢の効果』によると、お酢には次のような効果があるそうです。
・糖尿病の予防
・血圧の降下作用
・血中コレステロール値の低下
・カルシウムの吸収促進
血圧を降下させ、血中コレステロールも低下させるということは、動脈硬化やそれに伴う脳梗塞、心不全などの生活習慣病の予防にもつながるということ。
生活習慣を変えるのには時間がかかりますから、摂るだけで重大な病気を予防してくれるお酢は心強い味方になりそうですね。
「お酢なんてそんなに摂れないよ」という方は、ぜひ伝統的なお酢の生産工程を知って、美味しい本物のお酢を選んでみてください!
酢の健康効果とは?飲み過ぎのデメリットと注意点をご紹介
酢に含まれた健康効果・効能をご紹介いたします。
飲み過ぎのデメリットや酢酸成分について、飲み方の注意点も含めて徹底解説!酢を使ったレシピもご紹介します。
酢の健康効果とは?飲み過ぎのデメリットと注意点をご紹介の記事を見る
お酢はこうして生まれる~酢の生産工程~

お酢の作られ方は様々ですが、ここでは伝統的な米酢の生産工程をご紹介します。
精米~米を蒸す
まずは原料の玄米を精米します。
タンパク質が多いと旨味が増す一方で独特の香りも生まれるため、各社とも精米歩合を工夫し、味や香りの差を生み出しています。
精米後は洗って水に浸し、蒸し釜で長時間蒸します。
麹づくり

米は、蒸しあがったら冷まし、麹菌をまぶしてゆきます。
ここはとても重要な工程。
温度、湿度が保たれた麹室で、糖化力とタンパク分解力の強い麹を作ります。
菌が均一に繁殖できるように、また内部が熱くなりすぎないように、固まった米粒をほぐしながら約2日かけて麹を育てます。
酒母(しゅぼ)の仕込み
次は酒母づくりです。
「酒母?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。
お酢づくりは、半分は酒づくりなんです。
できあがった麹は冷まし、水と一緒にタンクに入れ、そこに酵母を加えます。
さらに蒸した米を入れてかき混ぜ、2週間~1ヶ月ほど寝かせます。
ここではアルコールを作ることではなく、酵母を増殖させることが目的。
細やかな温度管理により、元気な酵母を育てます。
醪(もろみ)づくり

元気のいい酒母ができたら、いよいよアルコール発酵。
できあがった酒母を大きなタンクに入れ、水、麹、蒸し米を投入していきます。
この時、一気に入れると酵母濃度が薄まり、雑菌の繁殖につながるので、材料は3回に分けて投入します。 日本酒の製造でよく耳にする「三段仕込み」です。
発酵は、約30日かけてゆっくりと。
杜氏は、見た目や味から発酵の具合を確かめて温度管理や櫂入れし、つきっきりでお世話します。
醪の中では何が起こっているの?
醪の中では麹が米のデンプンを糖化し、酵母がその糖分をアルコールにするという2種類の現象が起きています。
世界の酢の多くは果物などに含まれる糖分をそのままアルコール発酵させて作られており、米酢のような複雑なプロセスを経て作られるのはとても珍しいそうです。
仕込み~発酵

こうしてできあがった芳醇なお酒は、「酢もともろみ」と呼ばれます。
ようやくここからが酢の仕込みです。
タンクには、「酢もともろみ」と水のほか、安定して発酵させるためのスターターとして「種酢」と呼ばれるお酢を入れます。
「種酢」には代々受け継がれてきた菌が含まれており、それが各メーカーの味の違いにも関わっているようです。
発酵の適温は約40℃。
酢酸菌は空気を好み、空気に触れる液の表面だけで働きます。
そのため、発酵はとてもゆっくりです。
時間は1ヶ月というところから、4ヶ月以上かけてじっくりと発酵させる製造所もあります。
熟成
発酵が終わると、酢を熟成蔵に移し、さらにゆっくりと時間をかけて熟成します。
中には1年近く寝かせるメーカーも。
この間にお酢の香りがまろやかに、そして味わい深く変化していくのです。
ろ過~出荷
熟成が完了したお酢はろ過され、火入れして瓶詰めされます。
火入れするのは、発酵を止めるため。品質が変質するのを防ぎます。
しっかりと検品したら、ようやく全国へ出荷です。
お酒以上に工程が多くて複雑なお酢づくり。
製品によっては1年以上の長い期間をかけて、ようやく完成するのです。
考えられている以上に、手間暇をかけて作られているのですね。
日本と世界のお酢のお話
複雑な工程を経て作られるお酢ですが、初めからそうだった訳ではありません。
ここでは、お酢の歴史と世界のお酢文化についてご紹介します。
お酢の歴史

お酢は、元々自然界に存在する酵母と酢酸菌が果物などを発酵させ、自然につくられたものが始まりであろうといわれています。
文献に残っている最古のお酢は、紀元前5000年ごろのもの。
メソポタミアで、干しブドウやデーツを使って作られていたそうです。
その後、紀元前4世紀頃にはギリシアの医師によって治療に使われたりもしていたようですよ。
当時から健康によいとされていたんですね。
酢造りの文化が日本に渡ってきたのは4~5世紀頃。
酒の醸造技術とともに米酢の造り方も伝わりました。
江戸時代には、酒粕を長期間寝かせて作った「粕酢」が発明され、大ブレイク。
現在「赤酢」と呼ばれているのはこの粕酢で、現代でも江戸前寿司ではこの赤酢をシャリに使っているお寿司屋さんが多いそうです。
世界のお酢文化

世界のお酢を見てみると、ワインの産地にはブドウから作られるワインビネガーやバルサミコ酢、ビールの産地には麦から作られるモルトビネガーなど、地域によって様々な種類のお酢があります。
シェリーの産地にはシェリービネガー、シードルの産地にはシードルビネガー…酒文化あるところに酢の文化あり、とも考えられそうです。
お酢の元になるのはお酒ですから、当たり前といえば当たり前かもしれませんね。
ヨーロッパでは、スパイスやハーブ、果物などを漬け込んでお酢を楽しむことも多いそうです。
できあがったフレーバービネガーは、ドレッシングにしたり、お肉やお魚の調理に使ったり、ピクルスを漬けたり。
米酢を使うなら、ハーブやフルーツは何が合うのでしょうか?
色々と試してみると楽しみが広がりそうですね。
おすすめのバルサミコ酢
お酢は正しく選んでもっとおいしく、もっと健康に
ポイント1 原材料をチェック!

何といっても大切なのは、原材料です。
JAS規格では、米酢には米以外に、その他の穀類やアルコール、糖類やアミノ酸液、そのほか様々な添加物を添加してよいことになっています。
よく見られるのが、アルコールを添加して酢酸発酵させているもの。
これは米由来の味わいや栄養成分が少ないので、原材料に「アルコール」と書いてあるものは要注意です。
旨味を出すために加えられる調味料についてはどうでしょうか。
本当においしい米酢には、たっぷりと使用された米と長期の熟成によってしっかりとした旨味がつくられるもの。味つけのための材料が加えられている場合は、熟成の過程で生まれたアミノ酸が不足していることも考えられます。
すし酢やお酢ドリンクなど、特定の目的のために作られたお酢を除けば、原材料はシンプルに「米」と書いてある「純米酢」が、おいしい米酢である証です。
ポイント2 お米にこだわるメーカーのものを

お酢の原料米には、古米やクズ米、米ヌカなどを使うメーカーも多いといわれています。
どのような米を使用しているのかも要チェックです。
おいしいお米で作ってこそ、おいしいお酢ができあがるもの。
日本酒に置き換えて考えれば、すぐに想像がつきますよね。
メーカーによっては、『富士酢』を醸造している飯尾醸造のように「おいしい酢は、おいしい米からできる」と信念をもって、自社で無農薬米作りの研究に励んでいるようなところもあります。
ぜひ、お米にこだわるメーカーのものを選んでください。
米はたっぷり使用するほど旨味と栄養成分もたっぷりになりますので、米の使用量もおいしく健康的なお酢の目安になりますよ。
ポイント3 発酵法に注目!

発酵法にも注目です。
現代のお酢の多くは、「通気発酵法(速醸法/連続発酵法)」で作られています。
これはお酢のもととなる酒に機械で空気を送り込み、液の表面だけでなく内部でも強制的に酢酸発酵を行わせるもの。
短時間で発酵が完了するため安価なお酢ができますが、少し酸味が立った味になります。
伝統的な発酵方法は「静置発酵法」。
液の表面のみでゆっくりと発酵が行われるため、発酵に長い時間がかかります。
しかし、その時間がまろやかで深みある味わいを生み出すのです。
味わいが豊かなのも、健康成分であるアミノ酸が豊富に含まれているのも、「静置発酵法」で作られたお酢。
かわしま屋で取り扱っているお酢はほとんどがこの「静置発酵法」で作られています。
ポイント4 おいしい水で作られたお酢は、おいしい。
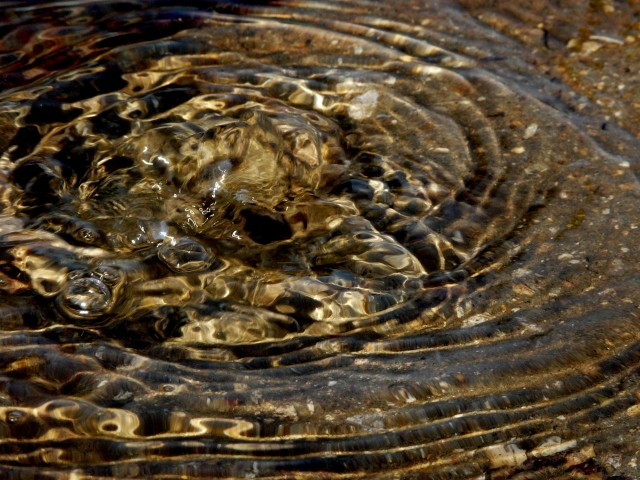
「原材料をチェック、お米にもこだわりを…」と書いてきましたが、お酢の原料の大部分を占めているのは、実は水です。
水はお酢の味を大きく左右するため、各メーカーとも、湧き水や地下水など水にこだわりをもってお酢づくりをしています。
たとえば大山食品『ヤマダイ 純米酢』で使用しているのは、宮崎県綾町の「綾の名水」。
豊かな照葉樹林に囲まれ、有機農業が盛んな町としても知られる綾町。
その湧き水はまろやかな味わいで、環境省選定の「日本名水百選」にも選ばれています。
日本酒のように、水に着目して選んでみるのも面白いですよ。
お酢の生産方法Q&A
- 酢の価格帯はいろいろありますが、何が違うのですか?
- 一般的に、酢の価格が高くなる・低くなるのには次のような理由が考えられます。
<価格が高くなる理由>
・良質な米を使っている
・使っている米の量が多い
・「静置発酵法」でじっくりと時間をかけて発酵
・熟成期間が長い
➡健康成分であるアミノ酸・旨味が豊富で、まろやかな味わいのお酢が多いと考えられます
<価格が安くなる理由>
・古米やクズ米など、低品質な米を使っている
・アルコールを添加して作っている
・「通気発酵法」で短時間で発酵
・熟成期間が短い
➡さっぱりとしていて、酸味が際立ったお酢が多いと考えられます
もちろん、各社の努力によって価格を抑えている部分もありますので、高いから・安いからというだけで一概に上記の内容が当てはまるとはいえません。
ラベルの表示やWebサイトなどで、原材料や製法を確認してみてください。
- お酢にアルコールが入っているものがあるのはなぜ?
- 生産工程の項目で見てきたように、米酢は米をアルコール発酵させ、酒にしてから酢酸発酵をさせています。
しかし米は高価なため、原料の一部をサトウキビやトウモロコシなどから作られる醸造アルコールで代用することがあるのです。
このアルコールは酢酸発酵して酢となるため、製品には残りませんが、米酢独特の旨味や成分には欠けたお酢となります。
また、醸造アルコールは輸入されたものが大半で、遺伝子組み換えの心配も残るため、安全面からもあまりおすすめはできません。
- レシピに「米酢」や「黒酢」、「ワインビネガー」とあったらその通りのものをつかわなければダメ?
- お酢にはそれぞれに独特の香りや風味、旨味があります。レシピ通りの仕上がりにしたいのであれば、お酢は指定されたものを使う方がよいでしょう。
どうしても代用したい場合は、果実酢なら果実酢、穀物酢なら穀物酢と原料の近いものを使用するか、黒酢とバルサミコ酢など熟成期間の比較的近いもの同士で代用されることをおすすめします。
お酢ってこんなに魅力的!酢ムリエ®内堀光康さんインタビュー
「酢」の魅力や疑問について、お酢のソムリエこと”酢ムリエ®”として日々酢を探求しつづけている内堀光康さんにお話しを伺いました。
酢ムリエ®内堀光康さんインタビューの記事を見る






























