醤油の種類は5つ!製法や地方による違い、使い分けの方法を徹底解説
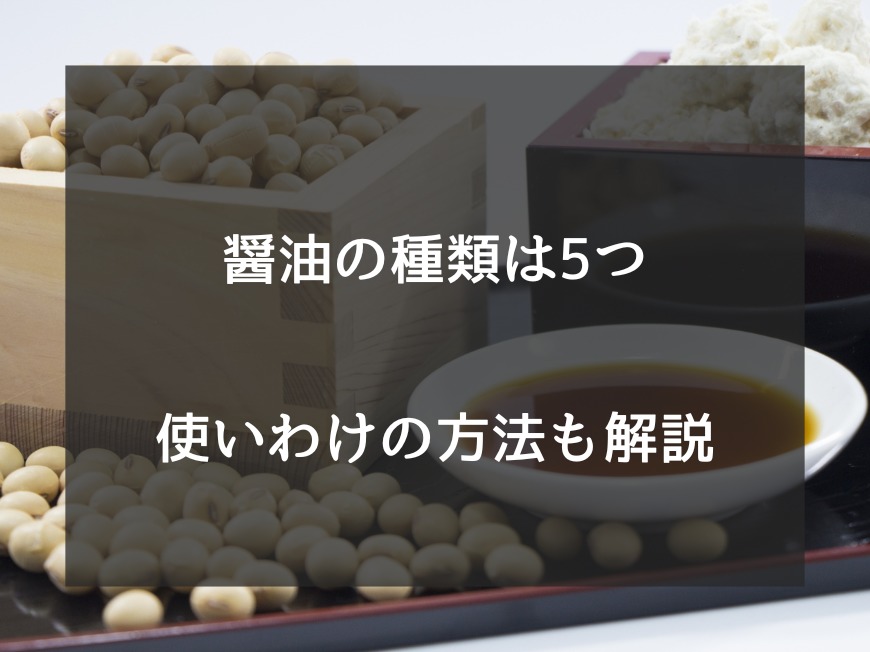
醤油は種類が多く、それぞれ特徴が異なります。そのため料理によって使い分けるのがおすすめです。適した醤油を選べば、いつもの料理の味わいがぐっと引き上がります。しかし、選び方がわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では醤油の種類や、使い分けの方法を分かりやすく解説します。作りたい料理に応じた、最適な醤油が見つかりますよ。毎日の料理がもっとおいしく、楽しくなるでしょう。
\ 国産原料100%の有機本醸造醤油 /
醤油の種類は5つ!違いは旨味と塩味のバランス

日本料理に欠かせない調味料である醤油は、種類によって旨味と塩味のバランスが異なります。JAS(Japanese Agricultural Standards、日本農林規格)による醤油の分類は5つです。以下5つの醤油の種類とそれぞれの特徴を紹介します。
- 塩味と旨味が調和する濃口醤油
- 少量で塩味が効く淡口醬油
- トロミのある再仕込み醤油
- 濃厚な旨味が特徴のたまり醤油
- 素材の味や色を活かす白醤油
参考:農林水産省 農林物資規格調査会 日本農林規格の改正について「しょうゆ」
塩味と旨味が調和する濃口醤油
濃口醤油は最も一般的な醤油で、シェア全体の約80%を占めます。塩分濃度は約16%で、塩味と旨味のバランスが非常によく、幅広い料理に使用できます
熟成期間が長いため、深いコクとまろやかな甘みが特徴です。煮物や炒め物、刺身、寿司、スープなどさまざまな料理にマッチします。
少量で塩味が効く淡口醬油
淡口醤油は色が淡く、旨味よりも塩味の強い醤油です。濃口醤油よりも色が薄く味の主張が控え目なので、素材の特徴を活かしたい料理に向いています。
名前や見た目に反して塩分濃度は高く、約18〜19%程度です。うどんや茶碗蒸しなど、透明感のある料理によく使われます。
トロミのある再仕込み醤油
再仕込み醤油は、一度作った醤油を再度仕込み直して作られる醤油です。濃厚な味わいとトロミがあります。濃口醤油よりも旨味が強く、まろやかな風味が特徴です。
2度発酵を行う必要があるため、他の醤油に比べると手間と時間がかかります。生産効率よりも味わいを重視し、旨味がギュッと凝縮されている醤油です。
脂の乗った刺身をつけたり、焼き魚にサッとかけたりすると、食材の旨味と醤油の風味がマッチします。
濃厚な旨味が特徴のたまり醤油
たまり醤油は濃厚さが特徴の醤油です。他の醤油よりも小麦の割合が非常に少なく、仕込みに使う水の量も少ないので、大豆の旨味成分が凝縮されています。
再仕込み醤油と同様にトロミもあり、料理に絡みやすいのもポイントです。加熱するときれいな照りが出ます。他の醤油と比べて色が濃く旨味も強いので、脂が多く癖の強い肉料理に最適です。
素材の味や色を活かす白醤油
白醤油は小麦を主な材料とする醤油です。色が非常に淡く琥珀色をしているので、素材の色を保ちながら風味を加えるのに適しています。国内生産量は非常に少なく、醤油全体の1%未満です。
主な材料である小麦は大豆よりも発酵にかかる時間が短いので、他の醤油よりも短い期間で完成します。淡口醤油と同様に旨味よりも塩味が強いのが特徴です。白だしの原料としても使われます。

醤油の種類は製法により3つに分類

醤油は製法によっても種類が変わります。
- 本醸造方式
- 混合醸造方式
- 混合方式
それぞれ見ていきましょう。
本醸造方式
本醸造方式は最も伝統的な醤油の製造方法です。大豆と小麦を主な原料とし、長時間かけて自然発酵させます。深い旨味と豊かな風味を引き出せるのが特徴です。
本醸造方式の醤油は甘味や酸味、塩味、苦味、旨味の5つの基本的な味覚が調和しています。自然発酵と長期間の熟成により、旨味のもとになるアミノ酸がたくさん発生するからです。
長期間の熟成と発酵は、醤油独特の色合いや香りも引き出します。質の高い醤油が探しているのであれば、本醸造のものを選ぶと良いでしょう。
混合醸造方式
混合醸造方式は発酵時間を短縮しつつも、豊かな風味の醤油を作る製造方法です。本醸造方式にアミノ酸液を加えることで、発酵時間を短縮しながらも風味を保っています。
混合醸造方式では発酵や熟成の過程を管理しやすいので、安定した品質の醤油を一貫して生産可能です。アミノ酸液により風味を維持することができ、製品間の品質のばらつきを減らします。
本醸造方式では数ヶ月から数年かかるところを、数週間から数ヶ月程度で製造できるのが特徴です。家庭用として比較的安価に大量生産されており、日常の料理に適しています。
混合方式
混合方式は短期間で醤油の大量生産を行う製法です。絞った醤油にアミノ酸や糖を加えて製作期間やコストを削減しています。
混合醸造方式との違いは、醸造の過程が一切ないことです。醤油本来の風味よりも、添加物による甘味や旨味が強く感じられます。
九州や東北で見られる甘い醤油は、本醸造ではなく混合方式により作られているのが一般的です。そのため混合方式の醤油は地域に根差した味となっています。
コストの観点だけでなく、地域に求められる味にするために混合方式が採用されていると考えて良いでしょう。
醤油は旨味や色で3つの等級に分類

JASは醤油を旨味や色で3つの等級に分類しています。具体的な内容は以下の表の通りです。
| 規格名 | 等級 | 醸造方式 | 色度 | 全窒素分 (容重) | 無塩可溶性固形分 (容重) |
|---|---|---|---|---|---|
| こいくちしょうゆ | 特級 | 本醸造のみ | 18番未満 | 1.50%以上 | 16%以上 |
| こいくちしょうゆ | 上級 | - | 18番未満 | 1.35%以上 | 14%以上 |
| こいくちしょうゆ | 標準 | - | 18番未満 | 1.20%以上 | - |
| うすくちしょうゆ | 特級 | 本醸造のみ | 22番以上 | 1.15%以上 | 14%以上 |
| うすくちしょうゆ | 上級 | - | 18番以上 | 1.05%以上 | 12%以上 |
| うすくちしょうゆ | 標準 | - | 18番以上 | 0.95%以上 | - |
| たまりしょうゆ | 特級 | 本醸造のみ | 18番未満 | 1.60%以上 | 16%以上 |
| たまりしょうゆ | 上級 | - | 18番未満 | 1.40%以上 | 13%以上 |
| たまりしょうゆ | 標準 | - | 18番未満 | 1.20%以上 | - |
| さいしこみしょうゆ | 特級 | 本醸造 又は混合醸造 | 18番未満 | 1.65%以上(本醸造) 2.00%以上(混合醸造) | 21%以上 |
| さいしこみしょうゆ | 上級 | - | 18番未満 | 1.50%以上 | 18%以上 |
| さいしこみしょうゆ | 標準 | - | 18番未満 | 1.40%以上 | - |
| しろしょうゆ | 特級 | 本醸造のみ | 46番以上 | 0.40%以上 0.80%未満 | 16%以上※2 |
| しろしょうゆ | 上級 | - | 46番以上 | 0.40%以上 0.90%未満 | 13%以上 |
| しろしょうゆ | 標準 | - | 10%以上 | - | 10%以上 |
※2 添加した砂糖は含まないこと。
参照:農林水産省 農林物資規格調査会 日本農林規格の改正について「しょうゆ」
表の全窒素分は主に旨味成分です。等級が上がるほど全窒素分が増えるので、旨味が強くなる傾向にあります。
また無塩可溶性固形分は醤油内の塩分以外の成分です。無塩可溶性固形分が多ければ、栄養価や旨味が多いと考えられます。
等級が上がるほど醤油内の成分が凝縮されているので、高品質な醤油だといえるでしょう。

古式天然醸造杉桶仕込み 国産有機醤油(こいくちしょうゆ) 900ml 無添加・国産原料100%の醤油-かわしま屋-
安心の有機・国産の原材料を伝統の製法を守って木桶で丁寧に醸造した、まろやかで香り高いこだわりの天然醸造醤油です。
1278 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>醤油は地域により種類が異なる

地方へ旅行に行った際、現地の料理がイメージと異なり驚いた方も多いでしょう。醤油は地域により種類が異なります。
そのため地域により醤油を使った料理の雰囲気も異なってくるのです。ここでは地域による醤油の種類の違いを解説します。
- 関東地方は濃い醤油
- 関西地方は淡い醤油
- 九州地方は甘い醤油
順番に見ていきましょう。
関東地方は濃い醤油
関東地方で主に使われているのは、濃口醤油をはじめとした色の濃い醤油です。そのため関東では醤油を使った汁物は色が濃い傾向にあります。
関東で濃口醬油が好まれる要因のひとつは、濃厚な味わいのかつお節がだしとして使われるためです。醤油の旨味が少なくあっさりしていると、だしに負けてしまいます。
力強いかつおだしとのバランスをとるために、旨味の強い濃口の醤油が好まれてきた背景があるのです。
関西地方は淡い醤油
関西地方では濃口醤油ではなく、色の薄い醤油が人気です。そのため素材の色や風味を活かした料理が多い傾向にあります。
淡口醤油が関西で好まれる理由のひとつは、関西では昆布だしが主流であることです。昆布だしは関東で好まれるかつお節よりも淡白であっさりとしています。
そのため濃口醤油を合わせると、昆布だしの風味が薄れてしまうのです。
九州地方は甘い醤油
九州地方では甘口醤油による、甘味のある味付けが好まれます。九州ではサツマイモやサトウキビといった甘味のある作物が豊富であり、甘味を活かした料理が発展してきたからです。
甘口醤油を使った九州の料理は、福岡の筑前煮や鹿児島の鶏飯などがあります。郷土料理に限らず、九州の家庭料理には甘い醤油が使われるのが一般的です。
九州の料理は甘味が加わることで、子どもから大人まで喜ぶ味付けのものが多くなっています。
醤油の種類による使い分けの方法

どの種類の醤油でも好みに応じて使い分けて大丈夫です。醤油は地域に根差した調味料なので、使い分けをしない傾向があります。
ただし醤油は種類ごとに特徴があるので、使い分けるとより料理の幅を広げられます。具体的な醤油の種類による使い分けの方法は以下の通りです。
- 濃口醤油はどんな使い方にも向いている
- 色の濃い醤油はそのままかけるのに向いている
- 色の薄い醤油は料理に加えるのに向いている
それぞれ解説します。
濃口醤油はどんな使い方にも向いている
濃口醤油はどんな料理にも使いやすい醤油です。バランスの良い塩味と旨味が、どの料理にもマッチします。
濃口醤油は万能な醤油ではありますが、素材や汁の繊細な風味や色合いを大切にしたい場合は、淡口の醤油を使うのがおすすめです。
また濃厚な料理に合わせる場合は、より色の濃い醬油でなければ物足りなく感じるかもしれません。
どんな料理にも合うので、醤油選びに迷ったら濃口醤油を選ぶと良いでしょう。
色の濃い醤油はそのままかけるのに向いている
再仕込み醬油やたまり醬油などの色の濃い醤油は、料理にそのままかけるのが向いています。調理中の味付けに使うと、風味や色に醤油の特徴が出すぎてしまうからです。
ただし伊勢うどんや照り焼きといった、濃厚な色や味が特徴の料理には問題なく使用できます。味の濃い煮物にも合いますが、あっさりとした煮物には向きません。
色の濃い醤油は刺身や寿司などのつけ醤油とするのを基本として、料理に使う際は相性を考えて使うのがおすすめです。
色の薄い醤油は料理に加えるのに向いている
淡口醤油や白醤油は素材を活かした料理に加えるのが良いでしょう。醤油の色や風味が控えめなので、素材の風味を引き立ててくれます。
ふろふき大根やお煮しめなど、食材の色を活かして華やかに仕上げたいときに最適です。脂の多い煮物に入れたり、つけ醤油として使ったりする場合は、物足りなさを感じるかもしれません。
色の薄い醤油は、だしの風味を活かした料理や、見た目を美しく保ちたい料理に使うと効果的です。
有名な醤油メーカー5選!商品の種類も解説
日本の醤油業界は、5つのメーカーでシェアの半分以上を占めています。ここでは5つのメーカーをシェアのランキング順にご紹介します。
- シェア1位:キッコーマン
- シェア2位:ヤマサ醤油
- シェア3位:正田醤油
- シェア4位:ヒゲタ醤油
- シェア5位:ヒガシマル醤油
順番に見ていきましょう。
シェア1位:キッコーマン
キッコーマンは国内シェアでトップを誇る醤油メーカーです。千葉県野田市に本社を置き、世界中に展開しています。
世界100か国以上で醤油を販売しており、「Kikkoman」というブランドは日本の醤油の代名詞として広く定着しています。キッコーマンの主な商品は以下の通りです。
- 特選丸大豆しょうゆ: 厳選された大豆を使用し、豊かな風味が特徴。
- うすくちしょうゆ: 素材の色を活かす料理に最適。
- しぼりたて生しょうゆ: フレッシュな風味を楽しめる密封ボトル入り
キッコーマンは、伝統的な濃口醤油からうすくち醤油、しぼりたて生しょうゆ、減塩しょうゆ、だし醤油など、さまざまな醤油製品を提供しています。
キッコーマンの特徴は使いやすさと鮮度保持を考慮したパッケージングです。1970年代に登場した赤いキャップの卓上びんや、後に開発されたやわらか密封ボトルなどがあります。
シェア2位:ヤマサ醤油
ヤマサ醤油は1645年に創業し、370年以上の歴史を持つ老舗醤油メーカーです。千葉県銚子市に本社を置き、日本の醤油業界をリードする存在となっています。ヤマサ醬油が取り扱っている具体的な商品の一例は以下の通りです。
- 超特選丸大豆しょうゆ: 丸大豆を使用した高品質な濃口醤油
- さしみしょうゆ: とろみがあり、刺身や冷奴に最適
- 超特選減塩しょうゆ: 通常の醤油から塩分を半分カットし、健康志向の消費者向け
ヤマサ醤油の特徴は独自の麹菌「ヤマサ菌」を使用していることです。ヤマサ菌の働きにより、ヤマサ醤油は赤みがかった色と芳醇な香りを持つ特徴的な醤油となっています。
ヤマサ醤油は伝統を守りつつも、技術的な革新を続けています。例えば、「鮮度の一滴」という製品は、二重構造の鮮度ボトルを採用し、酸化を防いで新鮮な状態を長く保てるものです。
シェア3位:正田醤油
正田醤油は1873年(明治6年)に創業し、群馬県館林市に本社を置く老舗醤油メーカーです。長い歴史を持ちながら、伝統的な製法を守りつつ、現代的な技術を取り入れています。
正田醤油の具体的な製品ラインナップの一例は以下があります。
- 特選しょうゆ: 高品質な大豆を使用し、伝統的な製法でじっくりと醸造した濃口醤油
- かつおだし入りしょうゆ: かつお節の出汁が効いた醤油で、煮物や汁物に最適
- 減塩しょうゆ: 健康志向の消費者向けに塩分を控えめにした商品
正田醤油のキャッチコピーは「おいしいがうれしい」です。品質の高い醤油作りに取り組んでいます。地域社会への貢献も積極的に行っており、地元のイベントや文化活動を支援しています。
シェア4位:ヒゲタ醤油
ヒゲタ醤油は、1616年に創業した日本でも有数の老舗醤油メーカーです。千葉県銚子市に本社を置き、400年以上の歴史を持っています。
江戸時代から続く伝統的な製法を守りつつ、現代の技術を取り入れて高品質な醤油を提供しています。ヒゲタ醤油の代表的な商品は以下の通りです。
- 本膳しょうゆ: 厳選された原料を使用し、伝統的な製法で作られた超特選ランクの醤油
- 昆布しょうゆ: 昆布の風味を加えた醤油で、まろやかな口当たりが特徴
- 減塩しょうゆ本膳: 本醸造しょうゆの風味を生かしつつ、塩分を50%カットした健康志向の醤油
ヒゲタ醤油は特に蕎麦つゆに定評があります。蕎麦屋で広く使用されており、プロの料理人からも高く評価されています。業務用商品として「かえし」や「めんつゆ」なども提供しており、飲食業界での信頼が厚いのが特徴です。
シェア5位:ヒガシマル醤油
ヒガシマル醤油は、兵庫県たつの市に本社を置き、長い歴史を持つ醤油メーカーです。1580年頃に創業された「幾久屋」を前身とし、1942年に「龍野醤油株式会社」として設立されました。
その後、1964年に「ヒガシマル醤油株式会社」に社名を変更しています。ヒガシマル醤油の主な商品ラインナップは以下の通りです。
- うすくち醤油: ヒガシマル醬油の代表的な商品で、素材の色や風味を活かす醤油
- 特選丸大豆うすくちしょうゆ: 高品質な丸大豆を使用し、風味豊かでまろやかな味わいが特徴
- ちょっとシリーズ: 簡単に調理できる粉末調味料
ヒガシマル醤油がある兵庫県たつの市は、うすくち醤油の発祥地です。揖保川の伏流水を使用し、発酵・熟成を緩やかに進めることで、繊細な味わいに仕上げています。
流通量1%!かわしま屋の希少な木桶仕込みの伝統醤油
かわしま屋では、醤油業界でも1%しか流通していない希少な木桶仕込みの醤油を販売しています。大手メーカーにはまねできない、昔ながらの製法にこだわった伝統の醤油をご賞味ください。
\ 国産原料100%の有機本醸造醤油 /
かわしま屋のこだわり濃口醤油で作る絶品レシピ
かわしま屋では国産原料100%にこだわった、伝統的な本醸造の濃口醤油を販売しています。こちらの醤油を使った絶品料理をご紹介するので、ぜひ試してみてください。筆者も作ってみましたが、いつもとは一味違う料理に仕上がりましたよ。

玉ねぎのバター醤油ステーキ
作り方
- 玉ねぎを立て半分に切ります。
- 醤油、みりん、酒、水を合わせておきます。
- フライパンにバターを入れて熱し、玉ねぎを炒めます。
- 玉ねぎ焼き色がついたら返します。
- 両面がこんがりと焼けたら、合わせておいた調味料をを加えて蓋をして蒸し焼きにします。
- 玉ねぎが柔らかくなったら蓋を取り、調味料を絡ませます。
コツ・ポイント

新じゃがのバター醤油
作り方
- 新じゃがは皮のままよく洗い、小ぶりなものはそのままで、大きなものは半分に切ります。
- 鍋にじゃがいもと水を入れて火にかけ、竹串がすっとささるぐらいまで茹でます。
- 醤油、砂糖、みりんを合わせておきます。
- じゃがいもが茹で上がったらざるに上げてお湯を切ります。
- 鍋にバターと合わせておいた調味料とじゃがいもを入れて火にかけ、じゃがいもにタレを絡ませます。
- お好みでパセリをふりかけてください。
コツ・ポイント

古式天然醸造杉桶仕込み 国産有機醤油(こいくちしょうゆ) 900ml 無添加・国産原料100%の醤油-かわしま屋-
安心の有機・国産の原材料を伝統の製法を守って木桶で丁寧に醸造した、まろやかで香り高いこだわりの天然醸造醤油です。
1278 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>























