宿便はどんな便?見た目でわかる特徴や健康リスクも徹底解説!
「最近、宿便ってよく聞くけど、どんな便のこと?」「便秘が続いているけど、これって宿便のせい?」そんな疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。腸内に便が溜まると体に悪影響があり、病気になる可能性もあります。
この記事では医学用語としての宿便の定義や、見た目でわかる宿便の特徴について、わかりやすく解説します。宿便を解消するとどうなるのかも併せてご紹介。諸説ある宿便の疑問を正しく解消してみてください。
医学用語としての宿便
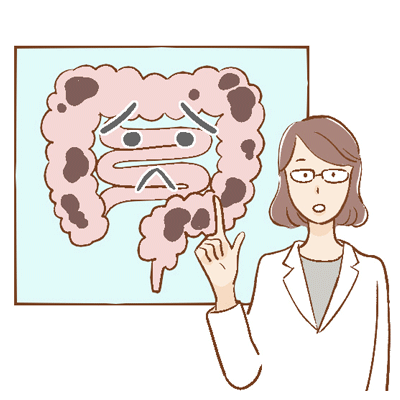
宿便とは、腸管内に長期間たまっていて排出されない便のことを指す言葉です。宿便の定義は複数の考え方があります。
- 腸管内に長くたまっている便(便秘の一種)
- 腸管内にヘドロのようにこびりつき、なかなか排泄されない便
世間で宿便は「腸管内にヘドロのようにこびりつき、なかなか排泄されない便」とされていました。消化管機能の停滞による、身体全体の不調や症状と関連付けられるようです。
しかし現代医学では「ヘドロのような便」について疑問視されています。ですが一部の病気には宿便という言葉が使われる場合があります。具体的な病気の一例は以下の通りです。
- 宿便性潰瘍
- 宿便性イレウス
- 宿便性穿孔
宿便はただのうわさではなく、医学的にも取り扱われている言葉だといえます。
宿便なんて嘘?
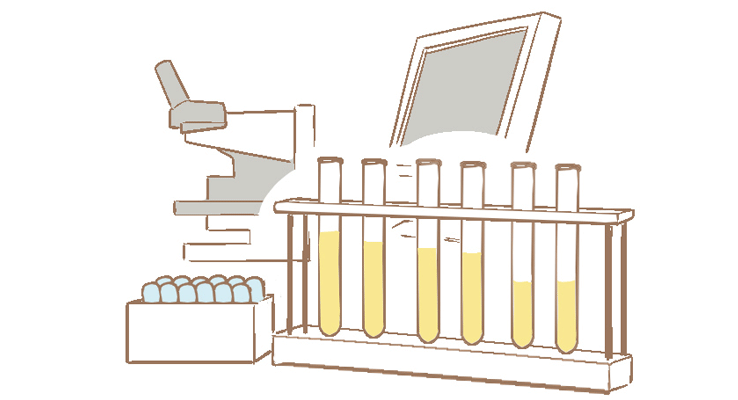
現代医学では宿便の定義は曖昧です。しかし宿便に関する言説のすべてが嘘ではありません。腸内に長い間便が残っている状態は、確かに存在するからです。
「古い便がヘドロのように腸壁にこびりつくということはありえない」「そういう状態の腸を見たことはない」といった医師の意見が多くあります。
宿便について懐疑的な話を聞くたびに「もしかして、”宿便”って健康食品や何かを売るために作り出された嘘なのでは?」と疑念が湧いてくるものです。
「宿便」は、「作り出された嘘」なのでしょうか?千葉中央メディカルセンターが発表している論文からヒントを探ってみましょう。
「宿便という用語は単に便秘によって消化管内に内容物が停留していることを意味するのではなく、通常の排便では排泄できない消化管内の貯留物を想定したものである」
引用:東洋医学雑誌 第65巻, 第4号 宿便についての一考察
としたうえで、バリウム検査後に頻回に下痢があったにもかかわらず、バリウムが腸壁に残存していたという例を示して「『排水管の内面にヘドロがこびり付いていた状態』という言辞が、単なる空想ではないことを強く示唆する所見である」
宿便という言葉は『腸内に長くたまっていた便』(広辞苑)と理解されているが 「その一つの形として腸内容物の腸管への比較的強固な附着があることを本報告では明らかにしたと考えている」
「便が毎日出ているという患者でもレントゲンを撮ると便が残っている」といったことは実際にあります。「便秘」という自覚がなくても腸内に便が残ってしまっているという人が存在するのは確かなようです。
どのような形態があるかについては今後明らかになるのを待つことにして、この記事では便通があるのに腸内に留まっている便をすべて「宿便(滞留便)」と呼ぶことにしたいと思います。
宿便は便秘の合併症のひとつ
宿便は便秘が長期間続くことで、腸内に滞留する便だと考えられます。宿便に対処せずに放置すると腸内環境が悪化し、さらなる体調不良を招くので注意が必要です。
例えば医学事典MSDマニュアルによれば、便秘が長期化すると便が腸内に溜まり、腹部膨満感や腹痛を引き起こすとされています。
また日本内科学会によれば、便秘により腸内圧が上がって腸管の血流が低下すると、腸壁に炎症や潰瘍が生じるケースもあるようです。
宿便は、便秘の延長線上にある合併症であり、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
参考
宿便と滞留便の違い
宿便と滞留便は、どちらも腸に便がたまっている状態のことを指します。医学的には、この2つに大きな違いはありません。どちらも便秘による症状の一種と考えられています。
宿便は「腸に長い間たまった便」として説明されることが多いですが、医学的にははっきりした定義がありません。一方、滞留便は「腸にたまった便」を指し、医学的には便秘の一つとされています。
どちらの場合も、原因や解決方法は同じです。宿便と滞留便は、腸に便がたまるという同じ現象を指していると考えてよいでしょう。
見た目でわかる宿便の特徴
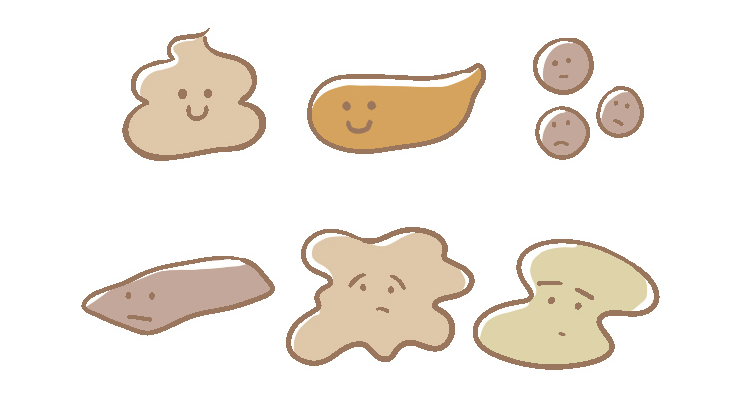
「これ、宿便なの? そうじゃないの?」 宿便を出そうとトライしている時に気になるのが、宿便の特徴です。 長く腸内にとどまっている宿便には、通常の便と比較して次のような特徴があると言われています。
- 強烈な悪臭がする
- 黒っぽい色をしている
- 水分の少ない硬い便
それぞれ見ていきましょう。
強烈な悪臭がする
宿便が強い臭いを出すのは、腸の中で腐ったり発酵したりするからです。この臭いは、腸の状態が悪いことを教えてくれるサインとなります。
便が腸の中に長くたまると、悪い菌が増えます。便の中の食べ物のカスを分解すると、アンモニアやスカトールといった臭いのもとになるガスが発生。腸内のガスが便の臭いを強くします。
また、腸の動きが悪くなると便が出にくくなり、さらに臭いが強くなることもあるので注意が必要です。
黒っぽい色をしている
宿便は、通常の便よりも黒っぽい色をしていることがあります。腸内に長い間便が滞留することによる、腸内環境の悪化が原因のひとつです。
また便が腸に長く留まると、腸が便の水分を吸収して色が濃くなります。併せて悪玉菌が増えると便を腐敗させ、さらに色が濃くなるようです。
腸内環境に問題がない場合でも、鉄分を多く含む食品やサプリメント、薬などを摂取すると便が黒くなります。腸管内に出血があっても便は黒くなるので、黒い便が続く際は医師に相談すると良いでしょう。
水分の少ない硬い便
宿便は、便が水分をほとんど含まず、硬くなっている状態です。便が腸の中に長く留まると、大腸が便から水分を吸い取ってしまいます。その結果、便はどんどん硬くなるのです。
また、運動不足や水分不足、食物繊維が足りない食事をしていると、腸の動きが悪くなります。そのため便が出にくくなり、硬い便の原因になります。
硬い便はコロコロとした形になり、出すのが大変です。宿便になるとなかなか便を出せずに、硬い便がさらに硬く、大きくなる悪循環に陥る傾向があります。
お通じにお悩みがある方におすすめ

オーガニック腸活乳酸菌パウダー 100g 1袋 乳酸菌 粉末 発酵食品由来の植物性乳酸菌30兆個入り!有機JAS認定 -かわしま屋- 【送料無料】 *メール便での発送*
日本古来の発酵食品のみを原材料とした、植物性乳酸菌のパウダーです。飲みやすい微粉末。毎日続けて腸から健康に!
3685 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>
腸活乳酸菌サプリ カプセルタイプ 1袋(60粒)|1袋に日本の発酵食品由来の植物性乳酸菌が30兆個! -かわしま屋- 【送料無料】*メール便での発送*
日本古来の発酵食品を原材料とした、植物性乳酸菌のカプセルです。毎日続けて腸から健康に!
3685 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>宿便・滞留便による健康リスク5選

宿便や滞留便が腸内に溜まると、体全体にさまざまな悪影響を及ぼします。ここでは専門家が発信している情報を元に、具体的な健康リスクを5つ挙げます。
- 心血管疾患リスクの増加
- 慢性腎臓病(CKD)のリスク増大
- サルコペニアやフレイルのリスク増加
- 腸管閉塞や消化管穿孔リスクの増加
- QOL(生活の質)の低下
それぞれ見ていきましょう。
宿便・滞留便による健康リスクの参考文献
日本内科学会雑誌第109巻第2号 慢性便秘症診療 ガイドライン2017
日本老年医学会雑誌 第57巻第4号 高齢者の慢性便秘症の病態と治療
日本内科学会雑誌 第112巻第9号 下部消化管機能性疾患診療の最近の進歩 ~慢性便秘症を中心に~
心血管疾患リスクの増加
宿便が心血管疾患のリスクを高める可能性があります。排便時のいきみや腸内環境の悪化が、心臓や血管に負担をかけるからです。
排便時に便が硬く、いきむことがあると血圧が急激に上がります。このような負荷は、特に高齢者や心疾患のリスクがある人にとって危険です。
また、腸内環境が悪化すると、炎症物質が血液中に入ることで動脈硬化が進む可能性があります。この状態が続くと、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるとされています。
例えば、日本内科学会による発表では、便秘のある人が心血管疾患を発症するリスクが通常の排便習慣を持つ人よりも高いそうです。
また高齢者がトイレで突然の心筋梗塞を起こす事例も報告されています。
慢性腎臓病(CKD)のリスク増大
宿便は慢性腎臓病(CKD)のリスクを高めることがあります。腸内環境の悪化が腎臓に負担をかけるためです。
便秘が長期間続くと、腸内に毒素が溜まりやすくなります。これらの毒素は血液中に吸収され、腎臓が排出する役割を担います。
腎臓が常に毒素処理をし続けると、負担が増加し、腎臓の働きが悪くなることがあるようです。また、便秘の際のいきみや腸の炎症も腎臓に悪影響を及ぼすとされています。
虎の門病院が行った研究では、便秘のある人はそうでない人に比べてCKDを発症するリスクが高いと報告されました。
この調査は350万人を対象に行われた大規模なものです。便秘が腎臓病の重要なリスク要因である可能性は高いといえるでしょう。
サルコペニアやフレイルのリスク増加
便秘が続くと、サルコペニア(筋肉が減る状態)やフレイル(体全体が弱くなる状態)のリスクが高まる可能性があるようです。
便秘によって腸内環境が悪化すると、栄養の吸収が悪くなります。また、便秘の不快感やストレスで食欲が減り、必要な栄養を摂れなくなることもあります。その結果、筋肉量が減り、体力が低下するのです。
日本内科学会の調査によると、便秘が慢性化している高齢者は、そうでない人に比べてサルコペニアやフレイルの症状が進みやすいそうです。
例えば、便秘による腹部の不快感が続くことで活動量が減り、それが筋肉の減少や代謝の低下につながるという事例も報告されています。また、便秘が原因で食事の量が減り、たんぱく質やビタミンが不足し、筋力が落ちるケースも多いです。
腸管閉塞や消化管穿孔リスクの増加
便秘が続くと腸管閉塞や消化管穿孔といった深刻な症状を引き起こす可能性があるようです。
便が腸内に溜まり続けると腸の動きが鈍くなり、腸管内の圧力が高まります。この圧力が腸壁を傷つけることで、腸管が詰まり閉塞を起こすことがあるとされています。
さらに、長期間放置された場合、腸壁が破れて穿孔を引き起こし、腹膜炎や重篤な感染症を伴うリスクが高まるようです。
日本内科学会の報告では、高齢者において便秘が腸管閉塞や穿孔を伴うリスクを増大させることが示されています。便秘患者の中には、腸の中に硬い便が長期間滞留し、腸閉塞や消化管の損傷に至った例もあります。
また、消化管穿孔が進行すると腹膜炎を起こし、手術が必要になるケースも少なくありません。日本老年医学会によると、ある高齢者施設のデータでは、慢性便秘症の患者の5%が重篤な合併症を経験しているという結果が報告されています。
QOL(生活の質)の低下
宿便が続くと生活が不便になり、心も体もつらくなることがあります。便秘になると、お腹が張ったり痛くなったりして、毎日が快適に過ごせなくなるからです。
さらに、便が出ないストレスや不安で気分が落ち込むこともあります。外出先でのトイレの心配が増えて、行動が制限される場合もあるでしょう。
WOCM会誌第27巻の報告では、便秘患者の身体的健康スコア(PCS)の数値と健康な人との比較データを参照。長期間の便秘による生活の質の低下に言及しています。
宿便には病気のリスクだけでなく、活き活きとした生活を送れなくなるリスクもあるようです。
宿便や滞留便の解消でびっくりするほど便が出る
宿便や滞留便を解消すると、一度にたくさんの便が出ることがあります。これは腸に溜まっていた便がまとめて排出されるからです。
腸に便が長く溜まっていると、腸の動きが悪くなります。その結果、さらに便が溜まりやすくなり、腸が働きにくくなる悪循環があります。
ですが宿便や滞留便を出せれば腸がリセットされ、また元気に動き始めるようです。そうすると、驚くほど便がスムーズに出ることがあります。
宿便を解消する効果は、びっくりするほど便が出るだけではありません。便秘が良くなり「体が軽くなった」と感じたという話もあります。
宿便を出す方法はたくさんあります。ぜひ滞留便の解消でびっくりするほどの便通を経験してみてください。
宿便の解消によるダイエット効果はある?
宿便とダイエットの関連性は、腸内環境と体重管理が密接にリンクしていることから注目されています。宿便を解消するとびっくりするほど便が出るなら、ダイエットに効果がありそうなものです。
ですが宿便解消によるダイエット効果は一時的なものだとされています。たしかに宿便が解消されることによって、体重減少に繋がる場合があります。
これは、排便とともに水分も体から失うことになるためです。一時的な状況を「ダイエットになる」「痩せる」と考えるのは適切ではないかもしれません。
ですが腸内環境の改善は、健康的に痩せるためには必須です。腸内がクリーンになることで新陳代謝が活性化し、消化・吸収が改善される一歩となります。
健康的に痩せるための土台を整えると考えれば、宿便の解消にもダイエット効果があるといえるでしょう。
腸内環境を改善したい方におすすめ

オーガニック腸活乳酸菌パウダー 100g 1袋 乳酸菌 粉末 発酵食品由来の植物性乳酸菌30兆個入り!有機JAS認定 -かわしま屋- 【送料無料】 *メール便での発送*
日本古来の発酵食品のみを原材料とした、植物性乳酸菌のパウダーです。飲みやすい微粉末。毎日続けて腸から健康に!
3685 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>
腸活乳酸菌サプリ カプセルタイプ 1袋(60粒)|1袋に日本の発酵食品由来の植物性乳酸菌が30兆個! -かわしま屋- 【送料無料】*メール便での発送*
日本古来の発酵食品を原材料とした、植物性乳酸菌のカプセルです。毎日続けて腸から健康に!
3685 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>宿便に関するQ&A
腸内環境を整えるおすすめの商品

オーガニック腸活乳酸菌パウダー 100g 1袋 乳酸菌 粉末 発酵食品由来の植物性乳酸菌30兆個入り!有機JAS認定 -かわしま屋- 【送料無料】 *メール便での発送*
日本古来の発酵食品のみを原材料とした、植物性乳酸菌のパウダーです。飲みやすい微粉末。毎日続けて腸から健康に!
3685 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>






















