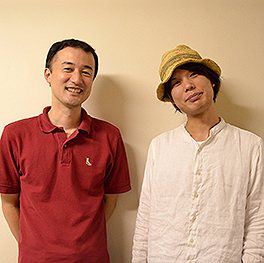「菱六」助野彰彦さんの麹づくり講座 【2.麹づくり実践編】

菱六の代表助野彰彦さんによるプロ向け麹づくりワークショップ。
今回は麹づくり実践の部分をまとめています。(3日間のワークショップの麹づくり実践の部分のみを抽出しています。)
麹づくりは通常三日間、おおよそ50時間程度かけて行われます。
【麹づくりの主なステップ】
.jpg)
【補足情報】
.jpg)
*なお、今回のワークショップではお米を洗い、水に漬ける箇所はワークショップ開始前日に行われたため、レポートでは紹介していません。
麹づくりの洗米と浸漬の様子はこちらの記事で紹介していますので気になる方はご参照ください。
1.お米の水切り
麹づくりの実践。まず初めのステップはお米の水切りです。
事前に助野さん前日に浸漬していただいたお米の水切りを行います。
.jpg) 前の晩に浸漬したお米
前の晩に浸漬したお米今回使われたお米は岡山県産の「アケボノ」という品種です。
精米歩合は92%程度。菱六にて精米されたものです。(一般的に食べられている白米は精米歩合が90%。それよりも精米歩合がやや高い。)
.jpg) 岡山県産アケボノ
岡山県産アケボノ粘りの少ないお米(ササニシキやあきたこまちなど)が麹づくりに向いています。
コシヒカリやヒノヒカリ(そのほかxxヒカリという名前の品種)、ミルキークィーンなどは粘りが強すぎて麹づくりには向きません。
前日のよるに洗い、浸漬(お米を水につける)した米をざるにあげ、
1時間程度置いておき、水をしっかりと切ります。
.jpg)
ここで水が残っていると、お米を蒸した際に蒸し具合にバラつきがでてきてしまい
良い麹に仕上がりません。1-2時間程時間を掛けてしっかりと水を切っておきましょう。
.jpg)
ざるからお米をあげる前に、ざるの角度を替えたり、お米をやさしく混ぜてあげると全体的にむらなく水が切れます。
.jpg)
.jpg)
1-2時間ほど置いておきます。
.jpg)
【洗米、浸漬、水切りの注意点】
お米は通常の炊飯の際の洗い方と同じで問題無し。
水に漬ける場合、お水を吸って膨らんだお米が水面より上にこないように、お水を多めにする。
冬場は42度程度のお湯につけてあげると浸水がすすみやすい。冬場など気温が寒く、浸水が進みづらい時期はお湯を使うのがおすすめ。
水切りをしっかり行わないと、お米の水分量が多すぎて、麹が上手く仕上がらない事があるので注意。
向いているお米は粘りのすくないお米。ササニシキやあきたこまち。
コシヒカリやヒノヒカリ、ミルキークィーンなどの粘りの強い米は向かない。
2.お米の蒸し
お米を蒸し布で包み、蒸し器に入れて高温でお米を蒸していきます。
.jpg) 蒸し布にはテトロンという化学繊維の物が使われています。
蒸し布にはテトロンという化学繊維の物が使われています。.jpg)
通気性に優れており、蒸し布にお米が付きづらい便利な素材です。
.jpg) 包んだ布はお米の上にも被せます。
包んだ布はお米の上にも被せます。蒸し器には中華せいろと和せいろの2種類が使われました。
.jpg) 中華せいろ。
中華せいろ。.jpg) 和せいろ。
和せいろ。.jpg) お米の表面から蒸気が貫通し、一部の表面が透明になってきたら蒸し器の蓋をします。
お米の表面から蒸気が貫通し、一部の表面が透明になってきたら蒸し器の蓋をします。.jpg) できるだけ強火にして強い蒸気で蒸し上げるのがポイントです。ここでの蒸し具合が麹の仕上がりを大きく左右します。
できるだけ強火にして強い蒸気で蒸し上げるのがポイントです。ここでの蒸し具合が麹の仕上がりを大きく左右します。蓋をしてから40分が蒸し時間の目安。途中(今回は20分)でせいろの段を入れ替えます。
.jpg) 途中でせいろの段を入れかえる。
途中でせいろの段を入れかえる。良いお米の蒸し具合は、お米をひとつまみ取ってみてひねり潰すと簡単に「ひねり餅」ができるぐらいです。
(ひねり餅:蒸したお米を手でひねってつくった餅の事です。)
.jpg) ひねり餅??が蒸し具合の目安。
ひねり餅??が蒸し具合の目安。目安の蒸し時間40分を経過してもまだ米が固い、またはお米の水分が足りないようでしたら
蒸し時間を延長してください。
ちなみに、米麹でつかう米は炊飯器などで炊いてしまうと、水分量(60%程度以上)が多くなりすぎて、良いに麹に仕上がりません。
適度な水分量(36-38%程度)に抑えた形でお米を仕上げる為には、お米を蒸気で「蒸す」という作業が必要になります。
【お米の蒸しの注意点】
蒸す道具のおすすめはせいろ。
蒸し布はテトロンがおすすめ。お米がくっつかないから。(ちなみに、かわしま屋の国産の蒸し布も、お米がくっつかないからおすすめです。)
蒸す際に蒸気とお米の距離が近いと、お米の水分量が多くなりすぎる(ビチャビチャになる)。せいろを使う場合は、空(何も入れない)蒸籠を一段目に置いて、お米は2段目より上に入れるのが良い。
できるだけ強火で蒸す。
お米の表面から蒸気が出てきて、お米の表面が透明になったら蓋をする。そこから40分間が蒸し時間の目安。
せいろが2段以上ある場合は途中で上下を入れ替える。
3.種切(種付)
種切(種付けとも呼びます。蒸したお米に種こうじをふりかける)を行います。
.jpg)
お米が蒸し上がったら、布を敷いたトレイや箱(今回はプラスチックの箱)にお米を移します。
.jpg)
蒸しに使った蒸し布は湿気を吸いすぎているので、種切以降のプロセスには使用しない方が良いです。
このワークショップでは内側(お米に接する部分)にはテトロンを、その周りには綿の布を敷いていました。
.jpg)
テトロンの周りの綿布が、お米から出る蒸気を適度に吸ってくれます。
綿の布だけだと、蒸し米の水分を吸いすぎてお米が乾燥してしまうので注意が必要です。
.jpg)
温度計でお米の温度を測り、(ここから先はお米の温度を品温と呼んでいきます)45℃程度に下がってきたら、種切を開始します。
.jpg)
今回使う種麹(麹菌、もやしとも呼びます)は「糖化用白A」という種類の物。(改良長白菌と近い性質の種麹です。)
.jpg)
.jpg)
品温が35℃程度になるまで、しっかりと混ぜていきます。
.jpg)
もれなく、くまなく、種麹が混ざるように種切をします。
.jpg) 結構な重労働です。
結構な重労働です。慣れないうちは、使用する種麹の量を既定よりも多くしましょう。
種麹の量が多い分には、仕上がりに問題はありません。不安なら規定量の2-10倍程度、種麹をばら撒いてしまいましょう。
このワークショップでは原料米16㎏に対して、40gの種麹を撒きました。(規定の3倍程度多く撒いています。)
.jpg)
少量(500-2㎏程度)の麹をつくる場合は、種切の際に品温が35℃以下にならないように注意が必要です。
品温が下がりすぎると、この後の工程で温度を高くしていくのが難しくなります。
少量をつくる際は、蒸し米をあまりひろげずに、スピーディーに種切を行いましょう。特に冬場は注意が必要です。
.jpg)
【種切りの注意点】
・蒸しに使った布は種切以降のプロセスには使わない。蒸した時に湿気を吸いすぎているから。
・種切以降のお米は、テトロン(内側)綿布(外側)の2枚を被せる。結露防止とお米の乾燥防止に良い。
・少量(500-2㎏程度)の麹をつくる場合は、種切の際に品温が35℃以下にならないように速攻で種切を行う。特に冬場は注意。
・腕に自信が無ければ、種麹を多めに使う。種麹の量が多い分には、仕上がりに問題はありません。不安なら規定量の2-10倍程度、種麹をばら撒け。
4.室に入れる(引き込み)
種切したお米を室(または保温庫)に入れることを引き込みと呼びます。
.jpg) しっかりと種切をしたお米を布(内側はテトロン、その外側に綿の布)で包みます。
しっかりと種切をしたお米を布(内側はテトロン、その外側に綿の布)で包みます。.jpg) 温度計を刺し、品温が確認できるようにしておきます。
温度計を刺し、品温が確認できるようにしておきます。.jpg)
.jpg) もやし町家の土壁とレンガで出来た室に入れます。
もやし町家の土壁とレンガで出来た室に入れます。.jpg) 室にいれたのは4/27 の15時。そこから10時間以上、保温します。
室にいれたのは4/27 の15時。そこから10時間以上、保温します。
一日目のワークショップはここまで。
もやし町家の麹室は、湿度が保ちづらいそうで、助野さんはこの後の麹づくりが上手くいくかどうか不安そうでした。
.jpg) 不安げに湿度計を見つめる助野さん。
不安げに湿度計を見つめる助野さん。
5.切返し
ワークショップ2日目。一つ目の工程は切返しです。
切返しとは、保温しているお米の塊をほぐして、温度を均一にすることです。お米の隅々まで酸素を行き渡らせる意味合いもあります。
このワークショップでは引き込みから約20時間後に切返しを行いました。
(前日の15時に引き込み。翌日14時に切返し。)
.jpg) 麹を室から出します。
麹を室から出します。
ワークショップでは、全員が作業しやすいように、麹を入れたプラスチックの箱を室から取り出して切返しを行いました。
この段階で、麹の特有の栗のような香りが強く漂います。香りの中に若干の酸味も感じます。
.jpg) 麹特有の栗のような香りが。
麹特有の栗のような香りが。
手を入れると、麹の温かさを感じます。所々に塊(麹の菌糸どうしが軽くくっついている)ができています。
.jpg) 塊になっている部分。
塊になっている部分。
.jpg) お米の表面にうっすらと白いものが覆っているのもわかります。
お米の表面にうっすらと白いものが覆っているのもわかります。麹の状貌(じょうぼう:姿、形のこと。ここでは白くなった表面や所々かたまりができている様子)と香り(栗のような香り)を目安に切り返しのタイミングを見極めます。
手をいれると、米の中央部分がより温かく、湿度も若干高いのが分かります。
中央部分と外側の温度や湿度(乾燥具合)が均一になるように切返しを行います。
.jpg)
この後のプロセスでは、麹菌の増殖速度が、麹の乾燥速度より上回るようにするのが肝です。
布を被せて、次のプロセス「盛り」まで、再度室に入れておきます。
.jpg)
.jpg) 再度、室に戻します。
再度、室に戻します。【切り返しの注意点】
米全体の温度と湿度(乾燥具合)が均一になるように行う。
家庭で少量(500-2kg程度)の麹をつくる場合は、切返しは速攻で終わらせる。(品温が下がりすぎるので。)省略しても良い。
蒸米の塊の中心と外側では「温度」と「湿度(乾燥具合)」に大きく差があります。温度と乾燥具合が均一になるように混ぜろ。
麹の状貌(すがた、かたち)と香りは常に意識する。
6.盛り
「盛り」とは麹を麹蓋に盛り分けていく作業の呼称です。
通常は切返しから数時間後に盛りを行います。今回は品温が低いので切返し直後に盛りを行いました。
プラスチック箱にまとめて入れてあった麹を、麹蓋に盛り分けていきます。
(ワークショップでは全員が作業しやすいように、室から箱をだして盛りを行いました。)
.jpg)
盛りのタイミングも、麹の香りと状貌で盛りのタイミングを判断します。
この時、品温は43.5度になっていました。
.jpg)
なお状貌が芳しくない(あまり白くなっていない)のに品温だけが上がっている場合は、
再度切り返しを行い品温を下げその後しばらく時間を置いて、麹でお米の表面の白さが増すまで待ちます。
.jpg) 使うのは杉製の麹蓋。
使うのは杉製の麹蓋。.jpg) マスを使っておおよそ1.2kg程度をプラスチック箱から麹蓋に移していきます。
マスを使っておおよそ1.2kg程度をプラスチック箱から麹蓋に移していきます。.jpg) 写真のように、山になるように麹を持っていきます。
写真のように、山になるように麹を持っていきます。(麹に厚みができるので品温が下がりづらく、乾燥速度も抑えられる為。)
温度が下がりすぎないように、山に厚みを持たせます。
.jpg) 写真のように、山になるように麹を持っていきます。
写真のように、山になるように麹を持っていきます。(麹に厚みができるので品温が下がりづらく、乾燥速度も抑えられる為。)
麹蓋いっぱいに麹をひろげるわけではないようです。
(麹蓋に盛った麹は1.2㎏程度。麹蓋いっぱいに麹を敷き詰めるとおおよそ2㎏程度入ります。)
.jpg)
麹蓋に麹を素早く盛り、室に入れました。
.jpg)
麹蓋を棒積み(麹蓋を単純に積み上げていく)が行われます。
.jpg) 麹蓋が棒積みされました。
麹蓋が棒積みされました。.jpg) ちなみに菱六では一日260枚の麹蓋に盛りを行っているそうです。
ちなみに菱六では一日260枚の麹蓋に盛りを行っているそうです。【麹盛りの注意点】
・麹の状貌と香りで盛るべきか否か判断できるようにする。
・品温が下がりすぎないように注意。
7.仲仕事(なかしごと)と仕舞仕事(しまいしごと)
三日目の作業一つ目は仲仕事と仕舞仕事。
「盛り」から数時間経過したタイミングで、品温が一定になるよう、麹に手を入れていきます。
この作業を仲仕事と呼びます。
.jpg) 室から出した麹蓋
室から出した麹蓋「仕舞仕事(しまいしごと)」は仲仕事の後5~7時間後、品温が40℃近くまで上昇した麹を再度混ぜて温度を均一にする作業の事です。
.jpg) 表面の白さが強まっています。
表面の白さが強まっています。.jpg) 麹特有の栗の香りも漂います。
麹特有の栗の香りも漂います。.jpg) 麹を室から出してみると、品温は36度後半。(このタイミングでは理想の品温は40度)
麹を室から出してみると、品温は36度後半。(このタイミングでは理想の品温は40度)品温がそこまであがらなかったので、仲仕事も仕舞仕事も省略されました。
(ここで麹に手を入れてしまうと品温が下がりすぎてしまうため。)
.jpg) 最後に助野さんが室の麹蓋を棒積みからレンガ積み(麹蓋に間をあけて重ねる方法)に切り替えます。
最後に助野さんが室の麹蓋を棒積みからレンガ積み(麹蓋に間をあけて重ねる方法)に切り替えます。.jpg) 麹蓋のレンガ積み。
麹蓋のレンガ積み。ワークショップの二日目はここまで。
【仲仕事・仕舞仕事の注意点】
・家庭で少量(500-2kg程度)の麹をつくる場合、品温の経過によっては(品温が急激にあがらない場合。40℃を超えない場合など)は仲仕事も仕舞仕事も省略して良い。
・棒積みとレンガ積みなど、麹蓋の積み上げ方で、品温の推移も調整できる。
8.出麹(でこうじ)
ワークショップの三日目の朝10時ごろ(引き込みから43時間経過後)出麹が行われました。
.jpg) 室から麹蓋を出します。
室から麹蓋を出します。.jpg) 出麹とは、十分に麹菌が繁殖した麹を室(または保温庫)からだす作業の事です。
出麹とは、十分に麹菌が繁殖した麹を室(または保温庫)からだす作業の事です。.jpg) 蓋を開けると栗の香りが漂います。
蓋を開けると栗の香りが漂います。種切りからおおよそ42-50時間経過後、破精(はぜ。麹菌の繁殖形態を表す言葉。お米から麹菌が繁殖して菌糸が白く見えている状態)が見えお米から栗のような香りが出ていれば、麹の出来上がりです。
.jpg) 破精回りは弱めですが、表面は白く覆われています
破精回りは弱めですが、表面は白く覆われています気温や湿度により菌の増殖具合が異なるため、出麹までの時間も変わります。状貌と香りで出麹のタイミングを見計らいます。
.jpg) 手で触れて、乾燥具合を確かめます。
手で触れて、乾燥具合を確かめます。米粒の表面に麹菌がよく繁殖し全体が白くなっており、米粒の内部にも麹菌が食い込んでいるのが理想的な麹の仕上がりです。
ワークショップでは、出麹の際の品温は43.5度。室の湿度が低かったので、菌の増殖速度よりも、麹の乾燥が速かったようです。
.jpg) 破精と香りは弱いですが、甘酒づくりには使えるであろう麹が仕上がっていました。
破精と香りは弱いですが、甘酒づくりには使えるであろう麹が仕上がっていました。麹の出来上がりです。仕上げに麹の粗熱を取ります。
.jpg) しゃもじで分割されます。
しゃもじで分割されます。.jpg) 扇風機に1時間ほど当てられます。
扇風機に1時間ほど当てられます。.jpg) 粗熱が完璧に取れたら、さらに分割して紙袋に入れて持ち帰ります。
粗熱が完璧に取れたら、さらに分割して紙袋に入れて持ち帰ります。.jpg) 出来上がった麹は、麹とその2倍の量の水をヨーグルティアに入れて60℃で12時間保温したら
出来上がった麹は、麹とその2倍の量の水をヨーグルティアに入れて60℃で12時間保温したら甘みの強い甘酒に仕上がりました。ヨーグルトに混ぜて食べるのがおすすめの食べ方です。
ここまでが麹づくり実践編です。
【出麹の注意点】
・出麹のタイミングも状貌と香りで判断する。
・粗熱はしっかり冷ます。油断していると、下がったはずの品温が再度上昇して麹の質が悪くなる(場合によってはダメになる)ことがある。
良い麹の条件
【良い麹の色】
麹の色は純白。米粒の表面に麹菌がよく繁殖し、米粒の内部にも麹菌が食い込んでいる。
【良い麹の触感】
手で握るとやわらかく弾力感がある。
【良い麹の重さ】
麹の重量がもともとのお米のおよそ20%増になっている(増加した分が菌の重さです。)
20%をこえると水分が多すぎです。また10%以下だと水分が少なくあまりいい麹ではなくなります。
【良い麹の味】
香り、触感(はぜこみ)、甘み、
麹を噛むと栗のような特有の香りがするのが良い麹の味です。
甘酒にして甘みをチェックするのもおすすめです。
麹1に対して水2の割合で60度で12時間保温して麹だけの甘酒をつくってみましょう。
美味しい甘酒に仕上がっていれば、家庭で行う麹づくりが成功したと言ってよいのではないでしょうか?
より専門的な方法だと、出麹後の麹の酵素力価を計測するという方法があります。(高額な専門器具が必要です。)
【甘みも旨味も強い麹に仕上げるには!】
甘みも旨味も強い麹に仕上げるには以下の2つがポイントです。
1.糖化力(アミラーゼ)と蛋白分解力(プロテアーゼ)が強い種麹を選ぶ。
→改良長白菌20gがおすすめ。
2.麹づくりの際の品温の経過を調整する。
「米麹の標準品温経過表」を参考にしてください。
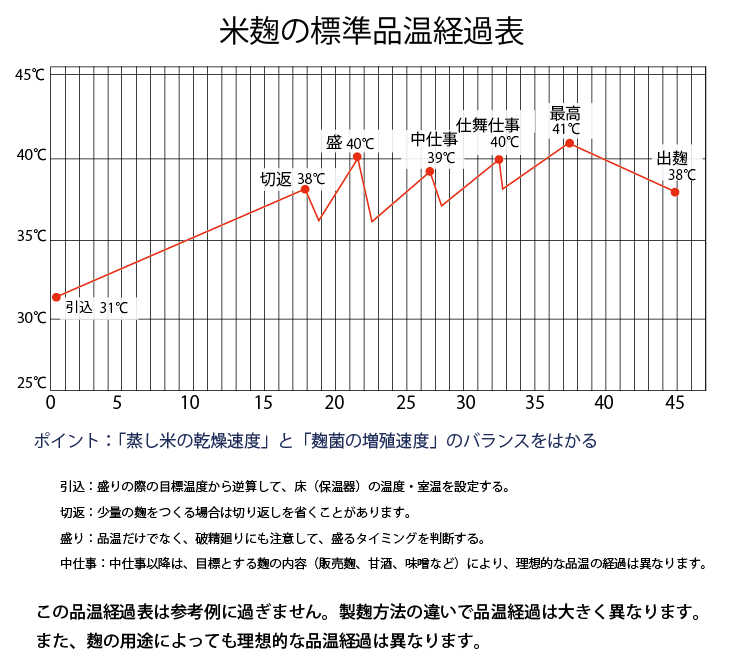
上の表はあくまで標準の品温経過表です。目安にしてください。
アミラーゼとプロテアーゼ両方を高くするには、切返後に品温を38-40℃付近に高めて、出麹までその近辺の温度を保つのが良い。
米麹の保存方法
出麹後は、麹を出来るだけ早く使用するのがおすすめです。
温度が低く、風通しの良いところに置いておいても、
麹の固まりが厚いと、発酵が止まらずに、麹の質が悪くなってしまう事があります。
出麹後に麹を1-2日置く場合は、麹のかたまりをもみほぐし、
できるだけ薄く広げておき涼しい場所に保管しておきましょう。
冷蔵庫で保存する場合は、吸湿性のある紙袋に入れておきます。おおよそ一週間を目安に使い切りましょう。
冷蔵庫する場合は、ジップロックなどに薄くして、空気をできるだけ出して保管しましょう。
おおよそ一か月程度を目安に使い切りましょう。
.jpg)
種麹(もやし)の選び方
種麹は用途に応じて以下の基準で選びましょう。
【糖化力】
アミラーゼの働きの強さ。甘みのつよい麹に仕上げたい場合は糖化力の強いものを選びましょう。
【蛋白分解力】
プロテアーゼの働きの強さ。旨味のつよい麹に仕上げたい場合は糖化力の強いものを選びましょう。
【褐変度】
仕上がりの色がつくかどうかの度合い。
白く仕上げたい、色がつかない方が良い場合は褐変度が「-(マイナス)」のものを選びましょう。
お味噌やお醤油、自分で飲む用の甘酒など、色が白くなくても良い場合は気にしなくても良いでしょう。
-:色が付きづらい
±:色が多少付く
+:色が付く
【菌糸の長さ】
仕上がりの菌糸の長さ。味にはほとんど影響はない。長毛のものは、菌糸が長くモコモコになりやすい。短毛のものは菌糸が短くなる。
見た目かほぐしやすさから選べば良いでしょう。
上記の基準から、かわしま屋では家庭で使う種麹には、お味噌にも甘酒にも使いやすい、甘みも旨味も強く仕上がる改良長白菌20gを推しています。

麹づくりにおすすめの道具とお手入れ方法
・蒸しにはせいろがおすすめ。
.jpg) 和せいろ
和せいろ.jpg) 中華せいろ
中華せいろ・麹蓋は杉のものが良い。檜(ヒノキ)製は良くない。檜にはヒノキチオールという殺菌作用をもつ成分が含まれているから。
.jpg) 杉の麹蓋
杉の麹蓋杉でも防腐加工されたものは使用しない方が良い。(ちなみに、かわしま屋の麹蓋は、国産の杉で出来ています。防腐加工もしていません。)
・蒸し布はお米がくっつかないタイプがおすすめ。菱六ではテトロンが使われていました。
.jpg) テトロンの蒸し布
テトロンの蒸し布・使用した道具は、熱湯で洗う。麹蓋には米麹のがへばりつくことが多いので、熱湯に入れてタワシでこする。
.jpg) その後、天日干しして乾かす。これでカビが防げる。
その後、天日干しして乾かす。これでカビが防げる。三日間のワークショップを終えて
麹づくりを、蒸しの段階から丸三日間助野さんの横で見られるのは有難かったです。
.jpg)
抱えていた疑問もすべて解消できました。
.jpg) 室のコンディション(特に湿度管理)があまり良くなかったみたいで、当初から助野さんは麹が上手く仕上がるか不安な様子でした。
室のコンディション(特に湿度管理)があまり良くなかったみたいで、当初から助野さんは麹が上手く仕上がるか不安な様子でした。その不安は的中し、破精と香りはやや物足りない出来に。
.jpg) 悔しがる助野さん。
悔しがる助野さん。その顔を見て、麹づくりとは試行錯誤の連続なんだと悟りました。。
.jpg) 四月の京都は良く晴れてて気持ちよかったです。
四月の京都は良く晴れてて気持ちよかったです。「麹づくりの講義編」に続きます。
麹づくりにおすすめの種麹と麹発酵器
・種麹の商品一覧はこちらからご覧いただけます。
・麹発酵器の商品一覧はこちらからご覧いただけます。
*写真の一部は荒木美恵子に撮影していただいたものです。荒木さん有難うございました。