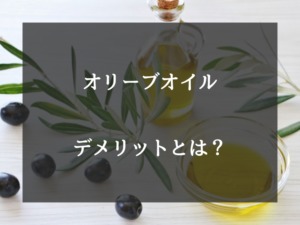足がつるのは梅干し不足?1日1個で予防できる理由を解説します!

「寝ているときや運動中に突然足がつることはありませんか?」
痛みで目が覚めたり、動けなくなったりすると、とても辛いものです。
足がつる原因は、筋肉の疲労・ミネラル不足・冷えなどさまざまです。実は、梅干しがその予防に役立つといわれていることをご存じでしょうか?
梅干しには、クエン酸・カリウム・ナトリウムなどが豊富に含まれています。これらの成分が筋肉の働きをサポートし、足がつるのを防ぐと考えられています。実際に、スポーツ選手の間でも梅干しを取り入れる人が増えているのです。
本記事では、足がつるのを予防する梅干しの効果や効果的な摂取方法、梅干しに頼らない改善策について詳しく紹介します。
「足がつるのを防ぎたい!」と思う方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
足がつる原因は主に5つ

ここでは、足がつる主な原因を5つ解説します。原因を理解すれば、具体的な対処法が見えてきます。
- 筋肉の過剰な収縮
- ミネラル不足による影響
- 水分不足による血流の悪化
- 身体の冷えによる筋肉の硬直
- 加齢による筋肉の柔軟性の低下
それでは、順番に見ていきましょう。
筋肉の過剰な収縮
筋肉の過剰な収縮は、足がつる主な原因の一つです。筋肉が硬直した状態から急に動くと、筋肉が極度に緊張して、足がつりやすくなります。
例えば、準備運動が不十分なままスポーツをすると、筋肉が柔軟に動けずに足がつることがあります。また、長時間座りっぱなしの状態から、急に動くのも足がつる要因です。
寝起きの身体が目覚めていないタイミングも急な動作には注意が必要です。
ミネラル不足による影響
足の筋肉が正常に動くためには、ミネラルが必要です。
カルシウムやマグネシウム、カリウムなどが不足すると、神経や筋肉の伝達が乱れ、足がつりやすくなります。
厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(令和元年)によると、日本人の多くがカルシウムを十分に摂取できていない可能性が指摘されています。ファストフードや加工食品の摂取が増え、栄養バランスが偏りがちだからです。
また、スポーツ選手や肉体労働者は、汗とともにナトリウムやカリウムを失いやすく、ミネラル不足が顕著になりやすいといわれています。不足状態が続かないよう、意識的な補給が大切です。
水分不足による血流の悪化
体内の水分不足も、足がつりやすくなる要因です。
体の約60%は水分で構成されています。そのため水分が不足すると血液の循環が悪くなり、筋肉に十分な酸素や栄養が届きません。その結果、足がつりやすくなります。
特に、エアコンの効いた室内で長時間過ごす人や、暑さを避けて外出を控える高齢者は注意が必要です。知らず知らずのうちに水分が不足する傾向があります。
水分不足が続くと、筋肉への血液供給が不十分になり、運動中や就寝中に足がつることがあります。特に夜間は血流が変化しやすいため、睡眠中に足がつる人が多いといわれています。
身体の冷えによる筋肉の硬直
体温が低下すると血流が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。
冬場だけでなく夏場のエアコンが効いた室内でも、知らないうちに体が冷えていることがあるので気をつけましょう。
冷えは女性に多いイメージがありますが、男性も注意が必要です。特にデスクワークが主な仕事だと、室内外の温度差によって自律神経が乱れ、体が冷えることがあります。
加齢による筋肉の柔軟性の低下
年齢を重ねると、筋繊維の量や質が変化し、若い頃と同じ動きをしていても足がつりやすくなります。特に、ふくらはぎなどの下半身の筋肉は衰えを感じやすい部分です。
さらに、加齢に伴い血管や関節も老化し、血液循環が悪化することがあります。筋肉に酸素や栄養が届きにくくなると、足がつりやすくなるのです。
参考:静脈学 (Jpn. J. Phlebol.) 2000年, Vol. 11, No. 3, pp. 247-252 下肢静脈瘤におけるこむら返りの発生因子
足がつるのを1日1個の梅干しが予防する理由

ここからは、梅干しが足のつりを予防する仕組みを説明します。梅干しの効果について次の3つの要素に絞って詳しく見ていきましょう。
- クエン酸が筋肉の疲労を軽減する
- カリウムが電解質バランスを調整する
- ナトリウムが筋肉の働きをサポートする
それぞれ解説します。
クエン酸が筋肉の疲労を軽減する
梅干しの酸っぱさの主成分であるクエン酸には、足がつりにくくなる効果があるといわれています。 クエン酸は、運動後や日常生活で溜まった筋肉の疲れを和らげるサポートをするからです。
消費者庁が公表している調査によると、クエン酸の継続摂取は疲労感の軽減に一定の効果があると報告されています。
足がつる原因の一つは、筋肉の過剰な疲労や緊張です。クエン酸がエネルギー代謝を促し、乳酸が溜まりにくい環境を作ることで、筋肉の急激な収縮を防ぎ、足のつりを予防する効果が期待できます。
少量でも継続した摂取が大切です。筋肉のコンディションが整い、足のつりの予防につながるでしょう。
カリウムが電解質バランスを調整する
足がつるのを予防するのであれば、梅干しに含まれるカリウムも見逃せません。
カリウムは細胞内の浸透圧を調整し、電解質のバランスを保つからです。その結果、神経や筋肉の働きを正常に維持するサポートをします。
梅干しはカリウムを豊富に含む食品として知られています。特に、しそ漬けの梅干しや塩分控えめのタイプはカリウムの含有量が多く、汗をかきやすい夏場や運動後のミネラル補給に適しています。
文部科学省が公表している食品成分表によると、梅干し100gあたりのカリウム含有量は約220mgです。梅干し1個(約10g)であれば、約22mgのカリウムが含まれることになります。
1日1個を習慣にすると、継続的にカリウムを補給できるでしょう。また、梅干しはそのまま食べられるため、手軽にカリウムを摂取できる点もメリットです。
カリウムの摂取不足が続くと筋肉の働きが乱れ、足がつりやすくなりまます。適度な塩分とともにカリウムを摂り、電解質のバランスを整えましょう。
ナトリウムが筋肉の働きをサポートする
梅干しの塩分も足がつるのを予防する効果があるとされています。ナトリウムは筋肉の収縮や弛緩に欠かせない成分だからです。
ナトリウムは神経伝達の面でカリウムとともに重要な役割を果たし、筋肉の働きをスムーズにします。
ただし、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、ナトリウムの過剰摂取が高血圧などのリスクを高める可能性があると警告されています。そのため、適量を意識することが重要です。
梅干し1個に含まれるナトリウム量は平均200~300mg程度とされています。毎日1個食べると、足がつりやすい人のナトリウム不足を補う可能性があります。
大切なのは、「摂りすぎない範囲で上手にナトリウムを補給する」ことです。梅干しは酸味のおかげで少量でも満足感を得やすいため、適量を意識しながら活用するとよいでしょう。
足がつるのを予防するための梅干しの摂取方法

ここでは、梅干しの選び方や食べるタイミングを具体的に提案します。
足のつりを予防するには、梅干しをただ食べるだけでなく、品質・摂取のタイミング・適量を意識することが大切です。
- 選ぶべき梅干しの種類
- 梅干しを食べるタイミング
- 梅干しの1日の最適な摂取量
それぞれ見ていきましょう。
選ぶべき梅干しの種類
足がつるのを予防するためには、塩分濃度が18%以上の昔ながらの梅干しがおすすめです。
梅干しの種類はさまざまです。添加物が多い梅干しや、塩分濃度が抑えられた梅干しだと、十分な効果を得られない可能性があります。
塩分濃度が18%以上の昔ながらの梅干しは、添加物を使わずに長期保存ができます。そのため安心して毎日の食事に取り入れられるのが特徴です。クエン酸の含有量も高く、疲労回復や足のつり予防にも効果が期待できます。
塩分を抑えた梅干しは、保存のために添加物が使用されていることがあります。そのため、購入時には原材料表示を確認しましょう。
梅干しを食べるタイミング
梅干しを摂取するタイミングによって、体への吸収や効果の実感度は変わります。足がつるのを予防するには、運動前後や夕食時など、適切なタイミングを選ぶことが大切です。
運動前に梅干しを食べると、クエン酸が筋肉のエネルギー代謝をサポートし、疲労を軽減する効果が期待できます。さらに、スポーツドリンクや水と一緒に摂れば、汗で失われるナトリウムやカリウムの補給にも役立つでしょう。
梅干しを運動後に食べるのも効果的です。運動によって溜まった乳酸の除去を助け、電解質バランスを素早く回復させる働きがあります。特に足がつりやすい人は、運動後の習慣として梅干しを取り入れるとよいでしょう。
夕食に梅干しを食べるのも一つの方法です。筋肉の収縮をサポートし、夜間に足がつりにくい身体作りをサポートします。
梅干しの1日の最適な摂取量
梅干しは健康に良い食品ですが、塩分を含むため摂り過ぎには注意が必要です。一般的には1日1個が適量とされ、多くても2個程度に留めるのが望ましいでしょう。
厚生労働省が提示する食塩相当量の目標値は1日あたり男性7.5g未満、女性6.5g未満です。梅干し1個で約1g前後の塩分を摂取する計算になります。そのため、ほかの食事で摂る塩分とのバランスを考え、1日の総摂取量が目標値を超えないよう管理することが大切です。
また、梅干しを毎日続けるには、無理なく習慣化できるかどうかも重要なポイントです。食べやすい梅干しレシピを見つけると良いでしょう。
重要なのは「適量を守ること」と「継続すること」です。毎日少しずつ続けると、安定した効果が期待できます。
参考:厚生労働省 日本における食塩摂取量の現状と減塩推進への課題~日本高血圧学会の取り組みを中心に~
梅干しに頼らず足がつるのを防ぐ方法
梅干しは足がつるのを予防するのに便利な食品です。しかし生活習慣全体を見直すことも大切です。足がつるのを防ぐには、梅干し以外にもできる対策はいくつかあります。
足がつる原因はさまざまで、特定の方法だけで完全に防ぐのは難しいとされています。複数の対策を組み合わせることで、より効果的に足のつりを予防できるでしょう。梅干しの摂取とあわせて実践することで、足がつるリスクをさらに抑えられるはずです。
それでは、梅干しに頼らずに足のつりを防ぐ方法について詳しく解説していきます。
食生活を改善する
足がつるのを防ぐには、バランスの良い食生活が欠かせません。特に、カルシウム・マグネシウム・カリウムなどのミネラルを意識的に摂取することが重要です。ミネラル不足は筋肉の働きを乱し、足がつる原因の一つになります。
小魚・海藻類・豆類・緑黄色野菜を取り入れると、身体に必要な栄養素を補給できます。特定の栄養素が不足していると感じる場合は、サプリメントを活用するのも一つの方法です。ただし、サプリメントに頼りすぎず、あくまでもバランスの良い食事を基本にすることを心がけましょう。
こまめな水分補給をする
水分不足は、足のつりを引き起こす大きな原因の一つです。特に、運動をする人や汗をかきやすい環境で働く人は、注意が必要です。意識的に水分を補給しないと、気づかないうちに脱水状態に陥ることがあります。
水分補給はのどが渇く前に行うのが理想です。一度に大量に飲むのではなく、少量をこまめに摂るほうが体に吸収されやすくなります。暑い季節はもちろん、冬場の乾燥した室内でも水分は失われていきます。そのため、一年を通して油断せず水分補給を心がけましょう。
梅干しで塩分やカリウムを補うのも有効です。ですが、体全体の水分とミネラルのバランスを整えることが、足のつりを防ぐ基本となるでしょう。
適度なストレッチをする
日常的にストレッチを取り入れることが、足のつりを防ぐ大きなポイントになります。筋肉の過度な緊張や疲労は、足がつる原因になりやすいからです。
ストレッチで筋肉をほぐすと、足がつりにくくなります。特に、ふくらはぎや足裏を重点的に伸ばすストレッチをすると、足がつる頻度を減らせる可能性が高くなります。
ただし、無理に痛みを感じるほど強く伸ばすのは逆効果です。適度に気持ちよい範囲で行い、毎日少しずつ継続しましょう。
就寝前にリラックスする
足がつりやすい時間帯として、特に夜中が挙げられます。
睡眠中に足がつると、痛みで目が覚めてしまい、翌日の疲労感にもつながることもあるでしょう。そこで、就寝前にリラックスする習慣を取り入れるのがおすすめです。
リラックスする方法としては、軽いストレッチや深呼吸、温かいお風呂にゆっくり入るなどが効果的です。これらの習慣は副交感神経を優位にし、筋肉の緊張を和らげる働きがあります。