【管理栄養士監修】ごま油の健康効果・効能・栄養|上手な選び方と使い方
記事の監修
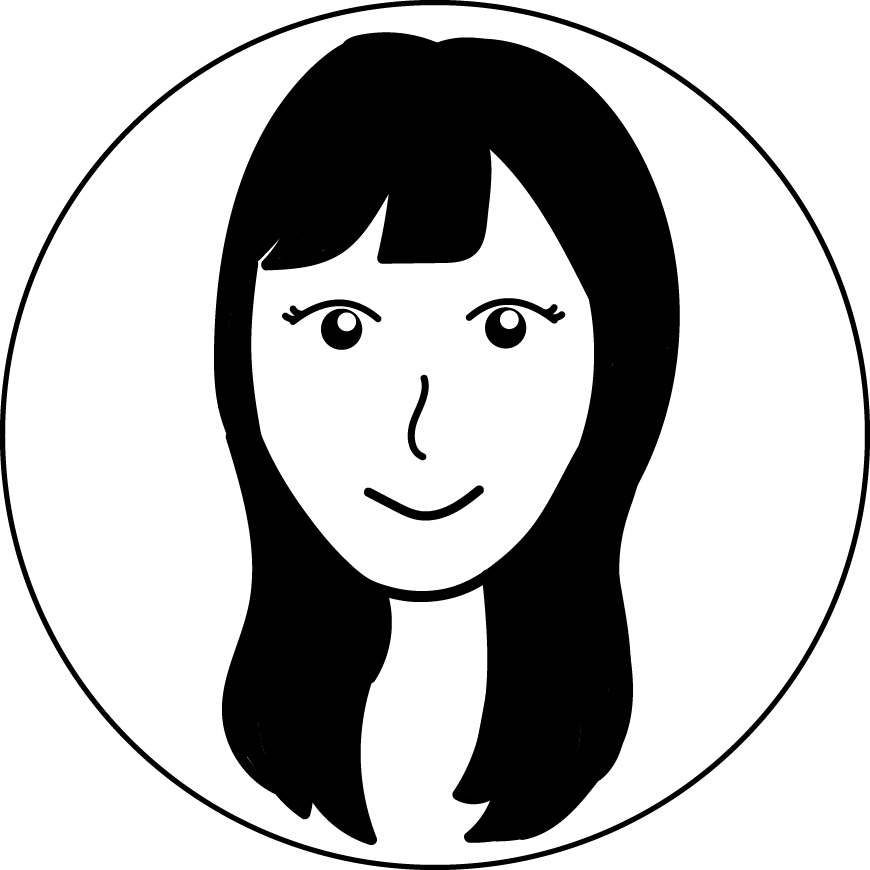
管理栄養士
鶴田ようこ
調理師・管理栄養士。2つの資格を生かし食用油脂製造会社にて品質管理に従事。
菜種油、オリーブ油の品質に関する分析、衛生管理等を行う。
幼い頃から野菜作りの手伝いをしていたことから、季節の野菜料理が得意。

ごま油は昔からサラダ油や、オリーブオイルと共に家庭でもよく使われてきました。中華や韓国料理には欠かすことができない油ですが、いつも作るお気に入りのレシピも、ごま油をひと回しかけるだけで、味や風味が変わって美味しくなる、とても万能な油です。
よく使う油だからこそ、「ごま油は体にいい?それとも悪いの?」など健康効果や、選び方、保存方法などが気になるところではないでしょうか?
それでは、ごま油にまつわる疑問を一つひとつ解決していきましょう!
ごま油は健康効果にいい?効果と効能
日本には奈良時代に中国から伝えられてというごま油ですが、インドでは5000年以上の歴史を持つアーユールベーダ(インドやスリランカの伝統医療)では、「若返りのオイル」とも言われ、オイルマッサージなどの施術でよく使われる油です。
リノール酸やオレイン酸といった不飽和脂肪酸が多く含まれ、コレステロール値を下げ血管を強くしてくれる効果があります。
またセサミンやセレンの抗酸化作用により、活性酸素からのダメージから細胞を守る効果も!
ごま油には様々な健康効果がありますが、ここでは6つの効果効能をご紹介いたします。
効果効能① コレステロール値を下げ、動脈硬化を予防
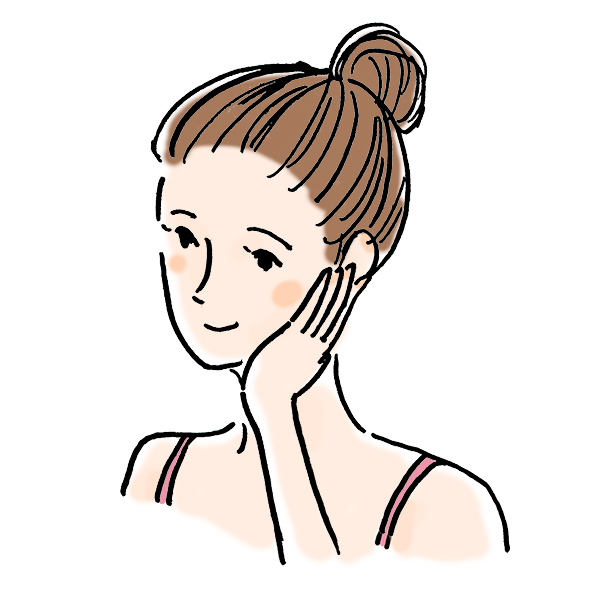
オレイン酸には、善玉コレステロールは減らさずに、
動脈硬化の原因となる悪玉コレステロールを減らしてくれる効果があります。
コレステロール値を抑えて、生活習慣病の予防に繋がります。
効果効能② 血管を強化し血行をスムーズに、心筋梗塞や脳卒中などの予防

食生活の乱れやストレスによる悪玉コレステロールの増加や加齢によって、 血管が徐々にもろくなったり、詰まったりしてしまいます。
すると、酸素や栄養素を体の隅々まで届ける役割を充分に果たせなくなり、心臓に負担をかけてしまうのです。
ごま油の成分は血液もサラサラにしてくれるので、動脈硬化・心筋梗塞の予防などさまざまな生活習慣病の対策に良いとされます。
効果効能③ 抗酸化作用により活性酸素の攻撃を抑制、がんや生活習慣病を予防

活性酸素による細胞へのダメージは、がんや生活習慣病の大きな原因となりますが
オレイン酸には抗酸化作用があり、活性酸素の攻撃を抑制してくれます。
そのため、若返り効果や、がんや生活習慣病を予防する働きが有ると言えます。
効果効能④ 抗酸化物質で血管の老化を防ぐ、アンチエイジング効果
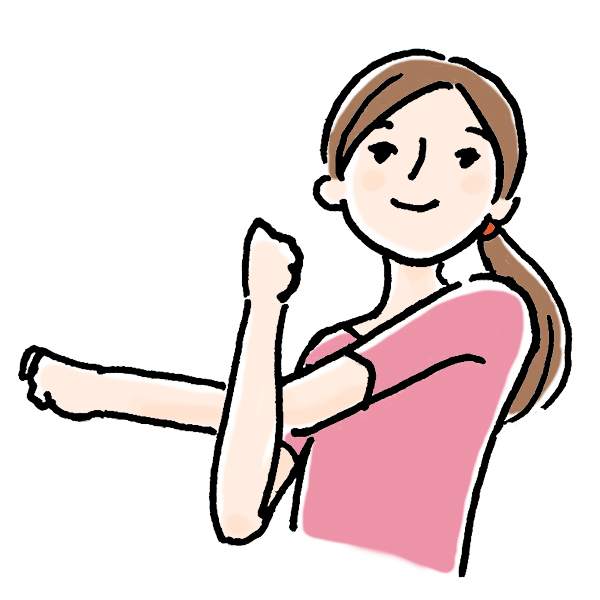
健康の要である血管の細胞もまた油でできているので、
全身をめぐる血管の老化をストップし、若々しさをキープするためには、
油に溶ける「抗酸化物質」が必要となってきます。
効果効能⑤ 腸を活発にし便秘の解消、腸内環境の改善
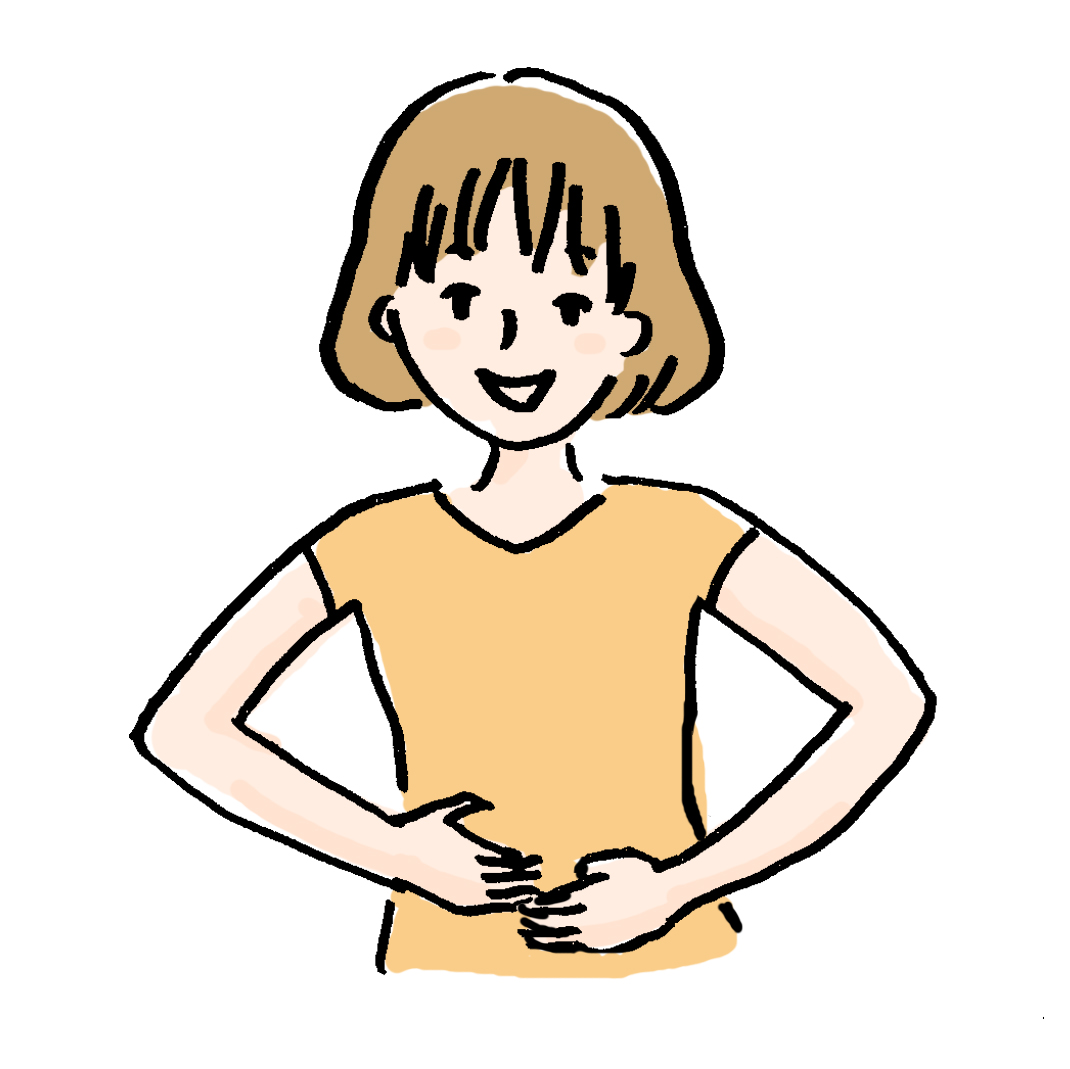
腸を刺激して蠕動運動を活発にしてくれるので、排便が促されるという効果が有ります。
お通じが良くなったり、潤滑油の役割を果たして腸内での便の通りが良くなります。
また硬い便も柔らかくなり出しやすくしてくれ便秘の解消に繋がります。
効果効能⑥ 皮膚を柔軟にしてシワの予防、保湿成分で美肌効果

抗酸化作用により活性酸素の攻撃を抑制するため、老化防止や若返り効果が期待できます。
皮膚を柔軟にする効果でシワの予防になり、保湿成分も多いため美肌効果にも繋がります。
参考文献:New Food Industry 2021年 63巻 5月号「日本人成人男女における精製ごま油摂取による抗酸化効果および血流改善効果検証試験:ランダム化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験」
参考文献:National Library of Medicine「Sesame oil attenuates ovalbumin-induced pulmonary edema and bronchial neutrophilic inflammation in mice」
香りがとっても良い!「ごま油」
どちらも安全な昔ながらの圧搾方法で搾油されており、「香りが良い」と評判の胡麻油です。しも農園のごま油は、貴重な完全国産、農薬不使用の「みまたんごま」 を昔ながらの圧搾機で製油されています。
ごま油の栄養と成分
ごま油とは

一般的にごま油とは、白ごまを焙煎して油分を搾ったものを指します。
琥珀色をしており、香ばしい特有の香りがあります。日本でも古くから油脂原料とされ、馴染みの深い油です。

ごま油は、全食品のなかでもトップクラスと言われるほど、リノール酸を豊富に含みます。
リノール酸はコレステロールを下げる働きが高いためダイエットにも役立ちます。
人が体内で合成できない必須脂肪酸ですので、食物から摂ることが重要です。
ただし、油ですからカロリーは高いので、とり過ぎには注意してください。
また、セサミンやセレンなど、抗酸化作用の強い成分も多く含まれます。
それにより、活性酸素の働きを抑えるのでアンチエイジング・美容にもいいとされます。
・オレイン酸(約60%)※オメガ9(n-9)系脂肪酸
心臓障害を防ぐ善玉コレステロールの値はそのままに、
悪玉コレステロールの値を低下させる働きがあるといわれています。
・リノール酸(約23%)※オメガ6(n-6)系脂肪酸
血中コレステロール値を低下させ血管の硬化を防止します。
・α-リノレン酸(約10%)※オメガ3(n-3)系脂肪酸
アレルギー性疾患を改善し、脳細胞を活性化する一方、血液をサラサラにし、
動脈硬化・脳梗塞・心筋梗塞・高血圧などの予防に効果があると言われています。
・セサミンK
ごまの成分としてお馴染みのセサミンには強力な抗酸化作用があります。
活性酸素や悪玉コレステロールの増加を抑える働きや、肝機能を高める作用もあります。
・セレン
活性酸素の生成を抑る働きがあります。
ビタミンEと共に摂取することで相乗効果があらわれますが、ごまはどちらも含んでいるため非常に効果的です。
活性酸素を抑えるので、がんの発症リスクを減らす作用もあると言われています。
・ビタミンE
抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。
日本人の摂取するビタミンE(トコフェノール)の約30%は植物油から摂取している現状です。
参考文献:文部科学省食品成分データベース「ごま油」
ごま油の選び方と安全性|体にいいごま油は?

植物油の安全性について
健康に良いとされる植物油ですが、大量生産の効率化によって
安全とは言えない油が市場に出回っているのも事実です。
本当に体にいい安心して使える油は、昔ながらの製法で圧搾されたごま油。それでは、その理由を見ていきましょう。
注目すべきは、油の抽出法
製造過程において、油を抽出する方法が二種類あります。
- 圧搾法(低温圧搾法・一番搾り)
- 専用の機械で潰して油を抽出する、昔ながらの製法。
- 化学溶剤での抽出法
- ヘキサン等の化学溶剤を使用して抽出する製法。
- ■圧搾法(低温圧搾法・一番搾り)とは・・・
- 圧搾法はその名の通り、物理的に原材料に専用の機械で圧力をかけて潰し、搾る方法です。
採油するのに手間がかかるもので、しかも原材料に含まれる油を全て採りきることができませんでした。
昔はこれが当たり前だったのです。
- ■化学溶剤での抽出法とは・・・
- 対して、コストをかけず大量に搾油する大手油脂メーカー等では
油をできるだけ無駄なく効率よく採油するために、
「ヘキサン」という石油系の溶剤を使用して原材料のの99%もの油を抽出します。
化学溶剤抽出の危険性
製造過程においてヘキサンは完全に取り除かれるため安全であるとされていますが、
ヘキサンとはガソリンにも含まれている成分です。
人の皮膚や呼吸器などに刺激を与えたり、
生殖機能や胎児にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
さらに、鼻を突くツンとした刺激臭がありますので、食用にするには脱臭をしなければなりません。
その脱臭作業のためには油を200℃以上の高温に加熱する必要があるのですが、
その際、人体に有害な「トランス脂肪酸」が発生してしまうのです。
- トランス脂肪酸とは
- トランス脂肪酸とは植物油に水素を加えた時に発生する副産物の油の成分で、
市販のマーガリンやパン・ケーキ等にも使われるショートニングに多く含まれています。
がんや動脈硬化の原因のもなりうる、人体に悪影響を与える
物質だということが既に認められており、
日本では規制されていませんが、摂取量を規制している国もあります。
スーパーなどで一般的に安価で売られているものは、化学溶剤を使った製法の油がほとんどと言えます。
もちろん商品になる際は化学溶剤は除かれ安全性のチェックもされているはずですが、
トランス脂肪酸が含まれ、熱処理されているため栄養素も減ってしまっています。
安心して油本来の健康効果をそのまま摂れるのは、圧搾法で手間をかけて作られた製品です。
圧搾法の油は溶剤で抽出した油よりも天然成分のビタミンや抗酸化物質が多く残り、
健康効果はより高くなります。
日々の食生活に欠かせない油ですから、健康のために安全なものを選んで使いたいものですね。



ごま油の保存方法
ごま油は他の食用油と比べ、酸化しにくいという特徴がありますので、
賞味期限によりますが、未開なら約2年ほど保存ができます。
開封した場合には空気や光により酸化が進行するので、冷蔵庫に入れる必要はありませんが
高温多湿を避け光の当たらない冷暗所で保存しましょう。
安全なごま油
かわしま屋では安全な、化学溶剤を使用せずに昔ながらの方法で圧搾されたごま油を販売しております。

金ごま油 250g|堀内製油
ごまの中でも香りと旨味が強い金ごまを使用したごま油です。香りを最大限に引き出す焙煎作業や、昔ながらの圧搾製法で一滴一滴こだわりをもってつくられています。香りと甘みを程よく持ち合わせた使いやすい油です。
2000 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>
しも農園|金ごま油 国産圧搾絞り 100g
ヘルシーで栄養たっぷり、そのまま冷奴にかけたり、ドレッシングに利用したり、また炒め物に使用しますと香りが際立ちお料理が更に美味しくなります。
1991 円(税抜)
\初回購入で300ポイントGET!/
かわしま屋の商品を見る >>ごま油の種類

一般的なごま油
油分の多い白ごまを原材料とし、炒ってから搾油します。 炒り方によって、色の濃さや風味が変わるため、様々な商品があります。
中華料理で使われる色の濃いものは200℃以上の高温で焙煎されたものです。
太白油
焙煎せずに生のまま搾ったものは「太白油」と言い、色は透明です。
味は焙煎したものと同じようにコクがありますが、特有の香ばしい香りはあまり無いため
香りを気にせずに料理に使うことができます。
赤ちゃんから大人までオイルマッサージや、インド発祥の健康法アーユルヴェーダにも使われます。
黒絞り
黒ごまから抽出したごま油もありますが、白ごまと比べて油分が少なく皮が硬いため、あまり一般的に出回っていません
白ごまのものと比べて香りがさらに強いのが特徴。
皮の色は油の色には影響を与えないので、白ごまのものと同様に焙煎の強弱に応じた色をしています。
ごま油の使い方と簡単レシピ

酸化しづらく熱にも強い、頼もしいごま油。その使い方をご紹介します。
定番!炒め物に最適
炒め物はごま油料理の鉄板。ごまの豊かな香りが食欲をそそります。
中華料理が定番ですが、パスタ等に使っても上品な味に仕上がります。
仕上げにごま油をひとさじかけると、ごまの香りをより一層楽しめます。
揚げ物も香りよくカラッと仕上がる
天ぷらや唐揚げなど揚げ物油はサラダ油が一般的ですが、
熱に強く劣化しにくいごま油は揚げ物にも向いています。
揚げ油にごま油を混ぜて使うだけでも、ごまの風味で美味しくなりますし、
劣化しにくい性質のおかげで油の持ちも良くなります。
ごまの風味がたまらない、和え物
シンプルにごまの風味を楽しめる和え物も、ごま油料理の定番ですね。
素材の美味しさを、ごまの香りが引き立ててくれます。
醤油と混ぜてお刺身と和えたり、お酢を混ぜてマリネにも。
調味料としても活躍!
ごま油は香ばしい風味とコクがありますので、香り付けや調味料としても使われます。
- ・お使いの醤油に少量混ぜて使ってみる
- ・塩と混ぜてお肉のつけダレ代わりに
- ・冷奴にそのままかける
- ・焼き魚に少々たらす
- ・ごま油を熱して、野菜にかける
- ・ラーメンのスープにチョイ足し
など、お気軽にお試ししてみてください。
香りを活かしてドレッシング
油自体の香りが豊かなごま油は、ドレッシングにもピッタリ。
中華ドレッシングが定番です。お好みの分量でアレンジも。
ごま油と塩だけでおにぎりが美味しい!
おにぎりを握るとき、手に塩とごま油をつけて握る・・・ただそれだけです。
シンプルだけど、ごま油の風味とお米の味がしっかり感じられ、おにぎりがとっても美味しくなります。
お米好きの方にはおすすめの食べ方です。
海苔を巻いたら、韓国のりのような味にもなります。
オリーブオイルのように、パンにごま油?
パンにごま油。一見合わなさそうな組み合わせですが、
ごま油にもオリーブオイルのようにしっかりとした香りがありますので香ばしく、美味しくいただけます。ぜひ試してみて下さい!
ごま油のおいしさの理由|ごま油は酸化しやすい?

様々な料理に活用できるごま油、美味しさと使いやすさには理由があります。
酸化しにくい
開封後、短時間で酸化してしまう食用油も多い中で、ごま油は天然の酸化防止剤でもある「ビタミンE」
が多く含まれるため、酸化しにくい油です。
安定性の良い油で、加熱調理にも栄養が損なわれずに使えます。
加熱に強く、劣化しにくい
油脂の加熱による劣化の進行がゆるやかで、最も劣化しづらい食用油と言えます。
揚げ物の油臭さは精製ごま油が最も弱く、美味しく仕上がります。
べたつきが少なく、冷めてもおいしい
加熱に強く安定性に優れているため、揚げ物などを作り冷めてしまったあとでも
比較的味を損なわずに食べることができます。
搾油しやすいため安全性の高い商品が多い
ごまは油の原料の中でも油分が多い作物なので、現代普及している溶剤を使用した抽出法ではなく
昔ながらの圧搾法でも比較的効率よく採油できるため、普及品でも安心して使える商品が多く売られています。
●管理栄養士からのコメント
ごま油は、他の食用油と比較して酸化しづらい特徴があります。
製造方法の焙煎の度合いによってごま油の色が変わります。無色透明のごま油は揚げ物やお菓子作りに、琥珀色のごま油は炒め物や仕上げに使用するなど料理によって使い分けることをおすすめします。
ただ、ごま油は大さじ1杯で約130kcalあるため、摂取のしすぎには注意しましょう。
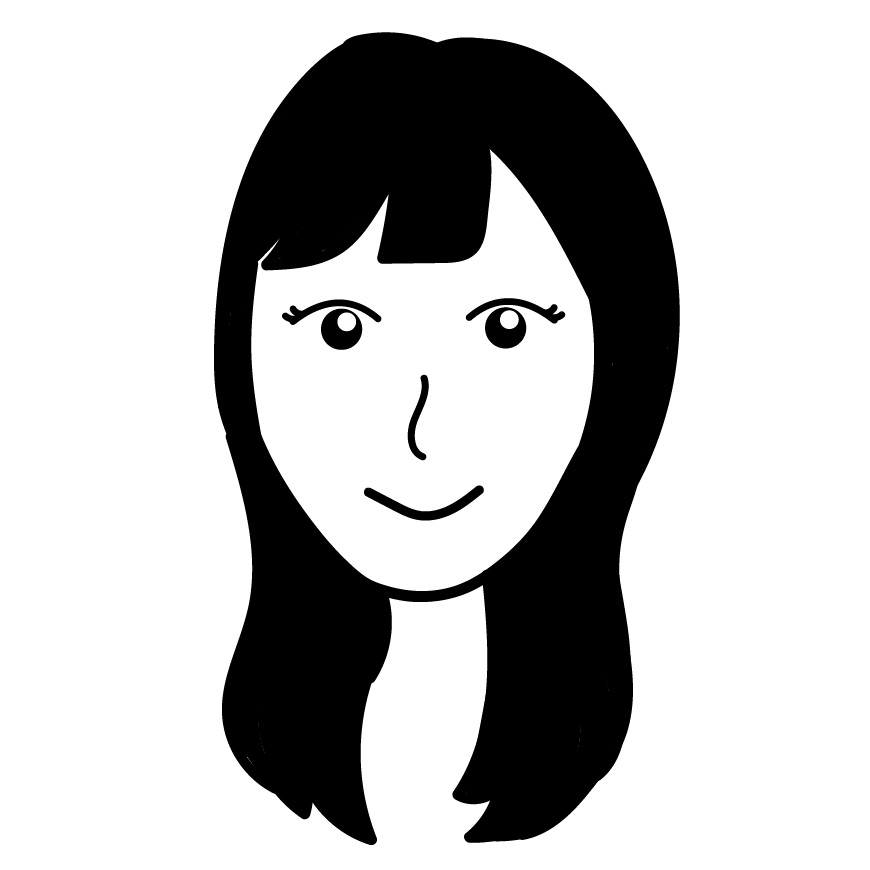
管理栄養士プロフィール
◎鶴田ようこ
調理師・管理栄養士。2つの資格を生かし食用油脂製造会社にて品質管理に従事。
菜種油、オリーブ油の品質に関する分析、衛生管理等を行う。
幼い頃から野菜作りの手伝いをしていたことから、季節の野菜料理が得意。
ごま油に関するQ&A
- 開封したごま油の保存方法を教えてください。
- ごま油は、食用油のなかでも酸化しにくい油ですが、しっかりフタをして、なるべく早く使いきるようにしましょう。
流しの下や戸棚の暗いところなど湿気や熱のこもらない場所で、常温保存(20℃程度)で品質には問題ありません。
- ごま油を料理の風味付けに使いたいのですが、入れるタイミングはいつがいいのでしょうか。
- 料理の早めの段階でごま油を使って火を入れすぎると匂いが飛ぶことがあるので、
香りづけしたい時は仕上げの段階でごま油を回し入れるのが良いでしょう。
- ごま油の色の違いはなんですか?
- 一般的なごま油は油分の多い白ごまを原材料とし、炒ってから搾油します。
炒り方によって、風味や色の濃さが変わります。
- ごま油の一日の摂取量はどのくらいですか?
- ごま油には体に良い成分がたっぷりと入っていますが、油ですので摂りすぎには気をつけましょう。
一日5~10グラムほどにするのが良いでしょう。
- ごま油は体にいいですか?
- ごま油は、他の油と同様に摂りすぎなければ健康にいいです。
悪玉コレステロールを減らす働きのある不飽和脂肪酸や、老化から守るビタミンE(トコフェノール)が多く含まれています。
おすすめのごま油
かわしま屋では安全で香り高い希少なごま油を取り揃えています。この機会にお試しください。






 もくじ
もくじ
















