花椒(ホアジャオ)の使い方|どんな味や香り?合う料理とは

スーパーで手に入る身近なスパイスであるにも関わらず、なかなか手を出しづらい「花椒」。
でも、実は今、ハマる人続出の注目スパイスなんです。
「読み方がわからない!」「山椒とどう違うの?」「使い方は…?」
疑問ばかりで「得体の知れないスパイス」という印象をもたれている方も、使ってみたら魅了されてしまうかもしれません。
今日は、皆さまの花椒に関するさまざまな疑問にお答えしつつ、花椒をつかった簡単でおいしいレシピをご紹介します。
花椒とは

花椒とは、中国原産のミカン科サンショウ属の低木「カホクザンショウ」の果実の皮です。
日本での読み方は「かしょう」、中国語では「ホアジャオ」「ホァジョー」などと発音されます。
柑橘系の爽やかで奥ゆきのある香りとしびれるような辛さが特徴で、中国料理、特に四川料理には欠かせないスパイスです。
日本では「麻婆豆腐のスパイス」として有名ですが、中国では炒め物や煮込み料理、漬けだれなどさまざまな料理に使われ、その応用範囲の広さは日本の山椒以上ともいえるでしょう。
生薬としては「蜀椒(しょくしょう)」と呼ばれ、身体の不調をやわらげる効能ももつとされています。
花椒と山椒の違い
花椒についてまず何よりも気になるのが、「日本の山椒とどこが違うの?」ということ。
花椒・山椒の違いと分類について調べました。
花椒と山椒は同じ植物?

中国原産の「カホクザンショウ」の果皮を乾燥させた「花椒」に対し、山椒は日本原産の「サンショウ」の果皮。同じミカン科サンショウ属ですが別の種です。
どちらも熟した果実の皮を乾燥させたものをスパイスとして使いますが、日本の山椒は果皮だけでなく若芽を「木の芽」として料理の彩りや香りづけに使ったり、未熟な果実を佃煮にしたりとさまざまな部位を利用します。
特に花椒と間違われやすい「花山椒(はなざんしょう)」は、山椒の花を食材として使ったもの。
つぼみの時が最も香り高いといわれるため、つぼみの時に収穫して料理のつまや佃煮などにされることが多いようです。
柔らかくしゃきっとした食感と清涼感ある香り、ほろ苦さなどが好まれています。
花椒の名称に「花」とつくのは、赤く開いた果実が花のように見えるからで、花山椒のように花を使っているわけではありません。
味や香り、使い方の違い

「花椒」と「山椒」には、同じパウダーで使った場合次のような味や香りの違いがあります。
| 味や香り | 使い方 | |
|---|---|---|
| 花椒 | ・柑橘系の爽やかで奥ゆきのある香り ・ベルガモット系の華やかな香り ・口の中がしびれるような強い辛み |
・餃子や炒飯にふりかけて香りと辛みづけ ・蒸し物や茹で野菜に風味と辛みづけ ・煮物や鍋に香りとしびれ感をプラス |
| 山椒 | ・柑橘系の爽やかな香り ・繊細ですがすがしい香り ・ピリリとした軽い辛み |
・鰻のかば焼きの臭み消し ・焼き鳥の風味づけ ・鍋の風味と辛みづけ |
花椒はビリビリとした強い刺激があるのが特徴で、香りも辛みもパンチがきいています。
対する山椒は「臭み消し」として使われることが多いですが、コショウの代わりに振りかけると料理に辛みと爽やかで品のある風味をつけることができます。
花椒がない時は山椒で代用することもできますが、やはり花椒独特の「しびれ感」は山椒には出せないようです。
赤花椒・青花椒・籐椒の違い

さて、山椒とは違う独特の香りと辛みをもった「花椒」ですが、実は「花椒」にも種類があるってご存じでしたか?
通常「花椒」と呼ばれているのは「赤花椒」。花椒の果実が熟してから乾燥させた果皮で、柑橘を思わせる爽やかな香りと刺激が特徴です。
通常の「花椒」よりもさらに刺激的で上品な香りとされているのが「青花椒」。
これは花椒の実を成熟前の段階で摘んだもので、「籐椒(タンジャオ)」とも呼ばれます。
花椒と比較するとさらにフレッシュ、フルーティーで豊かな香りが特徴。
「赤花椒」と「青花椒」はしびれ感と香りの強さが異なるため、ブレンドして使うとより花椒の魅力が際立つと言われています。
「花椒が気に入った!」という方は青花椒も手に入れて、さらに香り豊かなスパイス使いを楽しんでみてください。
花椒の使い方
さて、花椒は「粉末タイプ」のほか、「ホール」や「花椒塩(かしょうえん)」、「花椒辣醤(ファージャオラージャン)」など、さまざまな形で販売されています。
特に使い方に困るホールタイプを中心に、花椒の使い方をご紹介しましょう。
花椒の使い方(ホール)

「使いづらい」と敬遠されるホールタイプですが、香りが劣化しやすい粉末タイプと比べて鮮烈な香りと辛みを維持しやすく、使う頻度が低い方にこそおすすめです。
ホールタイプの主な使い方は次の3つ。
- ①調理の際に油に入れて使う
- ②粉末にして使う
- ③「花椒油(ホアジャオユ)」を作り、料理にかけて使う
それぞれ具体的な方法を見ていきましょう!
- ①調理の際に油に入れて使う
-
そのまま入れてもOKですし、コップの底などで軽くつぶしてから使っても構いません。
炒め物などの最初に油を熱し、その中に軽く潰したホールの花椒を入れて、弱火で味と香りを引き出します。
焦がすとえぐみが出てしまうので、焦がさないように注意してください。
長時間煮る煮物などの場合はホールのまま入れて煮込みます。器に盛る時に取り除く必要はありません。
- ②粉末にして使う
-
「料理の仕上げにかけたい」「唐揚げにつけたい」「餃子のたねに混ぜたい」といった場合は粉末にします。
①の使い方よりも香りが強く感じられるため、①の後、さらに仕上げに②を使うということもあるようです。
最初から粉末になっているものを使うよりもフレッシュな香りが楽しめます。
コーヒーミルなどを使うのもいいですし、すり鉢ですりつぶして使うのもおすすめです。
- ③「花椒油(ホアジャオユ)」を作り、料理にかけて使う
-
花椒の香りを移した「花椒油」。
これを作っておくとちょっとした和え物やサラダに使うこともでき、グンと花椒の応用範囲が広がります。
「家族は辛い物が苦手だけれど自分はもっとシビれたい!」という場合にも便利です。

花椒油の材料
- ・花椒(ホール)
- 10g
- ・植物油※なたね油やごま油など
- 100ml
花椒油の作り方
- 1
- 花椒をコップの底などで軽くつぶします。
- 2
- 小鍋に1と植物油を入れ、弱火で焦がさないように加熱します。
- 3
- 香りが立ったらコーヒーフィルターやキッチンペーパーを敷いたざるなどで濾し、粗熱をとります。
- 4
- 保存容器に入れます。
- ・ごま油で作れば、茹で野菜を和えるだけで中華風の一品ができます。
- ・できあがったオイルは、冷暗所で1ヶ月ほど保存可能です。
- ・油が劣化せず香りもフレッシュなうちに使い切るのがおすすめです。
花椒の使い方(粉・花椒塩・花椒辣醤)

粉末タイプや花椒塩、花椒辣醤(ファージャオラージャン)の使い方は簡単です。
- <花椒(粉末タイプ)・花椒塩の使い方>
- ・唐揚げや焼き鳥などにふりかけて
- ・スープや鍋の隠し味として
- ・中華風の和え物やドレッシングに
- ・餃子やハンバーグの下味をつける時に
- ・カレーのスパイスとして
- ・炒飯のコショウ代わりに
- <花椒辣醤(ファージャオラージャン)の使い方>
- ・しゃぶしゃぶの漬けだれに
- ・餃子のたれに
- ・ラーメンやうどんに一さじ加えて
- ・鍋に一さじ加えて
後からかけたりつけたりすることができるので、家族の好みに合わせて使うことができますよ。
粉末花椒はコショウのように、花椒辣醤は柚子胡椒のように、いつもの料理にプラスして使ってみてください!
花椒の効果・効能
中国では生薬として使われるという花椒。
少量でも身体の調子を整えるさまざまな効果をもっています。
花椒の効果・効能1 健胃効果
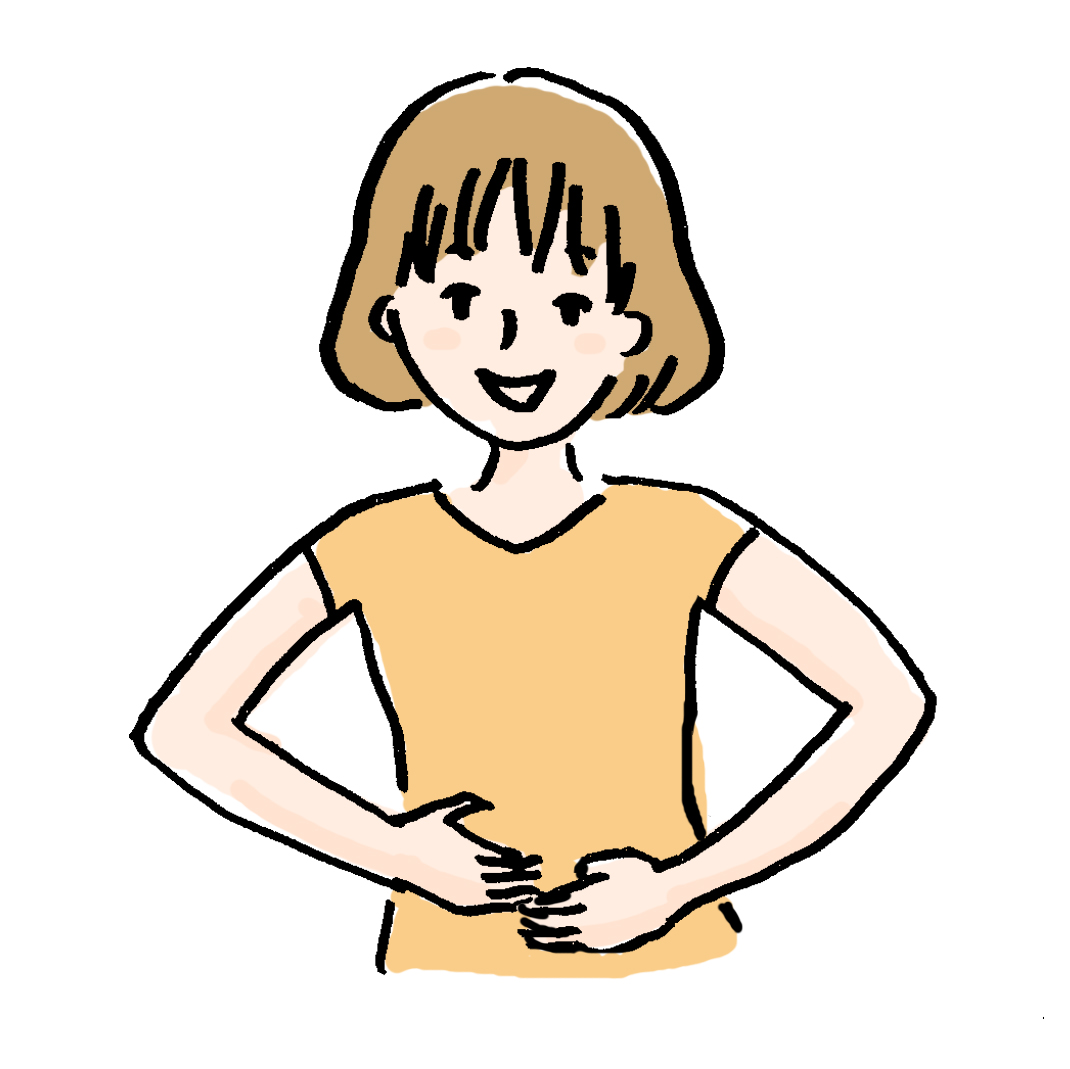
花椒には、消化をすすめ、食欲を引き出す効果があります。
また、お腹の冷えからくるさまざまな症状にも有効です。
花椒の効果・効能2 身体を温める効果

花椒には、身体を穏やかに温める効果があります。
冷え性の方は改善効果が期待できるでしょう。
花椒の効果・効能3 鎮痛効果

しびれ感をもたらす花椒には、鎮痛効果もあるといわれています。
生薬としては腹痛や歯痛、関節の痛みなどに用いられることもあるそうです。
花椒の効果・効能4 精神安定効果
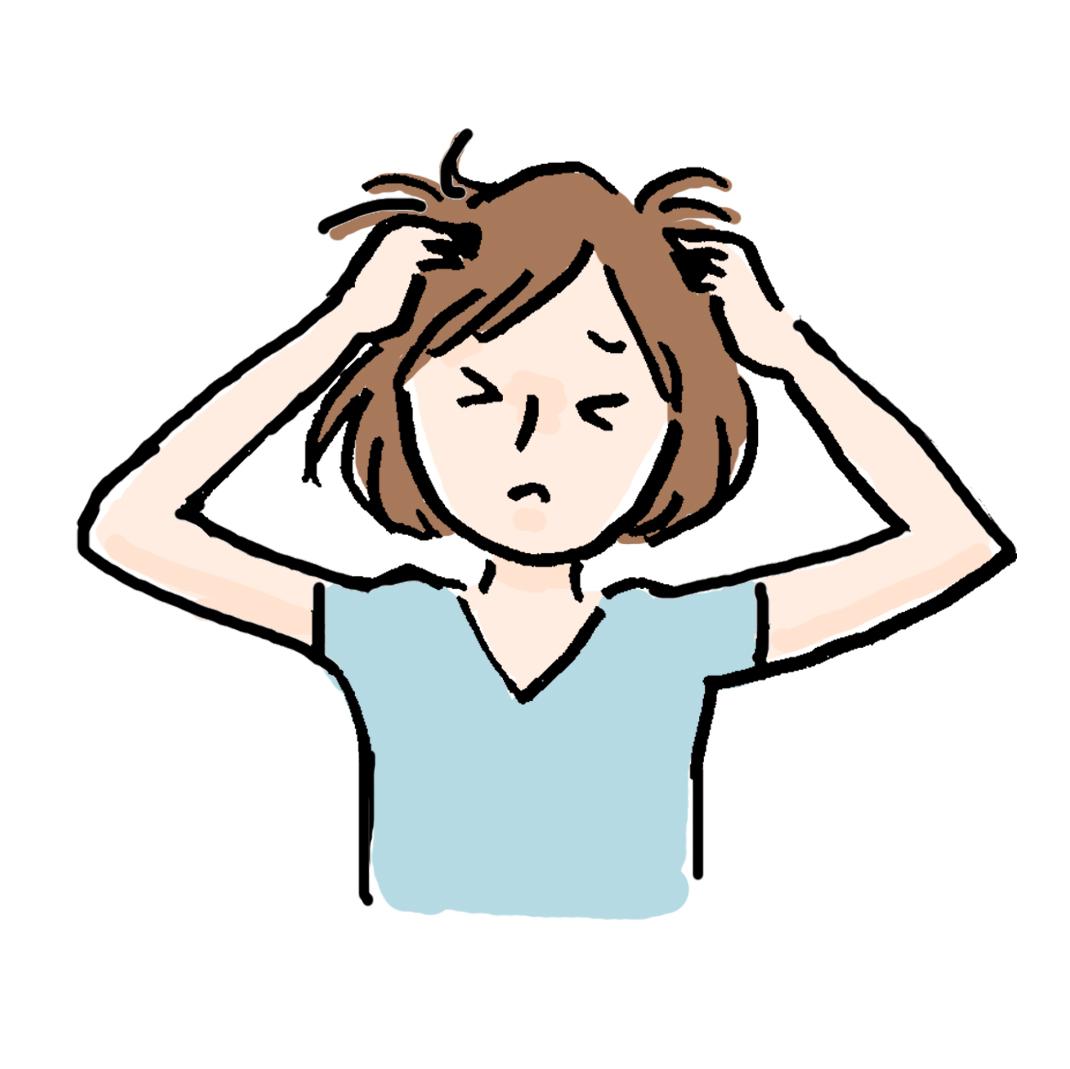
花椒には精神を安定させる効果があります。
気を巡らせる効果もあるため、ストレスなどのイライラや、鬱々とした気分の方のリフレッシュにも役立ちそうです。
おすすめ花椒レシピ
「花椒を使った本格的な麻婆豆腐が食べたい!」という方、「麻婆豆腐のために花椒を買ったけど、余っちゃった…」という方、「花椒が好きでたまらない!」という方、どんな方にも一度は作ってみていただきたいレシピです。
ビリビリ麻婆豆腐
辛みと刺激が苦手な方は豆板醤と花椒を控えめにして作ってみてください。

材料
- ・豚ひき肉
- 300g
- ・ごま油
- 大さじ1
- ☆にんにく(すりおろす)
- 2かけ
- ☆豆豉(トウチ※)(みじん切り)
※黒大豆を発酵させたもの。なければ豆鼓醤(トウチジャン)か八丁味噌で代用。 - 大さじ1/2
- ☆豆板醤
- 大さじ1
- ・鶏がらスープ
- 300ml
- ・豆腐(2㎝角に切る)
- 300g
- ●醤油
- 大さじ1+1/2
- ●紹興酒
- 大さじ1
- ●葉にんにくまたはにんにくの芽(そぎ切り)
- 1本
- ●長ねぎ(みじん切り)
- 5~6㎝
- ・片栗粉
- 大さじ1
- ・花椒(ホールのものをミルなどで粉末にしたもの)
- 大さじ1
つくり方
- 1
- 中華鍋に油を熱し、ひき肉を入れてよく炒めます。いじると肉汁が出てしまうのであまりいじらずにこんがりと香りよく炒めます。
- 2
- ☆をすべて入れ、馴染むように炒めて鶏ガラスープのうち200mlを注ぎます。
- 3
- 別の鍋にお湯を沸かし、切っておいた豆腐を入れて茹でます。
- 4
- 3を網ですくって煮えている2の中に入れます。
- 5
- 4に●を順に入れます。
- 6
- 鶏ガラスープの残り100mlに片栗粉を溶き、5に入れてとろみをつけます。
- 7
- 最後に強火で火を入れてから皿に盛り、仕上げに花椒をかけます。
濃厚シビレ汁なし坦々麺
あればたれに花椒辣醤(ファージャオラージャン)を加えて花椒の香りをアップさせるのもおすすめ。

材料
- ・中華麺
- 2玉
(肉みそ)材料
- ・豚挽き肉
- 200g
- ・長ネギ
- 1本(みじん切り)
- ・にんにく
- 1かけ(みじん切り)
- ・ショウガ
- 1かけ(みじん切り)
- ・豆板醤
- 小さじ1
- ・ごま油
- 大さじ1
- ☆紹興酒
- 大さじ1
- ☆しょうゆ
- 大さじ1
- ☆甜麺醤
- 大さじ1+1/2
(たれ)材料
- ●黒酢
- 大さじ1
- ●練りごま ※ピーナッツペーストでも可
- 大さじ1
- ●すりごま
- 大さじ1
- ●ごま油
- 小さじ1
- ●ラー油
- 大さじ1
- ・花椒(ホールのものをミルなどで粉末にしたもの)
- 小さじ1
(仕上げ)材料
- ・ナッツ(ピーナッツかミックスナッツなどを砕いたもの)
- 大さじ4
- ・チンゲンサイ、水菜など
- 好みで
つくり方
- 1
- 中華鍋にごま油を入れて熱し、長ネギ・にんにく・ショウガと豆板醤を炒めます。
- 2
- 香りが立ったら豚ひき肉を入れ、こんがりと香ばしく炒めます。
- 3
- ☆をすべて入れ、混ぜながら軽く水気を飛ばします。
- 4
- 別の鍋に湯をわかし、中華麺を茹でます。
- 5
- ●をすべてボウルに入れて混ぜ、3を入れ、さらに茹であがって水気を切った中華麺を入れて混ぜます。
- 6
- 器に盛り、花椒とナッツをかけ、好みの野菜を添えてできあがりです。
青花椒のハイボール
花椒がハイボールのスッキリ感を強め、肉料理などにぴったりです。
通常の花椒でも作れますが、できれば青花椒のフレッシュ感と豊かな香りをぜひ味わっていただきたい一杯です。

材料
- ・ウイスキ
- 40ml
- ・炭酸水
- 160ml
- ・青花椒(ホール)
- 適量
つくり方
- 1
- 冷やした炭酸水とウイスキーをグラスに注ぎます。
- 2
- そこに粗く挽いた花椒を入れ、かき混ぜてできあがりです。
花椒についてのQ&A
- 花椒を食べ過ぎるとどうなりますか?
- 通常、食事に使う量であれば問題はありませんが、一度に大量に摂ると下痢など思わぬ症状が出る可能性があり、身体のバランスを崩す原因にもなります。健康効果を期待して大量に摂取したりすることはやめましょう。
- 花椒の代用になりそうなものを教えてください。
- 花椒がない場合は山椒が近い風味ですが、独特の「しびれ感」はありません。
山椒の方が香りと辛みがマイルドなので、量を増やして使ってみてください。
- 花椒の賞味期限や保存方法について教えてください。
- 花椒の賞味期限は、開封しなければ1年半ほどです。
ただ、常温では香りが揮発しやすいので、開封後は密封して、冷蔵もしくは冷凍するのがおすすめです。
- 花椒を食べるとしびれる理由は?
- 花椒には辛み成分であるサンショールや舌を麻痺させるキサントキシンが含まれ、これが「しびれる感覚」をもたらすといわれています。
- 花椒をかけましたが辛くないです。どんなふうに調理すればよいでしょうか?
- ホールのものを使って油にしっかりと味を抽出し、調理すると辛みがしっかり出ます。辛みや香りは保存している間に弱まっていくため、新鮮なものを使うのもポイントです。






 もくじ
もくじ
















