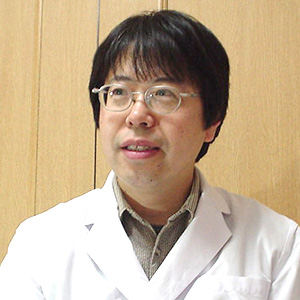水溶性食物繊維とは。特性や効果、おすすめの摂取方法まで全て解説

「水溶性食物繊維って何?体に良いって聞いたけど具体的に知りたい!」
「食物繊維、不溶性食物繊維とはどう違うの?」
こんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
今回はそんな疑問にお答えすべく、食物繊維~水溶性・不溶性食物繊維まで幅広く解説していきたいと思います。
また、効率的な摂取方法・便秘解消に関する解説も含めておりますのでぜひ参考にしてみてください。
水溶性食物繊維とは

まずはじめに、食物繊維は「人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分の総体」と定義されている栄養素です。
植物性の食品に多く含まれており、ごぼうやほうれん草が代表的です。
また食物繊維には主に、水に溶ける”水溶性食物繊維”と、水に溶けにくい”不溶性食物繊維”の2種類があります。
中でもアルギン酸のような水溶性食物繊維は特に、便秘解消や肥満の予防、生活習慣病の予防など多くの健康効果が期待できる栄養素のため、健康的な体づくりには欠かせません。
もちろんセルロースのような不溶性食物繊維にも、便通を促進するなどの健康効果があり、水溶性・不溶性関係なく食物繊維は健康にとても有益です。
近年では不足しがちと言われるくらいなので、積極的に摂取していきたいですね。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の違い
次に、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の違いを性状・特性の観点からみていきましょう。
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|
| 性状 | |
| ネバネバやサラサラ | ザラザラやボソボソ |
| 特性 | |
| <保水性に優れる> ▶水分を吸収して膨らみ、腸を刺激することで便通を促します。 |
|
| <発酵性> ▶腸内で発酵することで善玉菌が暮らしやすい腸内環境に整えます。 |
|
| <吸着性> ▶余分な糖や脂質を吸着し体の外に排泄します。 |
<繊維状> ▶噛む回数が増え、歯や顎の発育を支えます。 |
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の具体的な成分名、またその成分が多く含まれる食品は以下の通りです。
| 成分 | 多く含まれる食品 |
|---|---|
| ペクチン | りんごや柑橘類の果皮、野菜 等 |
| アルギン酸 | 昆布などの褐藻類 等 |
| グルコマンナン | こんにゃく、山芋 等 |
| ガム質 | グアー豆、麦類 等 |
| 成分 | 多く含まれる食品 |
|---|---|
| セルロース | 野菜、穀類、豆類 等 |
| ヘミセルロース | 穀類、豆腐、小麦ふすま 等 |
| リグニン | 野菜、穀類、豆類 等 |
| キチン | 甲殻類の殻 等 |
以上のように、食物繊維は水溶性・不溶性の2つに分けられそれぞれ違いがあります。しかし、どちらも健康に良い効果をもたらしてくれることに違いはありません。それぞれの違いをきちんと把握した上で活用していきたいですね。
食物繊維含有量の多い野菜・食品おすすめランキング

ここからは、食物繊維(特に水溶性食物繊維)をより効率的に摂取できるおすすめの食品を、ランキング形式で紹介していきます。
ぜひお料理を作る際の参考にしてみてくださいね。
野菜類の食物繊維量ランキング
| 1位 らっきょう(g/可食部100g) | ||
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 18.6 | 2.1 | 20.7 |
| 2位 にんにく(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 4.1 | 2.1 | 6.2 |
| 3位 ごぼう(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 2.3 | 3.4 | 5.7 |
| 4位 めキャベツ(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.4 | 4.1 | 5.5 |
| 5位 モロヘイヤ(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.3 | 4.6 | 5.9 |
穀類の食物繊維量ランキング
| 1位 大麦(米粒麦)(g/可食部100g) | ||
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 6.0 | 2.7 | 8.7 |
| 2位 ライ麦(全粒粉)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 3.2 | 10.1 | 13.3 |
| 3位 オートミール(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 3.2 | 6.2 | 9.4 |
| 4位 ライ麦パン(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 2.0 | 3.6 | 5.6 |
| 5位 アマランサス(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.1 | 6.3 | 7.4 |
| (参考)精白米(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| ー | 0.5 | 0.5 |
きのこ類の食物繊維量ランキング
| 1位 なめこ(g/可食部100g) | ||
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.0 | 2.3 | 3.3 |
| 2位 生しいたけ(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.4 | 3.8 | 4.2 |
| 3位 えのきたけ(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.4 | 3.5 | 3.9 |
| 4位 まつたけ(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.3 | 4.4 | 4.7 |
| 5位 ぶなしめじ(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.3 | 3.4 | 3.7 |
果実類の食物繊維量ランキング
| 1位 きんかん(g/可食部100g) | ||
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 2.3 | 2.3 | 4.6 |
| 2位 干しぶどう(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.2 | 2.9 | 4.1 |
| 3位 マルメロ(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.7 | 4.4 | 5.1 |
| 4位 グァバ(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.7 | 4.4 | 5.1 |
| 5位 ラズベリー(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.7 | 4.0 | 4.7 |
豆類の食物繊維量ランキング
| 1位 きな粉(g/可食部100g) | ||
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 2.7 | 15.4 | 18.1 |
| 2位 いんげん豆(ゆで)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.5 | 11.8 | 13.3 |
| 3位 大豆(ゆで)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.9 | 5.8 | 6.6 |
| 4位 あずき(ゆで)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.8 | 11.0 | 11.8 |
| 5位 ささげ(ゆで)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 0.8 | 9.9 | 10.7 |
種実類の食物繊維量ランキング
| 1位 ごま(いり)(g/可食部100g) | ||
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 2.5 | 10.1 | 12.6 |
| 2位 かぼちゃ(いり)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.8 | 5.5 | 7.3 |
| 3位 えごま(乾)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.7 | 19.1 | 20.8 |
| 4位 アーモンド(いり)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.1 | 10.0 | 11.0 |
| 5位 甘ぐり(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| 1.0 | 7.5 | 8.5 |
藻類の食物繊維量ランキング
| 1位 焼きのり(g/可食部100g) | ||
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| ー | ー | 36.0 |
| 2位 あおのり(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| ー | ー | 35.2 |
| 3位 わかめ(乾)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| ー | ー | 32.7 |
| 4位 こんぶ(乾)(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| ー | ー | 27.1 |
| (参考)寒天(g/可食部100g) | ||
| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 総量 |
| ー | ー | 1.5 |
食物繊維の1日の摂取量、摂取方法

上記では食物繊維を多く含む食品をご紹介しましたが、では一体、一日にどのくらいの量を摂取するのが望ましいのでしょうか?
厚生労働省が定める食事摂取基準(2015年版)によると、食物繊維の1日あたりの目標摂取量は18~69歳で男性20g以上、女性18g以上となっています。
しかし、近年の食の欧米化に伴い日本人の食物繊維摂取量は減少傾向にあります。
最近の報告によると、一日あたりの平均摂取量は約14gと推定されるそうです。
「もっと効率的に食物繊維を摂取するにはどうしたらいいの?」
「不足すると健康に悪影響なの?」
そんな不安を解決すべく、以下ではおすすめの摂取方法と不足するとどうなってしまうのか、また食物繊維が足りているかの自己チェックをご紹介していきます。
おすすめ!効率的な摂取方法
一番のおすすめ摂取方法は「主食の白米に玄米や大麦を取り入れること」。
理由は、白米に比べて玄米や大麦に含まれる食物繊維量はなんと6倍~17倍だからです!
それぞれに含まれる食物繊維量を見てみましょう。
100gあたりの食物繊維を比較すると、白米は0.5gですが、玄米は3.0g、大麦(米粒麦)はなんと8.7g。
これだけで違いは一目瞭然ですが、具体的に「お茶碗一杯分のごはん」で考えていきましょう。
お茶碗一杯分のごはんは約150g、炊く前の精米に換算すると約65gになります。
白米約65gに含まれる食物繊維量は0.5g×65g/100g=0.325g。
| 【全て白米の場合】 お茶碗一杯分のごはんに含まれる食物繊維量 |
|
|---|---|
| 白米に含まれる食物繊維量 | 総量 |
| 0.5g×65g/100g≒0.33g | 約0.3g |
つまり「全て白米を使用した場合のお茶碗一杯分のごはんには食物繊維が約0.3g含まれている」ということです。
では、お米の5分の1を大麦に置き換えた場合で計算してみます。
お茶碗一杯分の精米(炊く前)は約65gなので、そのうち52gを白米、13gを大麦にします。
すると白米52gに含まれる食物繊維量は0.5g×52g/100g=0.26g。
また大麦13gに含まれる食物繊維量は8.7g×13g/100g≒1.13g。
合計すると約1.4gになりました。
| 【5分の1を大麦に置き換えた場合】 お茶碗一杯分のごはんに含まれる食物繊維量 |
||
|---|---|---|
| 白米に含まれる食物繊維量 | 大麦に含まれる食物繊維量 | 総量 |
| 0.5g×52g/100g=0.26g | 8.7g×13g/100g≒1.13g | 約1.4g |
全て白米だけのごはんと比較すると1g以上の差が生まれました。
計算では大麦を5分の1で置き換えたましたが、これを3分の1まで置き換えると食物繊維量は約2.1gとなります。
| 【3分の1を大麦に置き換えた場合】 お茶碗一杯分のごはんに含まれる食物繊維量 |
||
|---|---|---|
| 白米に含まれる食物繊維量 | 大麦に含まれる食物繊維量 | 総量 |
| 0.5g×43.4g/100g≒0.22g | 8.7g×21.6g/100g≒1.88g | 約2.1g |
1日に3食摂取すると考えると、なんと女性の場合、これだけで目標量の3割以上の食物繊維を摂取することができてしまうのです。
また、上記で説明したように食物繊維は野菜類・きのこ類・果実類・豆類・藻類などにも多く含まれているため、主菜や副菜で食事の中に上手く取り入れていくとよいでしょう。
食物繊維が不足するとどうなる?

食物繊維が慢性的に不足すると、腸内環境の悪化により便秘を引き起こしやすくなります。
また便秘によって大腸がんのリスクも高まってしまいます。
さらには、生活習慣病の予防効果を持つ食物繊維が不足するとその効果は無くなり、結果として生活習慣病の発症リスクまで高めてしまうのです。
このように食物繊維は、体の健康を考えると欠かすことができません。
とても安全な栄養素で健康効果が得られるのですから、積極的に摂取していきましょう。
食物繊維が足りているかの自己チェック
食物繊維が足りているかの自己チェックをしてみましょう。
基本的に「一日に一回、規則的に排便がある」状態であれば問題ありません。
そのままの食生活を維持することを心掛けるとよいでしょう。
しかし上記の状態に当てはまらない場合は、少し食習慣を見直した方が良いかもしれません。
2つ前の見出し「おすすめ!効率的な摂取方法」で効率的な食物繊維の摂取方法をご紹介しましたので、ぜひお試しください。
ちなみに日本内科学会では、「3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態」を便秘の定義としています。
これに当てはまる方は特に食物繊維を意識して摂取するとよいでしょう。
水溶性食物繊維とともに摂取して便秘解消をより効率的にする方法

最後に、便秘解消にフォーカスしてお話します。
便秘解消には特に水溶性食物繊維の摂取が効果的ですが、それと同時に行うことで、より効率的に便秘解消を促す方法をご紹介します。
十分な水分補給
水分は、便を柔らかくするために必要不可欠です。
水分が不足すると便が硬くなってしまい、排出しにくくなってしまうのです。
便秘の方には1日約2リットルの水分補給が効果的です。
そして特におすすめなのが「起床時、お水を1杯飲むこと」。
水を飲むことで腸を刺激し排便を促す効果が期待できます。
乳酸菌を摂取する

プロバイオティクスという言葉をご存じですか?
プロバイオティクスとは、人体に良い影響を与える微生物のことです。
そしてその代表が「乳酸菌」。
乳酸菌には腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランス状態を良好に保つ作用があり、便秘改善に非常に効果的です。
乳酸菌と、そのエサになる食物繊維を同時に摂取することでより便秘解消の効果が期待できるでしょう。
乳酸菌の種類と効果
私たちの体を守ってくれる免疫機能が集中している「腸」。
整腸作用の他にも、乳酸菌にはさまざまな効果を発揮することがわかってきました。
今回は、乳酸菌に期待できる効果について詳しく紹介していきます。
乳酸菌の種類と効果の記事を見る
乳酸菌の上手な摂取法とは?「大腸の専門医」後藤利夫先生に聞きました。
腸内環境が悪化するとどんな悪影響があるのか、改善するにはどうしたらいいか。
普段見ることが出来ない自分のお腹の中でどんなことが起こっているのか?
乳酸菌サプリの効果なども詳しく解説していきます!
「大腸の専門医」後藤利夫先生についての記事を見る
適度な運動
みなさんご存じの通り、運動不足は便秘を促進させる一つの要因です。
適度な運動は腸に刺激を与え蠕動運動を促進させてくれますし、心のリフレッシュにも繋がります。
運動が苦手な方は、ウォーキングやストレッチから始めてもいいので、日常に軽度な運動を取り入れるとよいでしょう。
また運動をした際には水分補給を忘れずに。
水溶性食物繊維に関するQ&A
- 水溶性食物繊維って何ですか?
- 食物繊維の1種です。食物繊維には水に溶ける水溶性食物繊維と水に溶けにくい不溶性食物繊維の2種類があります。
水溶性食物繊維は便秘解消や肥満の予防、生活習慣病予防など多くの健康効果が期待できる栄養素です。
- 水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の違いを教えてください。
- 水に溶けるのが水溶性食物繊維、水に溶けにくいのが不溶性食物繊維です。
どちらも食物繊維であることは同じです。お互いに似たような特性を持っていますが、特に異なる特性としては次の通りです。<水溶性食物繊維:余分な糖や脂質を吸着し体の外に排泄する。><不溶性食物繊維:繊維状であるため噛む回数が増え、歯や顎の発育を支える。>
- 食物繊維の1日の摂取量はどのくらいがいいですか?
- 厚生労働省が定める食事摂取基準(2015年版)によると、食物繊維の1日あたりの目標摂取量は18~69歳で男性20g以上、女性18g以上となっています。
しかし日本人の一日あたりの平均摂取量は約14gと推定されているため、積極的に摂取していくとよいでしょう。
- 食物繊維を効率的に摂取する方法はありますか?
- おすすめの摂取方法は主食の白米に玄米や大麦を取り入れる方法です
。例えば白米の3分の1を大麦に置き換えることで、女性なら1日の目標量の3割以上を摂取することができます。
(1日3食:お茶碗1杯で換算)
- 食物繊維が多く含まれている食品を教えてください。
- 食物繊維は野菜類、穀類、きのこ類、果実類、豆類、種実類、藻類に多く含まれています。
逆に動物性の魚介類や肉類などの食品にはほとんど含まれていません。
詳しくは見出し「食物繊維含有量の多い野菜・食品」をご覧ください。






 もくじ
もくじ