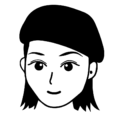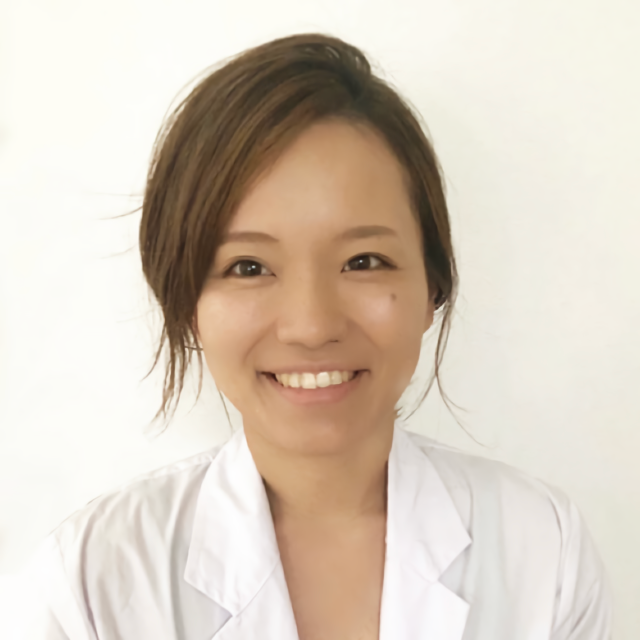あんこの失敗しない作り方|つぶあん&こしあんレシピ
記事の監修
管理栄養士
川野 恵
フリーランスの管理栄養士としてレシピ開発や栄養のコラム作成のほか、外食チェーン店でのダイエットを意識した食べ方を紹介。現在はクリニックにて、生活習慣病などに悩む方々へ栄養指導を行なっている。

和菓子には欠かせないあんこ。
この記事では、簡単に作れるあんこのレシピをご紹介します。
また、あんこがもたらす健康効果についても詳しく紹介。
あんこを使った人気のレシピも提案します。
手作りあんこで、美味しい和スイーツを楽しみましょう。
※当レシピはかわしま屋が和菓子製造者のアドバイスのもとにまとめたものです。
作り方の一例としてご覧ください。

つぶあん
材料
- 小豆 200 g
- 砂糖 200 g
- 水(砂糖を煮溶かす用) 70 ml
作り方
- 小豆をたっぷりのお水でやさしく洗います。

- 小豆にたっぷりの水を加えて中火で煮ます。小豆は水を吸うと2.4倍ほどに膨れるので大きめの鍋を使用しましょう。小豆は浸水は必要なくそのまま炊き始められます。

- 沸騰したら火を止め、蓋をして20分ほど放置して蒸らします。

- 蒸らし終えたら煮汁を捨てます。ここまでの工程を渋切りと呼びます。

- 渋切りをした小豆と水を入れて煮ます。ここでの水の量は小豆が水にひたるぐらいです。

- 鍋を中火にかけ、沸いたらアクをすくい取ります。お湯の中で豆が踊るとつぶれてしまうので、踊らないように火加減に気を付けます。煮ている最中、小豆が湯から出ないように時々さし水をします。

- 40~50分煮て一度豆の煮具合を確かめます。指で豆をつぶし、軽い力でつぶれる状態が良い煮具合です。小豆の品種などによって1時間以上かかることもあり、大きさによって煮えムラも出てくるので、いくつかの豆をみて煮えている状態になったら火から外します

- 蓋をしたまま30分蒸らします(この蒸らしで煮えムラをなくします)。

- 鍋に水70mlを入れ、弱火にかけて砂糖を溶かします。 完全に溶かす必要はありません。
- 砂糖を溶かした鍋に小豆を入れて強火にかけます。豆をつぶさず焦がさないよう、なべ底から手早く混ぜます。仕上がり直前に塩をひとつまみ程度入れると味がひきしまります。

- あんは冷めると少し硬くなるので、好みのかたさよりやや柔らかめくらいに練りあがったら、速やかに別容器に移し変えて冷まします。鍋のまま放置すると砂糖が熱によって変質し、後味がくどくなってしまいます。
- 美味しいつぶあんの完成です。

動画

こしあん
作り方
- 小豆をたっぷりのお水でやさしく洗います。

- 小豆にたっぷりの水を加えて中火で煮ます。小豆は水を吸うと2.4倍ほどに膨れるので大きめの鍋を使用しましょう。小豆は浸水は必要なくそのまま炊き始められます。

- 沸騰したら火を止め、蓋をして20分ほど放置して蒸らします。

- 蒸らし終えたら煮汁を捨てます。ここまでの工程を渋切りと呼びます。

- 渋切りをした小豆と水を入れて煮ます。ここでの水の量は豆の4~5倍ほどです。

- 鍋を中火にかけ、沸いたらアクをすくい取ります。煮ている最中、小豆が湯から出ないように時々さし水をします。

- 40~50分煮て一度豆の煮具合を確かめます。指で豆をつぶし、軽い力でつぶれる状態が良い煮具合です。小豆の品種などによって1時間以上かかることもあり、大きさによって煮えムラも出てくるので、いくつかの豆をみて煮えている状態になったら火から外します。

- 蓋をしたまま30分蒸らします(この蒸らしで煮えムラをなくします)。

- ボウルにザルをのせて小豆をあげます。

- お玉の裏やへらなどで小豆をつぶすように漉します。

- 水を加えて皮と中身を分けます。このあと豆の皮は使いません。

- 別のボウルに目の細かい漉し器をのせ、1回目で漉した液を流し入れて薄皮などを取り除きます。

- 途中で水を加えながらゴムベラで漉します。残った薄皮などは捨てます。

- 水を加えて混ぜたら15分ほど置き、あんが沈んだら上ずみを捨てます。合計2回行います

- 布きんをザルの内側に広げてあんを入れます。

- 汁気を搾り、中身をボウルに開けます。

- 生あんの出来上がりです。

- 鍋に砂糖と水100ccを入れ中火にかけ砂糖を溶かします。

- 火を止め生あんを全量入れます。

- ゴムベラで混ぜてほぐします。強火にかけ鍋底にヘラを当てるようにして混ぜ続けます。ぼってりとした固さになれば火を止めて塩を加えなじむまで混ぜます。

- バットに広げて冷ませば、こしあんの完成です。(あんは冷ますと少し固くなります。)

動画
つぶあんからこしあんを作る方法

こしあんは、つぶあんをミキサーにかけるだけで簡単に作れます。
つぶあんを滑らかになるまでミキサーにかけてこしあんにするので、含まれている栄養素は変わりません。
皮をこした場合よりも食物繊維・サポニン・ポリフェノールなどが摂れるので「小豆の栄養素をしっかりと補いたい」というこしあん好きさんに、とてもおすすめの作り方です。
ミキサーではなくブレンダーを使っても、美味しく作れますよ。
アレンジあんこレシピ

デーツで作るあんこ
材料
- 茹で小豆 200 g
- デーツ 100 g
- 水 100 cc
作り方
- デーツの種を外してたら実をを細かく切ります。
- 鍋に水とデーツを入れて中火にかけ煮ます。
- デーツが柔らかくなったら茹で小豆を加えて煮ます。
- ヘラで混ぜながら煮てください。
- 好みの柔らかさになったら火を止めて完成です。
あんこを食べる適量は?

小豆には多くの栄養素が含まれていますが、あんこは砂糖もたくさん使用しているので食べすぎには要注意です。
糖質が多くなるので小豆だけの場合と比べると血糖値が上がりやすくなります。
そこで、あんこを食べるおすすめの適量は、カレースプーン1杯分くらい。
これくらいであれば、100kcal前後・糖質20~30gとなり、健康に大きく影響を与えることは少なくなります。
トーストに塗ったり、ヨーグルトにかけたり、普段の食事にチョイ足しすれば食べ過ぎも防ぎやすくなります。
あんこの作り方についてのQ&A
- あんこを作るときに小豆は一晩水につけなくても大丈夫ですか?
-
あんこを作る際は小豆を浸水させなくても大丈夫です。ただし、渋抜きのために、煮る前に小豆とひたひたの水を鍋に入れ強火にかけ、て沸騰したら一度ざるにあげましょう。
- あんこはの砂糖をパルスイートなどの甘味料に置き換えても作れますか?
-
あんこは砂糖の代わりに甘味料を使っても作れます。糖質を制限したい方はぜひお試しください。
- あんこの保存方法は?
-
あんこを保存するときは、粗熱をとり、小分けにして冷蔵庫や冷凍庫に入れてください。
冷凍庫では約2~3か月間保存可能です。
- あんこを食べると血糖値が上がりますか?
-
あんこを食べると血糖値が上がる可能性があります。市販のあんこは砂糖が多く使われているため、糖質量が多いです。糖質の摂り過ぎは血糖値を急激に高めることがあります。そのため、あんこを食べる場合でも低糖質なあんこを選ぶことで、血糖値の上昇を抑えることができるでしょう。砂糖を使わずに麹を使って作る発酵あんこもいいですね。
- あんこをたくさん食べたら太りますか?
-
砂糖を多く使用している市販のあんこの場合、食べ過ぎると太る可能性があります。大福などは餅の糖質もあるため、とても高カロリーなので気をつけましょう。
管理栄養士からのコメント
老若男女問わずに好かれるあんこには、栄養がたくさん詰まっています。
ミネラルやビタミンB群、食物繊維など、身体の調子を整えるのに欠かせないものばかりです。
ただ、小豆の栄養以外にも、既製品のあんこの中には砂糖の糖質もたっぷり入っているのが気になるところ。
せっかくだったら、小豆の栄養と美味しさを罪悪感なく楽しみたいですよね。
今回紹介したレシピを参考にしながら好みで砂糖の量を調整すれば、ヘルシーな自分だけのあんこを作ることができます。
また、小豆を茹でた汁にも栄養素が溶けだしているので、捨てずに使うようにしましょう。
茹で汁と少しのお塩を一緒にご飯を炊いてみると、美味ですよ。
管理栄養士プロフィール
川野 恵
給食委託会社や仕出し弁当屋での献立作成を経験後、出産を機にフリーランスとして活動。
フリーランスの管理栄養士としてレシピ開発や栄養のコラム作成のほか、外食チェーン店でのダイエットを意識した食べ方を紹介。現在はクリニックにて、生活習慣病などに悩む方々へ栄養指導を行なっている。
身体は食べ物でできている事を意識し、健康で過ごせるよう多くの方を支えていける管理栄養士になりたいと日々活動しています。
SNSやブログを通して、
・管理栄養士として栄養指導に携わりたい!
・血圧や血糖など血液結果を注意された!
・美味しく食べてきれいに痩せたい!
という悩みを解決するための情報を発信しています。