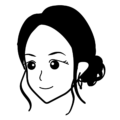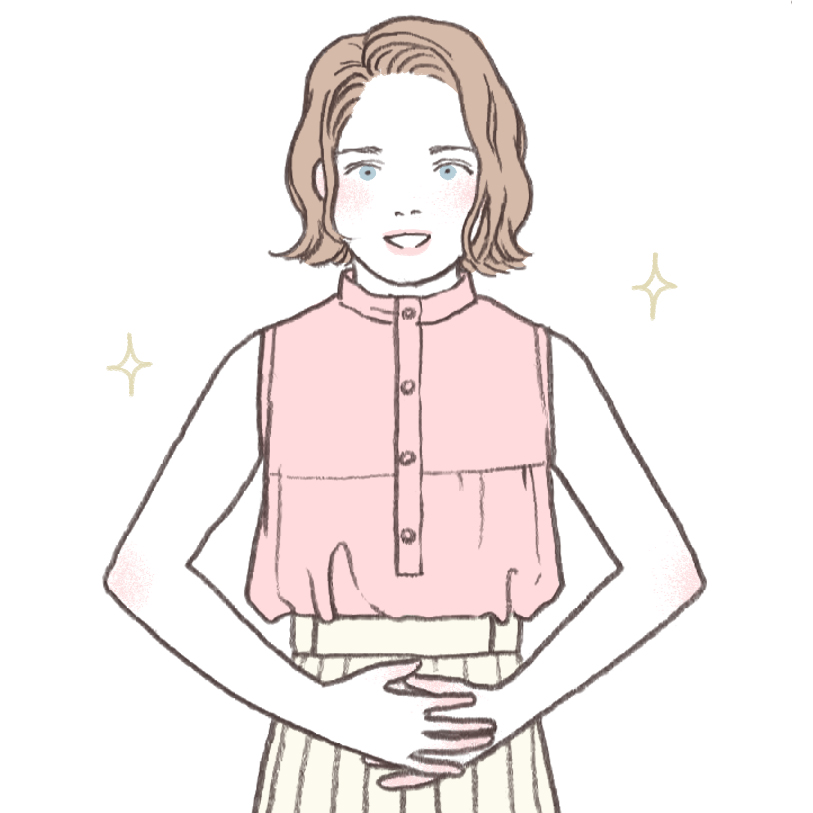にごり酢とは?注目の効果効能と飲み方・使い方
「にごり酢」をご存じですか?

血糖値の抑制や抗菌作用、ダイエット効果など多くの効果で知られ、健康を気にする方々の間でもブームになってきた酢。
市販の酢は透明なものが一般的ですが、ここ数年では「にごり」のある酢が話題です。
「にごり」の元になっているのは「酢酸菌」といい「にごり酢」には多くの酢酸菌が含まれます。この酢酸菌がもつ免疫機能を改善する効果に注目があつまっています。
この記事では、「にごり酢」の特徴や健康面での効果効能、レシピなど、日々の生活のなかで免疫力アップに向けて活用できるポイントを紹介します。
にごり酢ってどんな酢?

一般的な酢の大部分は、製造・商品化する際にろ過・加熱殺菌をしているため「にごり」がなく透明です。スーパーに並んでいる酢を選んでも、酢酸菌は摂れないということになります。
一方にごり酢は、原材料になる穀物や果実などを無添加で自然にアルコール発酵させ、それが更に時間をかけて酢酸菌により酢酸発酵したものを、最終の段階でろ過や加熱殺菌をせずに仕上げたものです。 そのため、にごり酢には原材料に由来する酵素やミネラル、そして酢酸菌を多く含んでいます。
にごりの正体、酢酸菌とは?
アルコールから酢を作る細菌(微生物)の総称であり、乳酸菌や納豆菌と同じ、食用の発酵菌の仲間です。 酢酸菌は空気中や果物、花など自然界のさまざまな場所に存在していて、酢を作るプロセスであらわれる表面の膜にたくさん含まれています。
酢を作るのために必要不可欠で、英語では「Mother of vinegar(お酢の母)」とも呼ばれています。


にごり酢の種類と見分け方
一番親しみのあると言えば、米を原料にした米酢ではありませんか? 近年では果物を使ったリンゴ酢や柿酢、トマト酢や玉ねぎ酢など、様々なお酢が注目されています。
これらの酢も、製造の工程で発酵を行っており「ろ過」しておらず酢酸菌が入った状態であれば「にごり酢」のひとつとなります。
バルサミコ酢や黒酢など、昔ながらの製法で発酵や熟成に時間をかけている酢にも、酢酸菌の細胞成分が少量含まれています。 またパッケージなどに「無濾過」や「にごり酢」といった記載がされているかもポイントです。
酢酸がたっぷり入ったおすすめのリンゴ酢

イタリア産 有機にごり リンゴ酢 1000g(1000ml)| 無添加・無ろ過・発酵助剤不使用のアップルサイダービネガー -かわしま屋-_t1
リンゴ作りに最適な気候で名高いイタリア最北のトレンティーノ地方で有機栽培された最高品質のリンゴのみを用いて発酵させた、ほのかな甘みとまろやかな深みが理想的です。添加物を一切加えていない、本物のリンゴ酢をお楽しみください。
1000 円(税抜)
注目の「にごり酢」の効果
酢酸菌がそのまま含まれているにごり酢。 この「酢酸菌」がおよぼす免疫をサポートする働きによって、アレルギーや花粉症の症状がやわらぐこと、飲酒時の肝機能をサポートすることなどの効果が明らかになってきました。
効果1 免疫力をサポート
にごり酢で免疫力アップ
酢酸菌は体の免疫機能の働きを助けアレルギー反応を和らげる作用があります。
次のような症状がやわらぐことが確認されています。
・花粉による鼻のかゆみ
・ハウスダストによる鼻の違和感
・ダニによる皮膚の違和感
参考: Oral Administration of Lipopolysaccharide of Acetic Acid Bacteria Protects Pollen Allergy in a Murine Model / 酢酸菌(Gluconacetobacter hansenii GK—1)は健常者の鼻の不快感を軽減する―無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験
効果2 飲酒時のアルコール濃度の低減
にごり酢で肝臓の代謝をサポート
普段からお酒を飲んでいる成人男性を対象とした試験で、酢酸菌酵素を摂取すると、しない場合と比べて体内の血中アルコール濃度が有意に低下したというデータが存在します。
酢酸菌が酵素によってアルコールを分解するプロセスは、私たちの肝臓で行なわれるアルコール代謝のプロセスと同じ。酢酸菌酵素を摂取することで、肝臓の負担を和らげる効果が期待できそうです。
効果3 飲酒時の肝機能をサポート
にごり酢酢で肝臓機能をサポート
効果2と関連して、酢酸菌酵素を継続的に摂取したマウスは、飲酒時の肝機能の悪化や肝臓への脂肪蓄積が軽減されたというデータが出ています。
メカニズムとしては、本来すべて肝臓で行われるはずだったアルコール代謝が、酢酸菌酵素を摂取することで胃や小腸でも行なわれるようになり、結果として肝機能の悪化が軽減されます。
なお、酢酸菌の効果をできるだけ得るためのポイントは、食事と一緒に摂り入れることです。なぜなら、胃の中に食べ物や油分があることで酢酸菌とアルコールとが触れ合う時間が長くなるからです。
「にごり酢」を手軽に飲みたい方におすすめのリンゴ酢
にごり酢を使ったレシピ
はじめに、にごり酢をそのまま割って飲む方法をご紹介します。毎日の免疫力アップの健康習慣やアレルギー対策として是非お試しください。レシピは、りんご酢だけでなく、どんなにごり酢でも作れます。

リンゴ酢サワー
材料
- リンゴ酢 大さじ 1
- 水や炭酸水、豆乳など 150 ㏄
作り方
- リンゴ酢をコップに入れ、水で5~8倍に薄めればできあがりです。
動画
コツ・ポイント
次に、お湯割りのレシピです。柿酢などの果実酢なら蜂蜜を加えホットドリンク風、トマト酢や玉ねぎ酢なら塩を足して食前スープのようにいただくのもオススメです。

柿酢とはちみつのあったかドリンク
材料
- 柿酢 大さじ 1
- はちみつ 大さじ 1
- 熱湯 150 ml
作り方
- グラスに柿酢とはちみつを入れます。
- そこに、熱湯を注いでよく混ぜます。
動画
次に、にごり酢を使った料理のレシピを4つ紹介します。にごり酢はさまざまな食材とも相性は抜群なので、メイン料理や副菜など、お好みの具材に替えればバリエーションをお楽しみいただけます。

酢キャベツ
材料
- キャベツ 400 g
- 塩 小さじ 1
- 酢 400 cc
作り方
- キャベツを千切りにします。

- 切ったキャベツをボウルに入れ、塩をまぶして軽く塩もみをし10分ほど置きます。

- 10分たったら、キャベツを保存容器に移します。

- キャベツを入れた容器に、キャベツが漬かるまで酢を注ぎ入れます。

- 蓋をして半日ほど置いたらできあがりです。

動画
コツ・ポイント
カロリーは低いのに食べ応えはあるのでダイエットにぴったりの一品です。 常備菜としてはもちろん、しっかり水分を切ればお弁当に入れられる、いつでも手軽に食べやすい副菜です。
ダイエットや日々の野菜不足解消にも役立つので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。 【監修:管理栄養士 安藤 ゆりえ】

きゅうりとわかめの酢の物
材料
- きゅうり 1 本
- 乾燥ワカメ 3 g
- 塩 ひとつまみ
- <三杯酢>穀物酢 大さじ 2
- <三杯酢>しょうゆ 大さじ 2
- <三杯酢>みりん 大さじ 2
作り方
- 乾燥わかめを水でもどします。
- きゅうりを薄い輪切りにし、ボウルに入れます。
- 塩ひとつまみを入れて軽く混ぜ、5分おきます。
- 三杯酢を作ります。
- みりんを耐熱ボールに入れて電子レンジで1分加熱します。
- 穀物酢、しょうゆ、加熱したみりんをボウルに入れてしっかりと混ぜます。
- きゅうりがしんなりしたら水気を切ります。
- もどしたわかめの水も切ります。
- きゅうり、わかめ、三杯酢を合わせてできあがりです。
動画

酢飯
材料
- 米 3 合
- 水 500 cc
- 昆布 1 枚
- 酒 大さじ 3
- <すし酢>酢 大さじ 6
- <すし酢>砂糖 大さじ 3
- <すし酢>塩 小さじ 2
作り方
- 米をといでざるに上げて、30分おいておきます。
- 米、水、昆布、酒を入れて炊きます。 いつものご飯よりかために炊き上げる分量です。
- ご飯を炊いている間にすし酢を作ります。
- 飯台をしめらせておきます。
- ご飯が炊けたら昆布を取り出します。
- ご飯を飯台に移し入れ、さっと広げます。
- 合わせたすし酢をご飯全体に回しかけます。
- しゃもじで切るように手早くご飯を混ぜます。うちわであおぎながら混ぜるとご飯がつやよく仕上がります。
動画

揚げない酢鶏
材料
- 鶏肉(モモ、むね肉でも可) 200 g
- ◎しょう油 大さじ 1
- ◎酒 小さじ 1
- ◎ごま油 小さじ 1
- 片栗粉 大さじ 2
- ピーマン 2 個
- 玉ねぎ 1/2 個
- にんじん 1/2 本
- ★にごり酢 大さじ 3
- ★しょうゆ 大さじ 3
- ★砂糖 大さじ 3
- ★ケチャップ 大さじ 2
- ★酒 大さじ 2
- ★水 大さじ 4
- ★片栗粉 大さじ 1
- オリーブオイル 大さじ 1
作り方
- 鶏肉はひと口大に切り、器に鶏肉と◎を入れて馴染ませ10分ほどやすませる。
- 野菜はひと口大にカットします。にんじんは耐熱容器に入れ600wのレンジで5分加熱しておく。
- ボウルに★を入れて混ぜておく。
- 保存袋に1と片栗粉を入れて全体にまぶす。
- フライパンを熱し、オリーブオイルをひく。
- 中火で鶏肉を火が通るまで炒める。全ての野菜を加えて更に炒める。
- 合わせておいた★を5に入れて全体になじむように炒めたら火を止める。
- お皿に盛りつけたら完成。
レシピに使ったお酢はこちら
にごり酢についてのQ&A
- にごり酢と一般的なお酢の違いは?
-
一般的な透明のお酢は、品質保持・見た目の美しさのためにろ過と加熱殺菌で酢酸菌が除去されてしまっています。それに比べて「にごり酢」は、自然に発酵されたお酢をろ過せずに仕上げ、加熱殺菌もしないため、生きた酢酸菌や酵素・ミネラルがたっぷり含まれています。
- にごり酢を使うメリットは?
-
にごり酢には、酵素やミネラルに加えて、力強いパワーを秘めたお酢そのものの源である酢酸菌がたっぷり含まれています。この酢酸菌は免疫力アップやアレルギー対策の分野で注目されており、一般的なお酢よりも高い健康効果が期待できるといえます。
- 酢を使う料理を毎日食べても体に害はありませんか?
-
酢は一度に食べる量が多いと胃や腸に負担がかかりますが、適量を毎日とる分には心配はいりません。ただし、胃のことで病院にかかっている方などであれば、必ず主治医に相談するようにしてください。
- お酢の酸味が苦手です。食べやすいレシピはありますか?
-
しょうが焼きなどでお肉の下味に酢を使ってみるのはいかがでしょうか。下味にしたり酢に火を通したりすることで酸味がやわらぎ、酸っぱさが苦手な方でもが食べやすくなります。
- 1日にどれくらいの量の酢をとればよいのですか?
-
摂取の適量は、1日ではにごり酢大さじ1~2・15㏄〜30㏄が目安です。 にごり酢に限らず酢は原液では刺激が強いので、必ず飲み物に混ぜたり、料理などと一緒にお召し上がりください。
- お酢をとるタイミングはいつが良いのでしょうか?
-
いつでも問題ありませんが、おすすめは寝る前です。身体や脳は、睡眠中に疲れを癒して状態を回復するため、就寝前に酢を摂取するとその働きをサポートしてくれます。

かわしま屋おすすめのにごり酢
かわしま屋では種類豊富ににごり酢を取り揃えています。ぜひお気に入りの味を探してみてください。

イタリア産 有機にごり リンゴ酢 1000g(1000ml)| 無添加・無ろ過・発酵助剤不使用のアップルサイダービネガー -かわしま屋-_t1
リンゴ作りに最適な気候で名高いイタリア最北のトレンティーノ地方で有機栽培された最高品質のリンゴのみを用いて発酵させた、ほのかな甘みとまろやかな深みが理想的です。添加物を一切加えていない、本物のリンゴ酢をお楽しみください。
1000 円(税抜)

国産純リンゴ酢無濾過にごり酢・180日間静置発酵 (長野県産リンゴ100%)-1000ml-かわしま屋-
生きた酢酸菌が入っている、国産のりんご酢です。生のりんごを使用したりんご酢で、180日間静置発酵させています。
2180 円(税抜)

【2週間お試しサイズ】有機ミック酢 200g|6種のイタリア産無濾過にごり果実酢ブレンド -かわしま屋-_t1
1日15ml目安で約2週間分のお試しサイズです。イタリア産の有機・無濾過のフルーツビネガー6種類をブレンド。酢酸菌が生きている希釈タイプのお酢ドリンクの、気軽にお試し頂けるミニサイズです。砂糖・香料・保存料不使用、100%お酢のみなので安心して飲んでいただけます。
463 円(税抜)

イタリア・モデナ産 飲む有機バルサミコ酢 790ml(900g)| 有機ぶどうのみを原材料に、無添加で8年の長期熟成 -かわしま屋-_t1
イタリア・モデナ地方で有機農法で栽培された最高級ブドウのみを使ったバルサミコ酢です。8年間熟成されており、まるでワインの様な豊潤で濃厚な香りが特徴。カラメル色素や香料などは一切加えていない、本物のバルサミコ酢をお楽しみください。
1167 円(税抜)