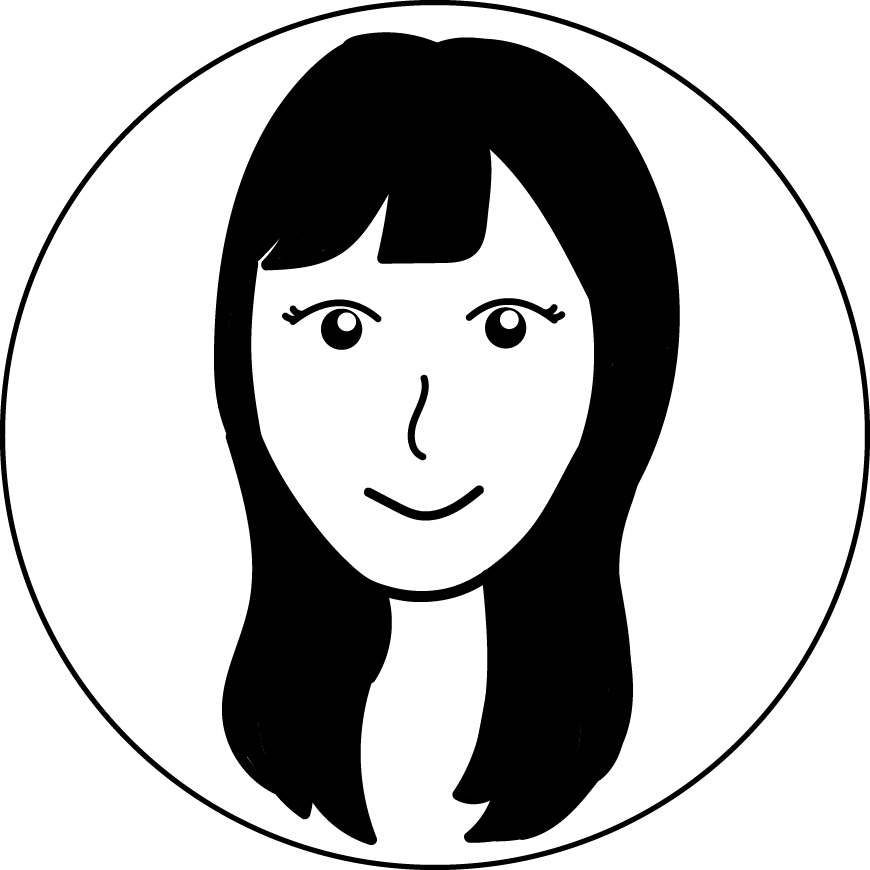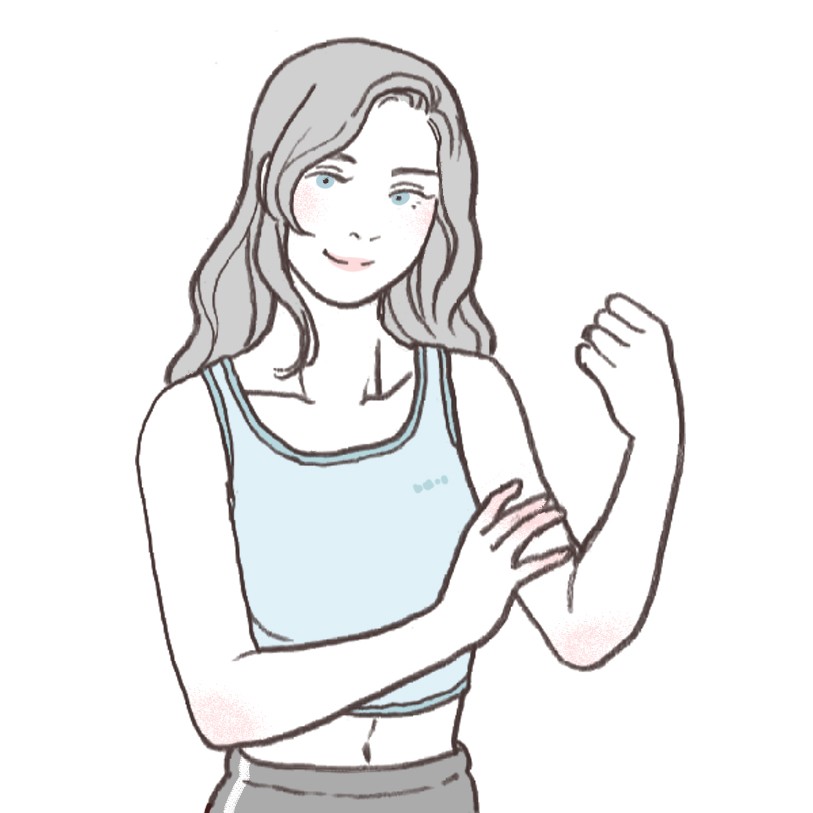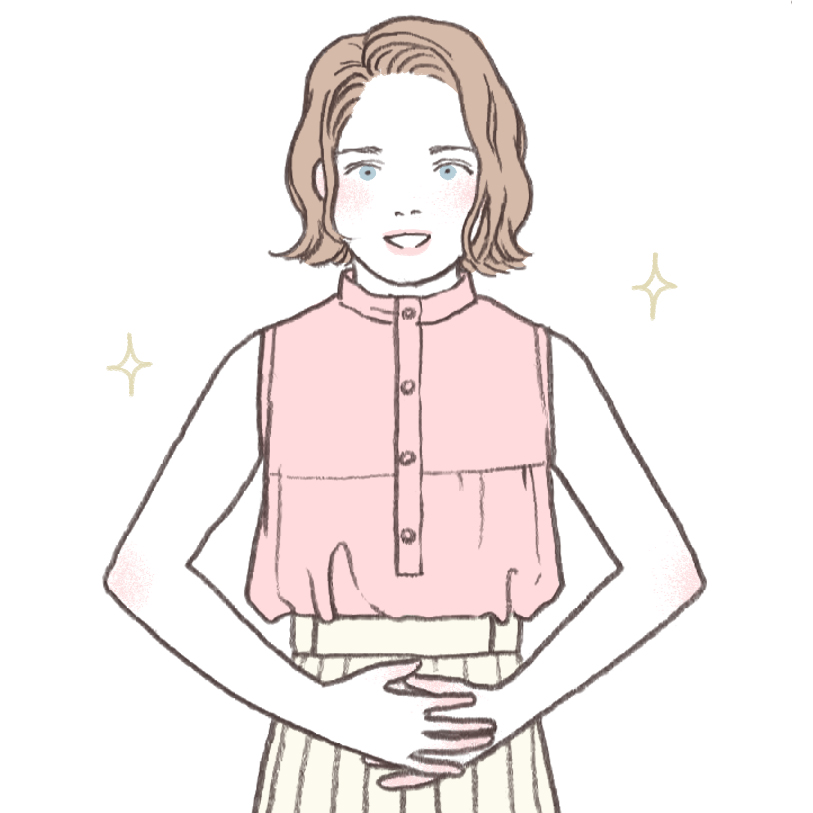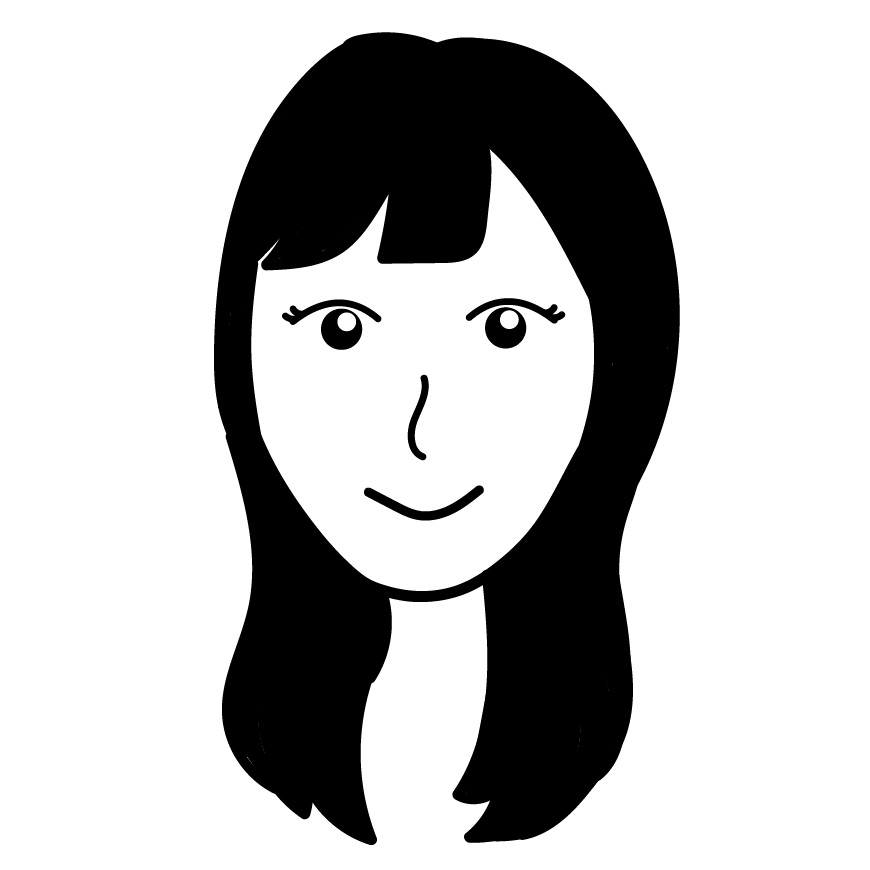オリーブオイルの成分と効果|ダイエットや便秘にメリットはある?

オリーブオイルには健康に良いイメージがありますが、具体的な効果はよく知らないという人も多いのではないでしょうか。あるいは、欧米のデータを元にした謳い文句に懐疑的な人もいるでしょう。
そこで本記事では、オリーブオイルの成分構成から具体的な効果まで詳しく解説します。また、欧米人のデータを元にしたメリットが日本人にも当てはまるかどうかも、合わせて解説していきます。
記事の監修
管理栄養士
鶴田 ようこ
調理師・管理栄養士。2つの資格を生かし食用油脂製造会社にて品質管理に従事。菜種油、オリーブ油の品質に関する分析、衛生管理等を行う。幼い頃から野菜作りの手伝いをしていたことから、季節の野菜料理が得意。
オリーブオイルの成分構成

栄養成分と脂質の構成を紹介します。後述する「オリーブオイルの効果」でも登場するキーワードがあるので、ぜひご覧ください。
日本食品標準成分表における成分構成
オリーブオイルには次のような成分が含まれています。
| 成分名 | 量(100gあたり) |
|---|---|
| β-カロテン(ビタミンA) | 180μg |
| α|トコフェロール(ビタミンE) | 7.4mg |
| β|トコフェロール(ビタミンE) | 0.2mg |
| γ|トコフェロール(ビタミンE) | 1.2mg |
| δ|トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg |
| ビタミンK | 42μg |
| 脂質 | 98.9g |
| 炭水化物 | 1.1g |
日本食品標準成分表2020年版(八訂)
脂質が大半ですが、オリーブオイルにはビタミンA・ビタミンE・ビタミンKが含まれています。ビタミンEはその他の油にも多く含まれていますが、β-カロテンが多いのはオリーブオイルならではの特徴です。
β-カロテンは体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜の維持に貢献する栄養成分です。ニンジンが多く含むことでも知られています。
オリーブオイルの脂肪酸の構成
オリーブオイルの脂肪酸の構成を、日本でよく使われる菜種油と比較してみましょう。
| 脂肪酸の種類 | オリーブオイル | 菜種油(ローエルシック) |
|---|---|---|
| オレイン酸 | 77.8% | 64.1% |
| リノール酸 | 6.5% | 19.0% |
| リノレン酸 | 0.7% | 8.5% |
| パルチミン酸 | 9.9% | 4.1% |
| パルミトレイン酸 | 0.6% | 0.2% |
| ステアリン酸 | 3.3% | 1.8% |
| アラキジン酸 | 0.4% | 0.6% |
| エイコセン酸 | 0.3% | 1.1% |
| ベヘン酸 | 0.1% | 0.3% |
| リグノセリン酸 | 0.0% | 0.1% |
| その他脂肪酸 | 0.4% | 0.1% |
菜種油と比べると、オレイン酸の割合が高いことがわかります。オレイン酸は酸化しにくく、血中LDLコレステロールが上がりにくいといわれている油です。詳しくは「オリーブオイルの効果」で紹介します。
オリーブオイルの5つの効果
オリーブオイルの成分に着目した効果を5つに分けて解説します。オリーブオイルを日常に取り入れるかどうか迷っているときの参考にしてください。
肌にうれしい効果
ビタミンEは抗酸化力の強い栄養成分で、細胞壁・生体膜の健康維持に役立ちます。皮膚の健康維持にも役立つということです。
また、ビタミンAにも皮膚や粘膜の健康を保つ効果があります。
なお、オリーブオイルには保湿作用があるため、肌に塗布するケアが紹介されることがあります。しかし、肌用に精製されていない食用オイルを塗布するのは避けるのが無難です。
ダイエットサポート
オリーブオイルの主成分であるオレイン酸には、脂肪の代謝(燃焼)を促す効果が期待されています。
ビタミンEにも代謝を高めてエネルギーを消費しやすい体を作るはたらきがあるため、ダイエットサポートに効果的です。
また、満腹感をもたらして食欲を抑制する効果もあります。食後血糖値の急上昇を防ぐことで、空腹感をもたらすインスリンの過剰分泌を抑えるメカニズムです。食べ過ぎによるカロリーオーバーも避けやすくなります。

腸内環境の改善
オレイン酸には腸を刺激し、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を活発にするはたらきがあります。
また、オリーブオイルの油分が腸内の潤滑油となり、便の詰まりを解消する効果も期待できます。
便が腸内に長く留まると腐敗によって有毒ガスや毒素がうみだされ、腸内環境が悪化します。適切な排便によって腸内環境を改善しましょう。

血液・血管の健康維持
オレイン酸とビタミンEには血中LDLコレステロールの減少や酸化抑制効果があります。
LDLコレステロールには良いはたらきもありますが、多すぎると動脈硬化の一因となるため、注意が必要です。デメリット面が注目され、悪玉コレステロールとも呼ばれています。
また、ビタミンEには細胞壁の健康維持効果や赤血球の破壊防止効果もあります。血管や血液の健康維持に有用です。
口臭・風邪予防
オリーブオイルで口をゆすぐと、コーティング効果によって菌の増殖を防ぎ、口臭予防が期待できるといわれています。
また、保湿力があるため、口腔内や喉の乾き防止にも有用です。乾燥が続くと風邪にもつながるので、予防としてとりいれてみましょう。
【注意】日本人は欧米人ほどの効果がない可能性

オリーブオイルのメリットとしては、ダイエットに良い、心疾患のリスクを低減するなどの効果が挙げられます。しかし、日本人では劇的な効果を期待できません。
ダイエットや心疾患のリスク低減に効果があったとされるデータは、欧米人を調査したものです。とくにアメリカ人の食生活では、飽和脂肪酸の含有量が多いバター・牛脂・ラードなどの動物性油脂が中心なので、オリーブオイルに切り替えると効果が高くあらわれます。
一方、日本の食生活では、不飽和脂肪酸が多い菜種油やごま油が中心で、飽和脂肪酸の摂取量は多くありません。つまり、オリーブオイルに切り替えても欧米人ほどの変化は生じないということです。
日本人にとってのオリーブオイルの効果を考えるときは、オリーブオイルがもつ成分に注目することが大切です。また、摂取量を考慮する必要があります。
オリーブオイルの摂取量の目安

オリーブオイルには健康にうれしい効果がさまざまありますが、カロリーも高いため摂取量には注意が必要です。ここで、代表的な油とカロリーを比較してみましょう。
| 品目 | 100gあたりのカロリー(kcal) |
|---|---|
| オリーブオイル | 894 |
| ごま油 | 890 |
| なたね油 | 887 |
| 大豆油 | 885 |
| バター(無発酵・有塩) | 700 |
| 牛脂 | 869 |
表からもわかるように、オリーブオイルはカロリーの高い油です。摂取しすぎるとカロリーオーバーになる可能性があります。1日の食事全体のカロリーにもよりますが、1日あたりの摂取量の目安は大さじ1杯までがおすすめです。
大さじ1杯あたりのオリーブオイルの量は12〜14g、カロリーは107〜125kcalです。120kcalを消費しようとすると、体重55kgの人が40分程度、通常速度でウォーキングした場合の運動量に相当します。
ただし、総摂取カロリーを意識して調整すれば、大さじ1杯以上の摂取も可能です。オリーブオイルを取り入れるときは、毎日の食事にプラスするだけでなく、1日の食事全体のカロリーを考慮しましょう。
その他のデメリットも気になる人は、次の記事をご覧ください。
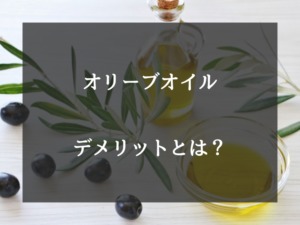
オリーブオイルの効果的な取り入れ方

オリーブオイルに含まれる抗酸化物質の中には、熱で破壊されるものもあります。健康への効果を意識するなら、加熱せずに取り入れることを心掛けましょう。次のような使い方ができます。
- ヨーグルト・塩と混ぜてドレッシングに
- 酢と混ぜてドレッシングに
- トマトジュースに
- 野菜と和えてサラダに
食物繊維たっぷりの野菜と一緒に摂ることは、腸内環境の改善に有用です。
さらに腸内環境の改善に役立てたい人は、乳酸菌の摂取につながるヨーグルトと一緒に食べてみましょう。ヨーグルト・塩・すりおろしニンニク・胡椒・オリーブオイルを混ぜて作る、トルコ風ヨーグルトソースは、サラダだけでなく肉料理や揚げ物とも合います。
オリーブオイルのレシピをさらに知りたい人は、次の記事をご覧ください。

オリーブオイルを食生活に取り入れてみよう

植物油に親しみのある日本人にとって、オリーブオイルは食生活にとりいれやすい油です。カロリーは高いため摂取量に注意は必要ですが、オレイン酸やビタミンEの摂取に役立ちます。
ビタミンEの含有量が多いナッツなどを食べる機会が少ない人は、積極的に取り入れてみましょう。肌や血管の健康維持に役立ちます。また、1日のトータルカロリーを考慮すれば、ダイエットサポートにも有用です。
なお、オリーブオイルの栄養を意識して摂りたいときは、ぜひ非加熱で食べられるドレッシングとして使うことをおすすめします。
●管理栄養士からのコメント
オリーブオイルは、ポリフェノール類やビタミンEなどを多く含んでいます。 オリーブオイルによっては、苦味や辛味があるもの、まろやかに感じるものなど様々あります。苦味や辛味はポリフェノールによるもので、時間経過とともにまろやかになります。 蓋を開けると空気に触れて酸化が始まるので、使用後はしっかり蓋を閉め、冷暗所での保管をおすすめします。 熱にも強いため様々な料理に使うことができますが、摂取のし過ぎには気を付けましょう。
管理栄養士プロフィール
鶴田 ようこ
調理師・管理栄養士。2つの資格を生かし食用油脂製造会社にて品質管理に従事。
菜種油、オリーブ油の品質に関する分析、衛生管理等を行う。
幼い頃から野菜作りの手伝いをしていたことから、季節の野菜料理が得意。